私の東大合格体験記 part22
どうも、フジです。
過去の記事のリンクは最後に載せていますので、そちらも読んでいただけると幸いです。
最後まで変化をつけるな
センター試験が行われてから二次試験本番まで、約1ヶ月の猶予があります。この1ヶ月は死に物狂いで勉強しなければならない期間…なのですが、私は、最後の1ヶ月だからと言っても特に変わりなく、今まで通りの勉強ルーティンをこなしました。勉強ルーティンを確立していたおかげで、不安や焦りで乱れることもなく、淡々と、そして着実に実力を高めていくことができたなと思っています。
過去問漬けの1ヶ月?
違います。
最終確認の1ヶ月です。
毎日1時間は英単語の復習をするし、毎日30分は古文単語の復習をする。リスニングの練習は毎朝欠かさず行っていたし、頑張ってまとめた世界史ノートは毎日1周余すことなく目を通していた。高校の授業がなくなったので、自由に使える時間が増えた分、過去問に触れている時間が多くなりはしましたが、どこまでいっても”知識の定着”が最優先。どれだけ完璧に覚えきれるかが勝負、どこかで妥協したら負けだと思っていました。
そう、センター試験が終わると、高校の授業は自由参加になったんですよ。高校のカリキュラムが終了して、最後の1ヶ月だけ、志望校別の対策講座が開講される…。自由参加だと言われていたので、私はそれには全く出席していませんでした。生活のルーティンを崩したくはなかったので登校してはいましたが、空き教室に篭って自分で勉強していました。何度も先生が「授業出た方がいいよぉ」と呼びに来ていたんですが、「自分の実力の伸ばし方は自分が一番よくわかってるんだから、この期に及んで学校の授業に頼る必要なんてないかな」と思ってお断りさせていただいてましたね。
ちなみに、過去問の扱い方ですけど、こちらも今まで通りです。どの教科も各大問ごとに目標時間を設定していたので、その目標時間内に解く練習をしていました。”過去問を解くこと”と同じくらい、過去問を解くことによって”暗記し損ねている知識を拾うこと”を重要視していました。解答解説を読み込んで、吸収できるものは全て吸収していく。解説の読み込みには、問題を解くのと同じかそれ以上の時間をかけていた記憶がありますね。
本番直前の東大模試
2月の初めに、某予備校が実施している東大模試を受験してきました。本番前最後の模試ですね。
多くの受験生が受けている記述式模試なのにも関わらず、結果が1週間もないくらいで返ってくるあたりからもお察しですが、採点が雑なので点数も判定もほとんど当てになりません。ただ、他の受験生のほとんどが受けているのに、自分だけ受けていないというのは明らかなディスアドバンテージだなと思って受けました。
点数は以下の通り。
国語49
数学60
英語72
世界史45
地理36
しれっと過去最高得点。雑な採点に救われた感じでしたね。「一応ここからも暗記漏れを回収できればいいな」くらいのノリで臨みましたが、偶然にも高得点を取れちゃったおかげで、もともとあった自信がさらに増幅。
東大に落ちるビジョンなんて、見ようと頑張っても見ることができませんでした。
【過去の記事はこちら】
小学校・中学校
part1, part2, part3
高校1年生
part4(地方公立高校でよかった)
part5(部活を辞めて帰宅部になった話)
part6(夏休みの過ごし方)
part7(文化祭・体育祭と勉強の両立)
part8(私の文理選択)
part9(冬休みの過ごし方)
高校2年生
part10(高2最初の実力テストの罠)
part11(高2で受験する志望校の冠模試)
part12(分析の重要性)
高校3年生
part13(赤本のご準備を)
part14(高3夏の東大模試)
part15(東大模試分析)
part16(高3の学校行事)
part17(高3秋の東大模試)
part18(センター地理対策)
part19(東大地理対策)
part20(センター試験本番)
part21(志望校確定)
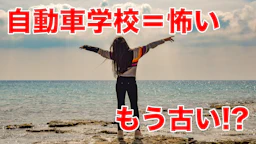
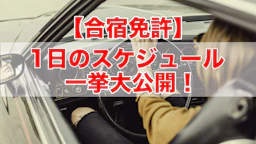


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)




