私の東大合格体験記 part12
どうも、フジです。
今回はちょっと気合が入ってしまいまして、いつもより分量が多めです。ですが、その分皆さんの参考になるところはあるかと思いますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
この記事だけで完結するようにはしていますが、先に part11 までを是非。
最後にリンクを載せています。
軌道修正
高校2年生の秋に受験した駿台の東大実戦模試で、「東大ってこんな感じの問題が出題されるのか」と、そこではじめて目指すべき場所が明確になりました。したがって、やるべきは「何が足りなくてこの問題が解けなかったのか」を分析するということ。
高校2年生の秋から冬にかけては、私にとって「軌道修正」の時期でした。
志望校がどこであれ、ある程度基礎が完成してきたタイミングで過去問を1度解いてみる(冠模試があればそれを受験するのがベスト)。そして、自分に足りないものが何なのかを分析する。非常に大切なことだと思います。
当時の私に足りなかったもの
みなさんの得点力不足の原因が、私と同じである可能性もありますから、当時の分析結果を詳細に書き記しておきます。
国語
国語の点数は120点中36点。合格するなら75点は目指したいところ。
現代文
現代文は、何度も何度も本文を読み返して考えるという圧倒的非効率スタイル。
細かい部分にフォーカスしすぎていて、文章全体がどういう論理展開なのかを全く把握できていませんでした。そのため、読み終わる頃には「あれ?結局どういう話をしてたんだっけ?」となってしまう…。
解決策として、現代文を読むときはいつも段落番号を振り、意味段落に分けるようにしましたね。
そうすることで、本文全体の構成や論理展開を意識しながら読み進めることができるようになりました。中学受験以来、現代文ではなんとなくでしか解答を書けていなかったのですが、これをするようにしてからは「文章構成的には下線部の言い換えはここにあるな」というようなことを考えながら論理的に問題を解くということができるようになりました。
古文
古文は、古文単語(単語帳に載っているもの)をしっかりと覚えているおかげで逐語訳はそこそこできるのですが、省略されている主語や目的語を適切に読み取ることができておらず、つじつまの合う物語を自分で勝手に作り上げてしまっているという問題点がありました。また、古文は英語以上に語意の文脈判断を求められる節がありますが、それがあまりにも苦手だという点。
解決策として、普段から主語と目的語を意識して読み、なぜそう判断できるのかをきちんと考えるようにしました。また、「文脈判断能力」に関して、こればっかりは努力で向上させることができるという確信を持てなかったので、文章中に出てきた知らない単語を覚えるようにしたり、古語辞典から重要そうな単語をピックアップして暗記したりと、知識量でカバーする方向性で進めました。
要は、力技です。
漢文
漢文は、読みやすい年と読みにくい年があると知って、運ゲーだなと思っちゃいましたね。
読みやすさに左右されず確実に高得点を狙えるだけの実力をつける労力を考えた時に、漢文の配点がたったの30点(全教科合計440点満点)であることを思うと、どう足掻いても他の科目•教科に時間をかけたほうがいいという結論にいたるわけです。「長いスパンで見て、最終的にセンター試験レベルに到達できればいいかな」くらいの認識に落ち着きました。
国語はまだ自主的に過去問を扱うには至っていません。高3の半ばくらいからだったような気がします。学校の授業だったり、補習だったりで扱う問題(自分のレベルに見合ったやつ)を丁寧に解くようにしていました。
数学
数学なのですが、80点中30点というのは思いのほか高得点でして、自分のやり方は今のところは間違ってなかったのかなという安心感を得ることができましたね。一応「数学で差をつけろ」というコンセプトで文系をやらせてもらっていたので、目指すは80点中60点だなと少し高めの目標を定めました。
青チャートをほぼ完璧にしてからは、学校での数学の授業時間以外に数学の勉強をすることはあまりありませんでした。学校の授業はその内容が自分的には物足りないものだったので、全く聞いていません。授業前にその授業で扱う範囲の問題を見て「この問題はこういう方針でいけば答えまで辿り着きそうだな」とイメージするくらい。
この頃から授業中は、赤チャートのエクササイズや章末問題に取り組んだり、大学への数学に掲載されている難しめの問題を解いたり…。赤本を買って解くようになったのは、高校3年生になってからでしたね。
英語
英語は120点中32点で、受かるためには最低でも70点はないと厳しいなといった感じ。どの大問にどれだけの時間をかけるか、どういう順番で解いていくかを事前に決めていなかったせいで時間効率が悪かったという点を差し引いても、32点は低すぎる点数です。
英語も古文と同様、単語はある程度わかるので、逐語訳をする分にはあまり苦労はしません。そのため、英文を読み進めていくこと自体は可能です。が、読み終えた時に「結局これってどういう文章だったんだ?」となってしまう。現代文と同じです。
これの原因は、文章構成を気にしていないという点はもちろんあるのですが、それ以上に「指示語の指示内容や文中の省略部分を意識せずに、ただ英語を日本語に直すだけ」の読み方をしていたという点があるでしょう。この問題点は、簡単な文章や短い文章ばかり読んでいると気がつけません。特に意識しなくても、指示内容や省略部分なんてなんとなくわかってしまうからです。
あとはシンプルに語彙力不足も感じましたね。私は鉄壁を完璧に覚えてはいたのですが、いかんせん意訳が苦手でして。難単語というよりはむしろ、誰でも見たことあるような単語の意味を覚えるべきだなと考えました。
例えば past という単語。ほとんどの人はざっくりと「過去(名詞)」くらいのイメージしかないはずです。なぜなら高校生が使うような単語帳にわざわざ載っていないから。ですが、辞書で調べてみると副詞の意味があったりするわけです。past が副詞で出てきた時、その品詞の意味があることを知らなければ、完璧な和訳は不可能に近いでしょう。
私が最初に買った赤本は、東大英語の赤本でした。
英単語等の基礎を忘れないよう復習には1時間以上の時間をかけていましたが、それをこなした上で何をしようかとなった時に、過去問の中から1題をピックアップしてじっくり読むということをしていましたね。最初はスピードは気にせず、ミスなく読むことに注力していました。指示語や省略部分を意識して...。
あ、一応言っておきますが、学校の授業で扱う長文はサラッと読んでいるので、東大の過去問以外で英文に全く触れていないというわけではありません。
こんな感じです。
本当にいろんなことを考えながら勉強していましたね。4年前のことなのに、これだけ詳しく書き起こせるのもどうなんだって気もしますが(笑) 参考になっていれば幸いです。
これ以前の記事はこちら↓
小学校・中学校
part1, part2, part3
高校1年生
part4(地方公立高校でよかった)
part5(部活を辞めて帰宅部になった話)
part6(夏休みの過ごし方)
part7(文化祭・体育祭と勉強の両立)
part8(私の文理選択)
part9(冬休みの過ごし方)
高校2年生
part10(高2最初の実力テストの罠)
part11(高2で受験する志望校の冠模試)
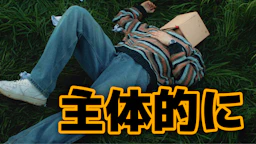

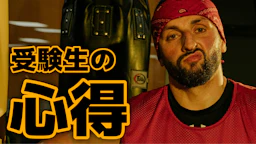

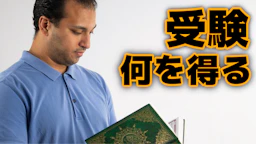
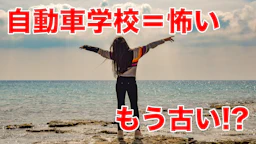
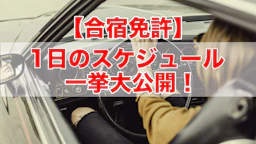


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)







