私の東大合格体験記 part19
どうも、フジです。
前回はセンター地理対策に関する内容を書きました。今回は、東大二次試験地理対策編です。過去の記事のリンクは最後に載せていますので、そちらも読んでいただけると幸いです。
どうやる?東大地理対策
ここから先は、東大を志望していて地理の勉強法に悩んでいる方向けです。
参考になるかはわかりません。
まず、初めて東大の地理に触れたのは高校2年生の秋に受けた東大模試。考えても考えてもさっぱりで、ほとんど空欄で提出した記憶があります。「まだ高校2年生だし、世界史と地理はできなくて当然だよね」と言われていたこともあり、その時は復習なんて全くしませんでした。
それ以降過去問を目にする機会はちょいちょいあったのですが、問題ときちんと向き合ったのは高3夏の東大模試が最初ですね。
さすがに高3の夏ともなると復習もするので、そこで「東大の地理はどんな問題がでてるんだろう」「どういう力が必要なんだろう」と考えるわけです。当時の敗因は明らかに知識不足にあったことは言うまでもありませんが、それとは別に「図表を読み取り因果関係を記述する」タイプの問題が多いなという印象を抱きました。センター試験で必要な知識に加えて、様々な因果関係のパターンを覚える必要があるなと思ったんですよね。
頭がキレる人であれば、じっくり考えることで自分の持っている知識と知識を結びつけ、その場で因果関係を見出すという高等技術が使えるのかもしれませんが、少なくともそれは私には無理だと確信していました。その力をどうやったら養えるのかもわからないし、無策にひたすら問題に当たるにしてもその力が伸びる確証もない。ならば無謀だが因果関係のパターンを可能な限り覚えてしまおう、という結論に至ったわけです。
英語の意訳が苦手で、鉄壁の英単語を全て辞書で調べて細かい意味まで覚えたり、古文単語の類推が苦手で、辞書に載ってる重要そうな単語を自分で選んできて覚えたり。私はセンス(?)のなさを量でカバーするタイプだったので、地理でこういう結論に至ったのも至極当然のことでした。
信じた道なら回り道でも正解である
東大地理のための対策を本格的に始めたのは高3の秋だったような気がします(当然センターレベルの知識のインプットと同時並行)。
私は東大の赤本及び青本、駿台、河合、代ゼミの東大模試それぞれ過去数年分を買い漁り、そして全ての解説に目を通し、そしてそこから問われうる因果関係を抽出してまとめ、それを全て暗記するという作業を行いました。国の人口の増加・減少の原因として考えられるものをまとめたり…。非常に骨の折れる作業でしたが、高2秋の東大模試ではほぼ空欄状態だったところから、最終的には、なんとか(正解しているかはさておき)自分的に満足のいく解答で解答欄を全て埋めることができるレベルにまでは到達できました。
ちなみに、よく各所で紹介されている帝国書院の「地理の研究(黄土色のやつ)」や「地理の完成(白っぽいやつ)」も一通り読みましたが、解答作成に使えそうな因果関係はあまり載っていなかったなあという印象でしたね。
解答欄を全て埋めることができるレベルにまで到達はしたのですが、それが「覚えた因果関係のパターンがテストで使えたから」なのか「様々な因果関係に触れていくうちに、自分の持ち合わせた知識から因果関係を見出す力というのが養われたから」なのかが私にはわかりません。
勉強法の記事を書く時はどこかにこの言葉を添えるようにしているのですが、やはり「正解はない」んですよね。
自分にはこのやり方が合っているんだと信じてそれを貫き、最後まで継続することが大切なんじゃないかなと思います。
ちなみにこれが私の地理の成績の推移です。
高2秋
駿台 8/60 (偏差値34.6)
↓
高3夏
駿台 19/60 (偏差値51.1)
河合 7/60 (偏差値30.4)
↓
高3秋
代ゼミ 19/60 (偏差値40.0)
河合 9/60 (偏差値28.3)
↓
東大二次試験本番 38/60
小学校・中学校
part1, part2, part3
高校1年生
part4(地方公立高校でよかった)
part5(部活を辞めて帰宅部になった話)
part6(夏休みの過ごし方)
part7(文化祭・体育祭と勉強の両立)
part8(私の文理選択)
part9(冬休みの過ごし方)
高校2年生
part10(高2最初の実力テストの罠)
part11(高2で受験する志望校の冠模試)
part12(分析の重要性)
高校3年生
part13(赤本のご準備を)
part14(高3夏の東大模試)
part15(東大模試分析)
part16(高3の学校行事)
part17(高3秋の東大模試)
part18(センター地理対策)
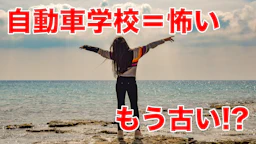
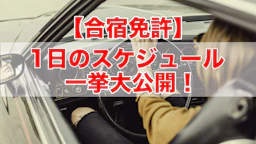


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)







