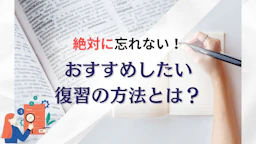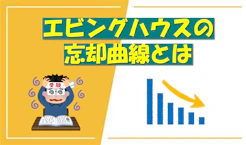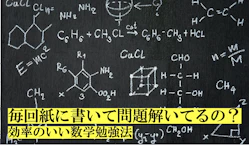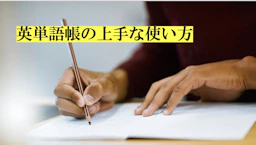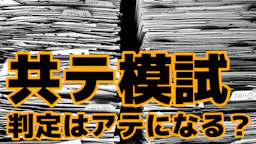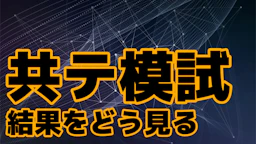正しい模試の活用法
みなさんは、正しく模試を活用できていますか?
模試といえば判定での一喜一憂だけ、といった人が多いんじゃないかとは思いますが、模試もせっかく受けているのですから、うまく活用していきたいですよね。そのためには模試の立ち位置を正しく知っておくことが大切だと思います。
前回の記事で、模試の判定は気にするに値するのかを考えてみました。
前回の内容を踏まえて、模試はどのように活用するのがいいのかを考えます。
受けっぱなしはダメ!
模試の復習はちゃんとするべきでしょう。
前回も書きましたが、中学受験や高校受験の時の私は、模試は受けたら受けっぱなし、判定を友達と比べて盛り上がるといった感じの使い方をしていました。志望校判定はこのくらいの扱いで良いと思いますが、やはり模試を受けっぱなしにするのは勿体無かったなと感じますね。
間違えた問題は、なぜ間違えたのかをしっかり分析します。凡ミスなのか、知識不足なのか。凡ミスであれば、次回以降のテストでそれを再発しないように気を引き締める。知識不足なのであればそれは覚える必要があるので、ノートを作るなり、教科書や参考書に書き込むなり、何かしら後から見返すことができるような状態を作ります。
高校1年生、高校2年生の時に受けた模試は、基本的に教科書や参考書に載っている基本的な内容のことが多かったので、間違えた問題の説明がある部分に付箋を貼って後から見返しやすいようにしていました。
高校3年生で受けた東大模試では、教科書に載っていない内容や、教科書に載っていてもつながりが明示されていないようなものが問われていました。そのため、解答・解説は隅々まで読み込んで、自分に不足している知識はないかをチェックしていました。
英語であれば、英単語帳に意味を書き込む・単語ノートを作る、数学であれば、間違えた問題をファイリングする、世界史であれば、自分で作っていたまとめノートに書き込む...。そこに自分に不足している知識があることが発覚したのなら、それは余すことなく自分のものにする努力をしなければなりません。
模試だけをみないこと
「今回の模試ではしっかり点が取れている、志望校判定もA判定だ、模試の復習も間違えたところはちゃんとした。」
これは現状問題なく勉強に取り組めているということを意味するのでしょうか?
何の心配もない?
前回も述べた通り、1回の模試の問題は、その出題範囲の全てを網羅しているわけではないのです。自分の苦手な分野、単元が出題されていないから、高得点を取ることができたのかもしれません。
志望校が求めている知識量に対して自分が今9割の知識を有しているから、しっかり点が取れていてA判定が出ているのであれば、特に心配する必要はないでしょう。しかし、自分の苦手な分野、単元が出題されていないから高得点を取ることができたのであって、明らかに欠けている部分があるのであれば、それは安心できる結果とはいえません。模試の結果から、自分がどちらのタイプなのかを分析しましょう。
後者なのであれば、この模試の後に何に取り組むべきなのかは明確です。
「志望校に合格するために必要な勉強の完成度に対して、自分が今どのくらいの立ち位置にいるのか」「志望校が求めている知識量に対して、自分が今どのくらいの知識を有しているか」が大切だと前回言いました。自分の立ち位置を、志望校の合格ラインへと近づけるために、まずは自分に欠けているのは何なのか、どの部分なのかを明らかにしましょう。
数学であれば、全ての単元を把握して、できる単元・できない単元に分類する。英語や古文であれば、まだ覚えていない文法をはっきりとさせる。模試に出題されているいない関係なく、自分は何がわかっていないのか、何を知らないのか、何をまだ覚えていないのかをはっきりさせましょう。
次にやることは決まっていますね。
自分に不足しているとわかった部分を、ひとつずつ自分のものにしていくのです。そうすれば、自分の立ち位置は一歩ずつ志望校の合格ラインへと近づいていくでしょう。次の模試でまた判定が微妙だった?そんなの関係ありません。模試で点を取れなくても、あなたは確実に志望校の合格ラインへと近づけています。
目指すのは、受験本番までに「志望校が求めている知識量に対して、自分がその8~9割の知識を有している」状態になることです。