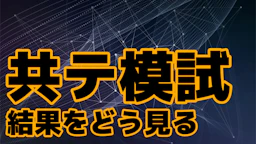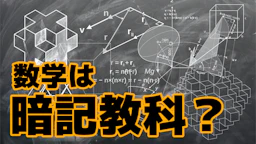共通テスト模試をどうみる?
どうも、フジです。
今回はpart2の記事なので、まだの方はぜひpart1から読んでみてください。
共通テスト模試の判定はアテになるか?
今回の記事では、まず最初に、変にいい成績(高順位やイイ判定)を取っちゃったせいで危機感が薄れてしまった人へ向けて、彼らの危機感を煽るために「そもそも共通テスト模試の判定はアテになるのか」という話をしてみようと思います。
結論から言うと、アテになりません。
理由はザックリ2つ。
まずは、共通テストと二次試験の出来は多くの場合比例しないからです。志望校が難関大学であればあるほど、比例しづらくなっていくのかなと思いますね。東大志望だった私は「なぜ共通テストを模した試験で、合格可能性を測ることができるんだよ、二次試験で問われる能力は共通テストとは全く異なるだろ」と叫ばずにはいられませんでした。東大の冠模試(大学別模試)ではD判定がザラな私でも、共通テスト模試(当時はセンター試験)では常に東大A判定が出ていたので、いかにその判定が無茶苦茶なのかを理解してもらえるはずです。共通テスト模試のA判定なんて、全くもって安心材料にはなり得ないのです。
続いて、そもそも模試自体が運ゲーだからです。「自分の知らない英単語がほとんど出てこなかった」「古文の解釈を偶然ドンピシャに当ててしまった」「数学は自分が得意な単元ばかりの出題だった」といった運要素で、点数は10点や20点くらい平気でブレますし、それだけで判定だって変わってきます。総合得点が50-100点レベルで変動したというのなら、それは実力の変化を認めるに値するのかなと思いますが、そうでもない限りは、たとえ判定や順位が揺れ動こうと、それは「誤差」とみなすべきだと私は考えます。だから、少し判定が良くなったからと言って、今A判定を取れているからと言って、浮かれていてはいけないのです。
というわけで、共通テスト模試の判定なんてものは全くアテにならず、「共通テスト模試で変にいい成績(高順位やイイ判定)を取っちゃったせいで危機感が薄れてしまう」なんてこと自体がおかしな話というわけです。
模試で見るあいまいな立ち位置なんて、努力の指標にしてはならない
しつこいようですが、模試の順位や判定なんてのは全く持って参考にならない指標なんですよ。
したがって「模試でA判定を取るために頑張ろう」といったように、個人的には模試の判定(他の受験生と比べた時の自分の立ち位置)を努力の指標にするのは間違っているような気がしています。
では何を努力の指標にすべきなのか。
私は「志望校に合格するために必要な勉強の完成度に対して、自分が今どのくらいの立ち位置にいるのか」「志望校が求めている知識量に対して、自分が今どのくらいの知識を有しているか」という、絶対的な尺度、これを努力の指標にするべきだと考えています。模試の判定なんてどうでもいいんですよ。手持ちの英単語帳、古文単語帳、青チャート、世界史の参考書、これらがどの程度完成されているのか、大事なのはそこじゃないですか?
模試に出題されているいない関係なく、自分は何がわかっていないのか、何を知らないのか、何をまだ覚えていないのかをはっきりさせましょう。そして、自分に不足しているとわかった部分を、ひとつずつ自分のものにしていくのです。そうすれば必ず、あなたは着実に志望校の合格へと近づくことができるでしょう。次の模試でまた判定が微妙だった?そんなの関係ありません。模試の成績が芳しくなくても、あなたは確実に志望校合格へと歩みを進めています。
というわけで、共通テスト模試に関しては以上です!ご質問、ありがとうございました!質問やリクエスト、めちゃくちゃありがたいです!本当に、どんなしょうもないことでも構わないので、超気軽に質問•リクエストを送ってもらえると嬉しいです。アプリokkeのマイページの「コメント・要望」の部分から是非(フジ宛と明記しておいてもらえると助かります)。