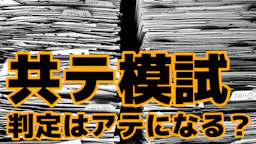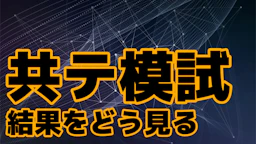数学は暗記は必要だが暗記教科じゃない
どうも、フジです。
皆さんは「数学は暗記教科だ!」という話、聞いたことありますか? 巷では、ちょくちょく囁かれているこの言説、取り違えている人が多いような気がするので、今回はこれについて深掘りしていこうと思います。
数学でも暗記は必要である
数学において暗記は必要不可欠です。当たり前です。ぶっちゃけ「なぜ数学で暗記が必要ないと錯覚していた?」って感じです。知識が頭の中に記憶されていないと、試験問題なんて解けるはずもないのです。それを考えると、そもそも暗記が不要な教科なんてこの世には存在しない、数学も含め全教科で暗記が必須だと言えるでしょう。
「数学は暗記教科だ」というのは、数学という教科の性質上「解けて満足、解けなかったけど解説を読んで納得して満足」で終わってしまう人が多いからこそ、「ちゃんと覚えようと思って取り組まないと、試験問題を解けるようにはならないよ」ということを念押しする、そういう意味合い(暗記の必要性を強調する意図)で言われているわけですね。
はい、ここまでで「ただただ参考書の解法を暗記しておけばいいよ」という話ではないことに気がつけた人は素晴らしいですね。
「数学は暗記教科だ」と言われて、これを「数学も、世界史や日本史のように、シンプルに暗記だけをしてりゃあいいってことか!」と解するのは明らかに誤りです。確かに解法を覚えておくことは必要不可欠ですが、解法を暗記してさえいれば数学ができるようになるのかと言われると、そんなはずがないのです。したがって、世界史や日本史のような教科を暗記教科とするならば、数学は暗記教科ではないということになります。
まあ、参考書の解法を闇雲に丸暗記するだけでも”数字を変えてみただけです”的な問題、つまり学校の定期テストあるあるな問題なら解けるようになるのでしょうが、それで数学ができるようになったと言うのには、やや無理があります。
数学は「なぜ?」が重要
数学を得意科目にしたければ「なぜ?」を常に意識する必要があるでしょう。青チャートのような参考書を解くにしても、志望校の過去問を解くにしても、結局「なぜそのような処理をするのか」「その処理を行うことで、どんな嬉しいことがあるのか」という、「なぜ?」を意識することが非常に大切なんです。暗記以前の問題、理解の段階の話です。
単純な解法丸暗記では、前節でも述べた通り数字が変わっただけな問題であれば対応可能ですが、それ以上の問題に対応することができないんですよね。これじゃあ「道具の存在は知っているが、その道具をどのように使うのか、何のために使うのか、どういう時に使うとよいのかは全く知らない」という状況に他なりません。そりゃ応用なんて効くわけがないんですよ。
「なぜ?」を意識した勉強をする、解法と一緒に、この「なぜ?」を覚えておくことで、数学は一気に得意科目になるんじゃないかなと私は思います。
模試の復習はどうやる?
先日のokke主催東大キャンパスツアーの中で、参加してくれていた方から「数学の模試の復習ってどうやって行なっていましたか?」という質問を受けました。今回のテーマと関連がある話なので、ここで取り上げます。
皆さんは数学の模試の復習、どのように取り組んでますか? 模試の復習もそうですし、過去問演習なんかもそうですが、やりがちなのは「とりあえず何回か解き直して、正解できるようにする」ってやつ。これをやっちゃってる人、少なくないと思いますよ。
前節までを読んでくれた方なら、この勉強法の無意味さを容易に理解することができるでしょう。
やはり大切なのは「なぜ?」という視点。
「この段階(例えば問題を読み終えた段階や最大最小問題の立式が終わった段階など)で、ここから先どのような進め方が考えられるのだろうか?」「数ある選択肢の中でなぜこの進め方が選ばれるのだろうか?」といった部分をきちんと理解して、ストックしていく。これが正しい模試の復習法なんじゃないかなと思います。
私は、高校3年生の間は、東大/京大/一橋の過去問、東大模試の過去問をメインに扱っていましたが、同じ問題を何度も繰り返し解くということはあまりしていませんでした。「この問題はこういう話だから、ここをこうすることによって、こんな感じになって、んでこれをこうしたら、こうなるから、こうしてこうしてこうすれば解ける!」というのをザックリと思い返してみるとか、そういう軽い復習で済ませることが多かったですね。もちろん、細かい処理を確認したいときは解き直すこともありましたけど。
というわけで、今回は以上。
数学の勉強の参考にしてください。