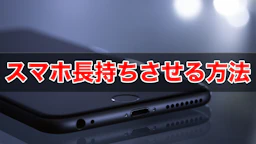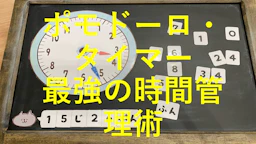勉強モードに入るには「助走」を設計せよ
どうも、フジです。
今回は、「堕落した状態からいきなり勉強モードに入るのはしんどい」というお話。
一度ダラダラしてしまうと、そこから急に勉強に切り替えるのって本当に難しいですよね。ベッドの上でスマホをいじっている状態から「さあテキストを開こう」と思っても、頭も体も動かない。しかも、同じ空間で長時間くつろいでいると、その空間そのものが「休む場所」として固定されてしまいます。だからこそ、気合いで「よし、やるぞ!」と切り替えようとするのは無理があるんです。
だから大切なのは、いきなり勉強を始めようとしないこと、「どうやったら勉強を始めやすい流れを作れるか」を考えることです。勉強そのものを始める前に、その前段階の“助走”を意図的に設計しておくんです。
場所を変えてみよう
最初の助走としておすすめなのは、やっぱり「場所を変える」こと。過去の記事で何度も触れているような気がします。
勉強道具を持って、家の外でもいいし、別の部屋でも構いません。とにかく、“堕落している場所”から物理的に離れてください。そうするだけで、ひとまずは「勉強スタート」に一歩近づけます。
この行動の意味は「せっかく場所を変えたし、何かやらないとな」という気持ちを生み出すことにあります。つまり、移動という行動そのものがもったいなさを作り出すんです。「ここまで来たんだから、少しだけでも勉強して帰ろう」と思えた時点で、もうスタートラインに立っています。最初の頃は、勉強を始められてもすぐに帰宅してしまう…かもしれませんが、続けていくうちに長居して勉強できるようになるはずです。
ちなみに、場所にもこだわれるといいですね。カフェでも図書館でも自習室でも構いませんが、「落ち着いてテキストを開ける環境」を自分なりに見つけておくと、勉強スイッチを入れやすくなります。
「せっかく〇〇したし」という連鎖を作る
「せっかく場所を変えたし、何かやらなきゃ」と思えるのが、行動を変えることのポイントでした。つまり、勉強モードに入るためのコツは、こうした“せっかく〇〇したし”を複数作ることにあります。
たとえば、「せっかく服を着替えたし勉強しよう」「せっかく机の上を片付けたしやらなきゃ」「せっかくタイマーをセットしたし始めよう」「せっかくシャーペンを出したしちょっと書いてみよう」とかね、こうやって自分の行動を細かく分けて、それぞれに小さな“もったいなさ”を仕込んでいくんです。そうすれば、どんなにやる気がなくても「ここまでやったのに何もせず終わるのは気持ち悪い」という心理が自然と働きます。人間は「行動を無駄にしたくない」生き物です。その性質を味方につけましょう。
勉強モードに入るまでを「一段の階段」と捉えるから苦しいんです。それを「小さな階段を数段登る」と考えれば、だいぶ楽になりますよ。実際にテキストを開いて勉強を始める前に、ハードルの低いステップを複数並べておけばいいんです。助走をつけなきゃね。
「勉強を始める前の行動」をルーティン化してみる
こうした“助走ステップ”を繰り返していくうちに、自然とそれがルーティン化されていきます。たとえば、「服を着替える→机を片付ける→タイマーをセットする→テキストを開く」といった流れが、自分の中で「勉強を始めるまでの一連の動き」として定着していくわけです。
この段階まで来ると、もう「やる気があるかどうか」に左右されにくくなります。この流れをしたら勉強が始まるというのを脳が覚えてくれるため、特別な決意がなくても自然と体が動くようになるでしょう。
同じ”助走ステップ”を日々意識して続けていけば、最終的には「特別な準備をしなくても自然と勉強を始められる」状態になっていく、つまり、助走を重ねた先に“習慣”ができあがる。そこまで行けば、勉強はもう「始めるもの」ではなく、「気づいたら始まっているもの」になりますね。
「堕落した状態」からいきなり勉強を始めようとするのは、誰にとっても難しいことです。でも、そこに“橋渡し”をつくれば話は変わります。「せっかく〇〇したしやらなきゃ」と思える小さな行動をいくつも積み重ねる。最後にはその流れがルーティンとなり、自然と勉強モードに入れるようになる。人は気分ではなく流れで動く、だからこそ、勉強の「始まり方」を設計しておくことが、最強の勉強法なんです。
というわけで今回は以上。