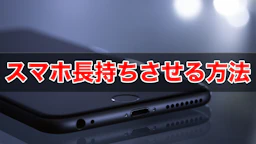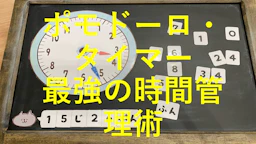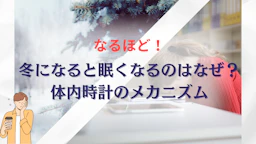睡眠は量より質!
どうも、フジです。
今回は「睡眠」について。
受験生にとって睡眠は「削るもの」というイメージが強いんじゃないでしょうか。私自身、遥か昔に「夜遅くまで起きていれば、そのぶん勉強時間を稼げる」と思い込んでいた時期がありました。けれど実際には、徹夜した翌日は頭がぼんやりして、ほとんど何も覚えられない。机に向かっている時間こそ長かったものの、効率は最悪でした。
この経験から学んだのは、睡眠を削ることは勉強にとってプラスどころかマイナスだということ。だからこそ今回は「睡眠は量より質を意識すべき」というテーマでお話ししていきます。
最低限の時間は削れない
まずはっきりさせておきたいのは、「量を削っても質でカバーできる」という考えは誤りだということです。
睡眠はただ体を休める時間ではなく、脳が情報を整理して記憶を定着させるための時間でもあります。日中に暗記した英単語や解いた問題は、寝ている間に脳が「長期記憶」として保存する。だから睡眠時間を極端に削ってしまうと、せっかく勉強しても知識が定着せず、むしろ効率が落ちてしまうんです。
実際、睡眠が5時間以下の生活を続けると、集中力が下がるだけでなく免疫力まで落ちると言われています。体調を崩して勉強が止まってしまったら本末転倒ですよね。だから「最低でも6時間程度は寝ること」。これは譲れないラインです。そのうえで7時間前後をとれていれば十分で、そこから先は「質をどう高めるか」が勝負になります。
質を高める習慣
では、どうすれば睡眠の質を上げられるのか。ここからは具体的な習慣を見ていきましょう。
まず大事なのは「寝る前の過ごし方」です。直前までスマホを見たり、ベッドで動画を流したまま寝落ちする人はめちゃくちゃ多いと思いますが、これは眠りを浅くする原因になります。ブルーライトが脳を刺激して「まだ昼間だ」と勘違いさせてしまうからです。私のおすすめは、寝る30分前にはスマホを閉じて、代わりに軽いストレッチや読書(もちろん参考書…!)に切り替えること。リラックスできて寝つきも良くなります。
次に「生活リズムの一定化」。毎日寝る時間と起きる時間がバラバラだと、体内時計が乱れて深い睡眠に入りにくくなります。受験勉強中はつい夜更かししてしまいがちですが、少なくとも「起きる時間」だけは一定に保つと体内リズムが安定しやすく、眠りの質も改善されます。
さらに「日中の活動」も大きく関わります。朝に太陽の光を浴びると、夜に眠気を誘うホルモンがしっかり分泌されるようになります。また、昼間に軽い運動をすると深い眠りにつながります。私も受験期には散歩を兼ねて英単語を覚える習慣を取り入れていましたが、そのおかげで夜は自然に眠れるようになっていました。
そして忘れてはいけないのが「環境づくり」です。スタバなどのカフェで集中できる理由のひとつに「環境の力」があるように、睡眠でも環境が大きく作用します。部屋をしっかり暗くする、外の音を遮断する、エアコンで温度を一定に保つ。こうした条件を整えるだけで、眠りの深さは驚くほど変わります。寝具についても、自分に合った枕やマットレスを選ぶことで寝返りがスムーズになり、熟睡感が得やすくなります。
勉強効率を支える睡眠の質
ここまでをまとめると、「量」は最低限確保しつつ、その先は「質」を意識することで、睡眠は学習効率に決定的な影響を与える、ということです。
では具体的に、どんな形で勉強に影響しているのかをもう少し掘り下げてみましょう。
まず大きいのが「記憶の定着」です。人間の脳は、新しく覚えたことを短期記憶として一時的に保存しますが、それを長期記憶へと移す作業は睡眠中に行われます。特に、深いノンレム睡眠の段階では、その日にインプットした情報が整理され、「重要なもの」と「不要なもの」とに振り分けられるのです。だから、しっかり深く眠れている人は、同じ時間勉強しても覚えたことが頭に残りやすい。逆に眠りが浅いと、努力した内容が定着せず、忘れやすくなってしまうんです。
次に「思考力・集中力」への影響です。私も経験がありますが、睡眠不足の状態では問題文を読むスピードが落ち、簡単な計算や論理展開でつまずくことが増えます。つまり、頭の処理速度そのものが落ちてしまうんです。たとえ机に向かって長時間勉強していても、普段の半分程度の効率しか出せないとなれば、時間を無駄にしているのと同じ。深く眠ることで脳の疲れがしっかり取れ、翌日はクリアな頭で勉強に臨めるわけです。
さらに「感情の安定」も無視できません。睡眠が足りないとイライラしやすくなり、些細なことで集中が切れてしまいます。受験勉強は長期戦なので、モチベーションを保つには心の安定も必要不可欠です。深い睡眠をとれていると気持ちが前向きになり、勉強に向かう姿勢そのものが変わってきます。
つまり、睡眠は単なる「休憩時間」ではありません。記憶を固め、思考力を維持し、感情を安定させる…この三つを支える基盤こそが「睡眠の質」なんです。机に向かった時間の長さよりも、どれだけ深く眠れているか。その差が、結果として学力の伸びを大きく左右するのです。
受験期は「少しでも長く勉強したい」と思うもの。でも実際には、睡眠を削って時間を稼ぐより、質の高い睡眠で頭をクリアに保つほうが何倍も効率的です。
必要な睡眠時間を確保しつつ、寝る前の習慣や生活リズム、環境を整えて眠りの質を上げる。これこそが、勉強を最後まで走り切るための土台になります。
というわけで今回は以上。