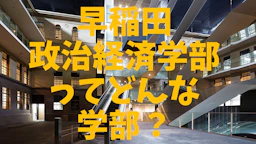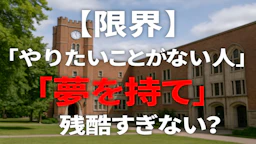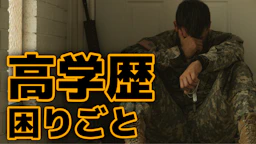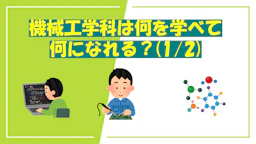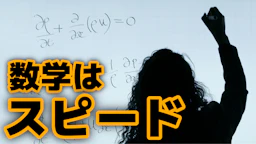科目を減らすのは「逃げ」ではないか?
どうも、フジです。
今回は、高3の秋ごろによく見られる「科目を減らす」という選択について。
受験も終盤に差し掛かるこの時期、焦りや不安から勉強の方針を大きく変えようとする人が増えてきます。そんな中でよく見られるのが「もうこの科目はやめようかな」「2教科で受けられる方式に変えようかな」といった判断です。一見すると合理的で、戦略的にも聞こえるかもしれません。しかし私は、このタイミングで科目を減らすのはあまり良い判断ではないと思っています。
早期に科目を絞るのはいい戦略
中学受験は国算理社、高校受験は国数英理社、どちらも全ての教科を当たり前のように使います。私は東大専願で東大以外を視野に入れたことがなく(滑り止めを受験する気もなかった)、そして東大は国数英理社の5教科全てを使用するため、大学受験も当然5教科全てで戦うものだと思っていました。
しかし実際には、5教科をすべて使う大学などほとんど存在していません。探せば2教科で受けられる大学もあれば、1教科で受験できてしまう大学すらあるわけです。同じ大学の中を見ても、受験方式が複数あり、使う教科数を臨機応変に選択できる場合も少なくありません。
だからこそ、早い段階で志望校を定めることができたのなら、必要のない科目の勉強をやめ、自分が受験で使う科目に全力を注ぐという戦略は非常に有効です。行きたい大学が明確で、そこで必要な科目が限定されているなら、理にかなった良い判断だと思います。
高3秋に科目数を減らすのは…
一方で、高3の秋にもなると「使う科目を減らそう」とする受験生が出てきます。すでにある程度絞っているにもかかわらずさらに減らそうとする、今回は「3科目から2科目に減らそうとする人」を想定して書いておりますが、模試を受けても思うように成績が伸びない、このままでは合格できないかもしれない、そうした不安の中で「志望校を下げるのではなく受験方式を変えることで使う科目の数を減らそう」と考える人が増えるのです。
一見すると、非常に合理的な選択に見えます。ですが実際には、ほとんどの場合この判断はうまくいかないのかなと思います。
なぜなら、この時期に科目を減らそうとする受験生の多くは、「より勝てる土俵に変える」というより「負けそうな土俵から降りる」発想になっているからです。明確な戦略というより、成績が伸びない科目から逃げるために科目数を減らしているのです。
もともと極少ない科目数で受験する層というのは、それらの科目が圧倒的に得意で、足を引っ張る科目を排除した方が合格率が上がると出願時に判断した人たちです。つまり「(ギリギリのタイミングで)より勝てる土俵に変える」タイプの人たちです。対して、逃げの一手として苦手科目を切った人は、残された科目が特別得意なわけでもないことがほとんどでしょうから、もうその時点ですでに不利な状況にあるのです。
加えて、このメンタリティで科目を減らした人に共通して言えるのは、切った科目に使っていた時間が本当に残された科目に回されるかといえば、極めて怪しいということです。ちゃんとそれができたとしても逆転できるかは微妙なスタートラインなのに、むしろ気持ち的な余裕が生まれたことで勉強の緊張感が薄れ、残された科目の勉強の強度まで下がってしまうケースが多いように思います。結局、科目を減らすことで集中できるようになったというよりも、「安心してしまった結果、全体の密度が落ちた」というパターンの方が圧倒的に多いのです。
そして何よりも、科目数を減らすということは、リスクを一点に集中させるということを意味します。多くの科目で受験する場合には、苦手分野を他の教科でカバーすることができます。例えば、英語で失敗しても数学と理科で取り返すといった補完関係が成り立つわけです(1教科の失態を複数教科で補えるのがデカい)。しかし科目を減らしてしまうと、そのバランスが完全に崩れます。1つの科目で失敗したら、それが致命傷になってしまう可能性が高すぎる。本番でのミスや出題傾向の変化、当日の体調など、どんな不確定要素があるかわからない以上、リスクを集中させるのはあまりにも危険です。
だからこそ、「圧倒的に得意で、安定して結果を出せる科目だけに絞る」場合を除いて、この時期に科目数を減らすのは得策とは言えません。むしろ、まだ伸び切っていない科目があるなら、そこで踏みとどまり、もう一段階伸ばしに行く方が結果的に良い方向に働くことが多いのです。
この時期に科目を減らしたくなる気持ちは痛いほどわかります。しかし、不安な時こそ腰を据えて粘ることが大事です。逃げずに向き合うその姿勢こそが、最終的にあなたを合格へと導く力になります。
というわけで今回は以上。