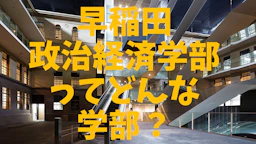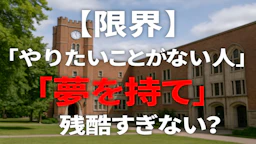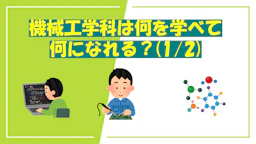学歴があって困ること
どうもフジです。
今回は、「学歴があることで逆に困ることもあるんだよ」という、ちょっと逆張りっぽく見えるかもしれないテーマについて、丁寧に掘り下げていきます。
私は以前の記事で、受験勉強を頑張って得られるものとして「学歴というプラチナチケット」がある、という話をしました。それは今も変わらず事実だと思っています。学歴によって広がる可能性、社会的な信用、就職時の選択肢、人生の土俵そのものが一段上がる感覚…その価値は確かに大きいです。
ただ今回は、その“チケット”が思わぬところで足を引っ張ることもあるという側面に焦点を当ててみたいと思います。学歴の価値やメリットを十分理解したうえで、それでも「それがあるからこそ感じる不自由さ」もある。これは実際に高学歴と呼ばれる大学に進んだ人たちの中で、誰もが一度は感じる感覚なんじゃないでしょうか。
というわけで今回は、「学歴という肩書きの裏にある“静かな足枷”」について、具体的に見ていきましょう。
「高学歴=常に完璧であれ」という見えない期待
まず最初にあるのが、学歴を持っている人に対して周囲が勝手に抱く“期待”です。
たとえば、ちょっとした場面で物事をうまくこなせなかったときに、「あれ?〇〇大って聞いてたけど意外と普通だね」と言われる。あるいは、難しい話に対して答えられないと、「〇〇大のクセにその程度?」とがっかりされる。別に本人は、偉そうにしているわけでも何でもないんですよ。ただ、学歴があるという一点によって、「できて当然」というフィルターをかけられてしまう。これはなかなかしんどいなあと思います。
私は過去にCoCo壱で働いていたことがあるんですが、働き始めてまもない頃にこういうシチュエーションはよくありましたね。「これってこうで合ってますか?」と尋ねると「これはこうだってこの前教えたよね?東大生なんだから1回で完璧に覚えられるでしょ?」みたいなことを言われるわけですよ。念の為確認しただけなのに!他にも、「こういうときどうするんですか?」と尋ねて「ちょっと考えたらなんとなくわからない?東大生でしょ?」と言われたこともありますね。自分で考えて動いてミスるより事前に尋ねてミスらないほうがどう考えてもいいじゃんと思いましたけど。
まあこんな感じで、外からの期待がストレス源になることもよくあるわけなんですが、これ、次第に自分自身の中に入り込んでくるのが最も厄介なポイントですよね。「できて当然と思われてるだろうから、恥をかかないようにしよう」とか、「ここで知らないって言ったら負けだ」みたいな防衛意識が芽生えてしまうんです。その結果、何をするにも“背負いながら”動くような状態になってしまう。周囲の視線や無言の期待に引っ張られる形で、自分の振る舞いがどんどん“型”に寄っていくみたいな。誰かからの強制もなければ明確な縛りもないんですが、ただ、自分が自分を“そうであらねば”と押し込めてしまうみたいな。これが、高学歴というラベルに付いてくる“見えない重さ”です。
進路選択の“自由”を奪うのもまた、学歴の重さ
「学歴があるからこそ自由な進路選択がしにくくなる」という現象、これもありますね。
ここで最初にしっかり言っておきたいのは、高学歴を手にした人の方が、物理的な意味では確実に選択肢は広がるということです。就職活動でも、進学でも、社会的な信用でも、ぶっちゃけ間違いなく有利ですし、どんな進路を選ぼうと思えば選べます。それは紛れもない事実です。
でも、それとは別に存在するのが「心理的・社会的な縛り」です。つまり、選べるけれど選びづらい、選べるはずなのに選べなくなっているという矛盾です。
たとえば、「学歴に見合わないと思われがちな進路」や、「人から説明しづらい働き方」を選ぼうとしたときに、自分の中にふとブレーキがかかることがあります。
「親があれだけお金と時間をかけてくれたのに、こんな道でいいんだろうか」
「応援してくれた先生や塾の講師に、顔向けできるかな」
「過去の自分が見たら、今の自分の選択をどう思うだろうか」
誰かに直接そう言われたわけじゃなくても、頭の片隅にそうした“まなざし”がよぎるわけですよ。それによって、本来自由だったはずの進路が「それっぽい進路」「分かりやすい成功ルート」へと絞られていくんです。周囲から評価されやすい仕事、見栄えのいい肩書き、失敗しにくい選択肢ばかりが目に入り、本音で「これがやりたい」と思える選択肢は見えづらくなっていく。ここには、「高学歴であること」と「自由であること」が、必ずしも一致しないというジレンマがあるなあと思います。
選択肢は広がった。
でも、選びにくい選択肢も増えた。
それは、学歴というチケットを手に入れた人間だけが直面する、非常に皮肉な現象です。
学歴は「使うもの」であって「従うもの」じゃない
ここまで読んで、「じゃあ学歴なんてない方がいいってこと?」と思った方もいるかもしれませんが、それは違います。学歴なんてあった方がいいに決まってます。可能性も選択肢も、間違いなく広がるんです。プラチナチケットであることには変わりありません。
ただし「使いこなせないとちょっとしんどいかもね」って話。
そのチケットを手にしたとき、人は無意識のうちに「期待に応えなきゃ」と思い込みがちです。親のため、先生のため、周囲の目のため…。でも本当に大切なのは、「自分が自分に応えること」です。
他人の評価に合わせて自分を設計するのではなく、自分の意思に合わせて学歴の価値を設計する。“どんな肩書きを持っているか”ではなく、“それをどう扱うか”がすべてです。だからこそ、進路を選ぶときも人と関わるときも、「私はこうしたい」と静かに言える強さを持ち、学歴があるからこそ自分の軸を見失わないようにすることが大切です。そんな意識を持てる人こそが、高学歴というプラチナチケットを本当に味方につけられる人なんだなと思います。
というわけで今回は以上。