こんにちは北の大学生です!
今回は現在機械工学科に所属する私が、工学部に属することの多い「機械工学科」について、何を学べて何になれるのかを紹介していこうと思います。
もうこの学科に来て3年目ですが、なかなかおすすめ出来る学科だと思っています。
自分の通う北海道大学での体験談ですが、他の大学でもおおよそ似たようなカリキュラムだと思いますので、ぜひ読んでみてください!
何を学べる?
では、まずは何を学べるかについて書いていこうと思います。研究室配属の前と後で学ぶ内容が変わってくるので、分けて書いていきます。
研究室配属の前
まずは研究室配属の前です。
研究室へは3年生の後期、または4年生の前期から配属されることが多いのですが、それまでは基礎的な勉強をすることがほとんどです。
具体的には、以下のような科目を勉強します。
・4大力学(熱力学、流体力学、材料工学、機械力学)
・応用数学
・制御工学
・電磁気学
・電気・電子回路
・量子力学
・設計工学
・機械材料力学
・コンピュータ演習
機械工学科と言えば4力と言われるくらい、4大力学はこの学科で絶対に学ぶ内容です。流体力学でつまずく人が割と多いイメージです。
次に応用数学ですが、これは数式を処理する道具として、機械工学科で過ごしていく上で避けては通れない科目です。特に微分方程式は4力では当たり前のように使いますし、量子力学や他の科目でも頻出の分野です。
応用数学が出来ないと、必然的に他の科目の理解も難しくなってしまうのです。
次に制御工学、電気・電子回路、量子力学などについてです。制御工学はラプラス変換、電気・電子工学はダイオードやトランジスタを用いた回路、量子力学はシュレディンガー方程式などを勉強します。
このように、機械工学科では幅広い分野の学問を学びます。機械に関係ないじゃんと思われるような分野も学びます。
ただこれは後ほど詳しく書くのですが、研究室配属の後の勉強をする際に役立つことになります。
また、設計もやりますし、プログラミングもやります。
私はバルブの設計やエンジンの設計をやりました。材料を決めて、強度を計算して、寸法を決めて、実際に製図して…という感じでかなり作業量が多く、寝れない日もちょっとありました。
プログラミングは、情報学科ほどがっつりはやりませんが、基本的なコードの組み方やWebマクロを作成したりします。
300行くらいのコードを書いたりしていました。
このように機械工学科は研究室配属前に、幅広い内容を学びます。このことから、機械工学科は便利屋さんと言われたりもします。
研究室配属の後
研究室配属前は幅広い内容を学びましたが、研究室配属後は専門的な内容を深めていくことになります。研究室配属によって専攻が決まるので、当たり前ですね。
機械工学科にはいくつか専攻がありますが、北大の場合は「機械宇宙工学専攻」「人間機械システムデザイン専攻」「エネルギー環境システム専攻」「量子理工学専攻」の4つがあります。
例えば、機械宇宙工学専攻の場合は航空宇宙工学、量子理工学専攻の場合は原子炉物理などを学んだりします。このような専門科目を勉強する際に、研究室配属の前で学んだ基礎的な内容がいろいろと活きてくるのです。
大学院まで進学すると、本格的に研究が始まり、より深い内容を学ぶことになりますし、より専門性が高くなります。
正直私の意見ですが、機械工学科の場合、学部までで卒業するとそこまで専門性は身につかず、広く薄く学んで終わりになってしまうのかなと思います。
ですので、仕事で使えるレベルまで専門性を磨きたければ、基本的には大学院に進学する必要があります。
今回はここまでです!
それでは読んでいただきありがとうございました🙏
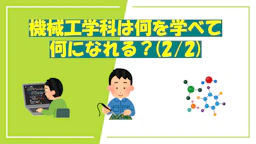



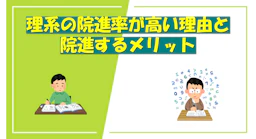

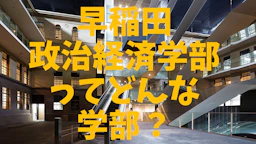

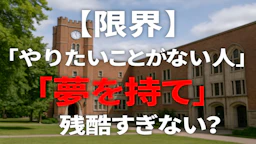
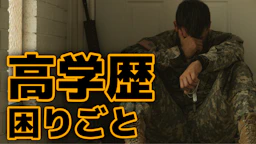
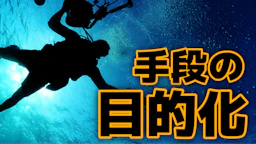

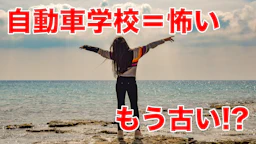
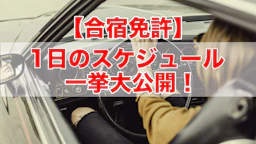


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)