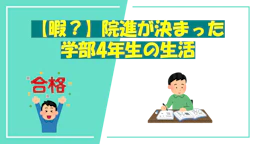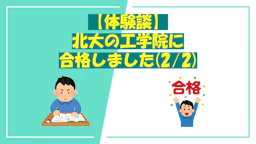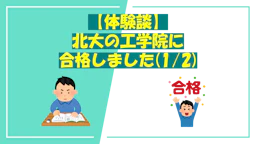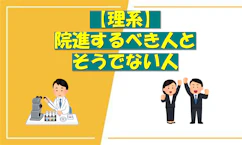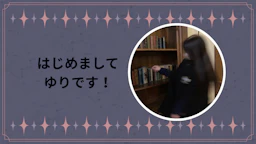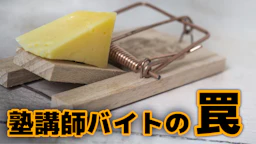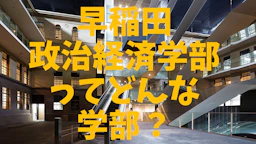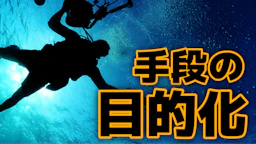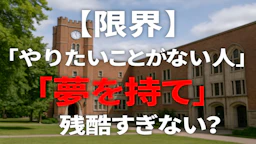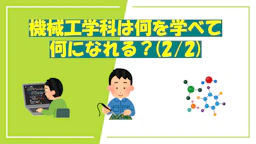こんにちは北の大学生です!
大学に入ると、基本的には4年間の学部時代を過ごしますが、その後、大学に残って研究を続けたい人は大学院に進学することになります(修士を取るのであれば、基本的にはプラスで2年通います。博士まで取る人は、さらに長くかかります)。
大学院では、自分の所属する学部の延長上にあるところにそのまま進学する人が多いですが、別の大学や別の分野の大学院を受けて入学することもできます。
大学院に進むと、最終学歴はその大学院になるので、大学入試で行きたいところに行けなかった人が大学院でリベンジする、というケースもときどきあります。
学部にもよりますが、特に理系職で就職する人は基本的に大学院に行くと思いますので、大学生活の参考までに、大学院に入る際に必要になる大学院入試(通称「院試」)について書いてみようと思います!
大学入試と大学院入試の違い
やりたい研究ができるかが最重要
大学院には研究をしに行くので、大学入試との一番大きな違いとしては、自分がやりたい研究ができるかという点を最も重視して、受験先を選ぶ点が挙げられるでしょう。
大学入試の場合、いろんな理由で大学を選ぶ人がいると思います。やりたいことがまだ決まっていなくて、とりあえず興味のありそうなところに入って、大学に行ってから考える、という人も多いでしょう。
それに対して大学院入試は、研究室で大学院を選ぶことが多いです。
例えば、「この分野の研究室は北大しかない」だとか「この内容の研究に対しては、東北大が一番強い」といった点で選んでいきます。単純に大学の偏差値で選ぶわけではなく、研究の内容や強さで選ぶということです。
大学入試ほど難易度の差はない
2つ目は、大学入試ほど、大学によって試験の難易度に差がないということです。
それに加えて、大学受験ほど難しくありません。
大学院の主な役割は研究なので、研究するのに必要な専門科目について理解できているかが試験で問われることになります。大学受験ほど幅広い科目を対策する必要がないですし、学部時代に関連科目を真面目に勉強して、きちんと対策すれば受かります。自分の在籍している北大であれば、学部時代の授業や教科書の内容が理解できていれば基本的には大丈夫です。
私の先輩も、2か月くらいの対策で院試に受かったと言っている人が多かったです。(もちろん、学部時代に真面目に勉強していないとかなり大変です)
また、基本的に英語の試験もあります。
しかし大学受験とは異なり、大学院独自の試験ではなく、外部の試験で英語の点数が決まることが多いです。
例えば北大の工学院では、英語の点数は提出したTOEICの点数で評価されます(どの試験で評価されるかは、大学院によってさまざまです)。機械系の研究室ではTOEICが550点以上ないと不合格になってしまいますが、これは北大生ならばノー勉で取れてしまうくらい、かなり緩い設定になっています。
ですが、550点よりもさらに高いスコアを提出すると、その分英語の点数が加点されるようになっています。TOEIC550点で院試に挑むのと850点で院試に挑むのとじゃ、スタートラインが違うわけです。
従って、大学院入試において少しでも有利になりたければ、TOEICは高得点を取っておくに越したことはないことになります。TOEICは1発勝負ではなく何回も受けられるので、ハイスコアが出るまで受け続けたりします。
さらに、大学院によっては面接も実施されます。研究したい内容や、志望動機などが聞かれます。試験とこれらの内容によって合否が決まります。
内部生が有利になりがち
3つ目に、内部生が有利になりがちという点です。(内部生というのは、北大生が、北大の同じ専攻の大学院を受けるようなケースです)
内部生が有利な理由は、以下の通りです。
・過去問を入手できるから
・院試を乗り越えた先輩にアドバイスをもらえるから
内部生の場合は、自分の所属している研究室に大量の過去問がある場合が多いです。それを研究室の同期と共に解いて対策していくという感じです。
それに比べて、外部生は過去問も入手しにくく、試験の傾向もつかみにくいです。なのでどうしても、勉強の効率は内部生よりも落ちてしまいます。
外部から大学院を受験する場合は、友達のコネを使って過去問を入手したり、志望している研究室の教授にメールでコンタクトを取ったりすると良いと思います。希望する研究室の教授に話しに行くのは、面接でのアピールにもなりますし、とても大事です。
今回はここまでです!
それでは読んでいただきありがとうございました🙏