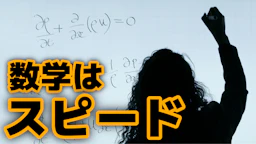「問題が解ける」に価値はない
どうも、フジです。
今回は、多くの高校生が勘違いしがちな「問題が解ける=定着している」という思い込みについて。
勉強をしていると、つい“正解”という結果に安心したくなるものですが、その瞬間にこそ一番大きな落とし穴が潜んでいます。問題が解けたという事実は、あなたの定着度を示すようでいて実はそんなこともないのです。
「解けたこと」と「定着していること」は全くの別物
多くの高校生は、問題を解けたかどうかで自分の定着度を測ろうとします。けれども、ここに大きな誤解があります。
問題が解けたということは、あくまで「その一問に正解した」という結果でしかありません。その裏には、運、勘、前に見たことがある問題との類似、単なる偶然の思い出しなど、様々な要因が絡んでいるため、「問題が解けた→必要な知識が十分に身についている」とは限らないのです。
「必要な知識が十分に身についている→問題が解ける」は成り立ちますよ。知識が定着していれば、当然その知識を使う問題は解けますから。しかし逆は成り立たない。だからこそ、「問題が解けたから定着している」と判断してはいけないのです。
VintageやNextStageのような網羅系の英文法問題集を思い浮かべてみてください。左ページの四択問題を正解できたからといって、右ページの解説部分をすべて理解し、例文を正確に使いこなせるとは限りませんよね? その1問の正解は、右側に記されている知識の一部分にしか触れていないのです。だから、その問題が解けたという事実だけでは「必要な知識がきちんと身についている」とは決して言えない。
繰り返しになりますが「問題が解けた」というのは結果にすぎず、定着の証拠ではないのです。問題を解いたその結果に一喜一憂するのではなく、正解の根拠となる知識を説明できるかどうかを常に確認することが、真の定着につながります。
定着度の基準はあくまで「知識の有無」である
前節では、問題演習をする際に常に念頭に置いておくべきポイントについて話しました。本節では、視野を広げて「勉強をする際に意識すべきポイント」に触れていきます。
まずは、学力の本質がどこにあるのかを整理しましょう。
学力とは「問題でわざわざ問われなくても再現できる力」のことだと私は考えています。つまり、知識が頭の中に正しく存在し、必要なときに取り出せる状態にあるかどうかがキモなわけですね。「必要な知識が十分に身についている→問題が解ける」は成り立つというのを踏まえると、納得感があるかなと思います。
それを踏まえると、勉強をする際に大切にすべきなのは、以下の3点でしょう。
- 「問題を解くのに必要な知識は何なのか」を的確に捉えること
- 「問題を解くのに必要な知識をきちんと覚えられている」状態を目指すこと
- 「問題を解くのに必要な知識がきちんと覚えられているかどうか」で自身の勉強の進捗を測ること
この3つです。
問題を解くこと自体はもちろん大切です。しかし、問題を解くことを「定着しているかどうかの確認作業」として捉えるならば、正解していても定着しているとは限らないという性質がある以上、そこに意味を見出すのは難しいものがあるでしょう。問題を解く行為が目的化して正答率を追い求めているなんてのはもはや論外ですが、そうでなくても、問題演習に時間を割くことで、「必要な知識の暗記」という最も重要な部分が置き去りになっていては本末転倒なのです。
具体例…
前節の話はやや抽象度が高いような気がしたので、具体例を添えておきます。
以前、「英語の長文が全然読めません!」と泣きそうになっていた生徒がいたんですね。話を聞けば「英単語を暗記しようと思って頑張ったことなど未だかつてない」と言うので、私はターゲット1900を渡して「とにかく単語を死ぬ気で覚えろ」と伝えました。
すると彼は、それ以降の3ヶ月間地道にコツコツ単語を覚え続け、ターゲット1900の700番までをなんとか覚えた状態(覚えたと言っても派生語や使い方などは曖昧な箇所も多い)にまで辿り着きました。
そんな状態で受験した次の模試、彼はどうやら英語長文が以前と比べると飛躍的に読めるようになっていたみたいで、その結果に自信を持った彼はこう言いました。
「もう英単語はある程度身についたので、これからは長文読解演習に比重を移したいです。」
一見、順調な成長のように見えますよね。でも、ここに大きな問題があります。彼は、自分の英単語の定着度を“長文が読めたかどうか”で判断してしまっているのです。
確かに、単語力が上がったことで長文が読みやすくなったのは事実でしょう。でも同時に、文章がたまたま簡単だった、知っているテーマだった、曖昧な単語が出てこなかった、そんな偶然の要素も混ざっています。つまり、「長文が読めた」という事実が「単語を覚えた」という証拠にはならないのです。
本当に単語が定着しているかどうかは、「単語を見て即座に意味が出てくるか」「文中で出てきても迷わず理解できるか」といった純粋な記憶の確認によってしか判断できません。これこそが、知識の定着度を測る唯一の正しい方法です。だから私は彼に「ちょっと文章が読めるようになったからって英単語力が満足についたと錯覚してはいけないよ。英単語の勉強は引き続き頑張って、覚えられているかどうかだけを評価の基準として、その完成度を高めていこう。」と伝えました。
これは、問題が解けたかどうかではなく、英文が読めたかどうかという話になってはいますが、定着度の評価基準を「きちんと知識を積み上げられているかどうか」以外のところに委ねてしまっているいい例です。
まあ、これ、昔の自分の話なんですけど。
結局のところ、勉強とは「結果を出すこと」ではなく、「結果を生み出すための根拠を積み上げること」です。問題が解けたという結果は一瞬のものであり、運や偶然の影響も受けます。でも、知識を積み上げることは決して裏切りません。必要な知識を確実に自分の中に刻み込んでいくこと。それが、学力を本当に伸ばすということです。
というわけで今回は以上。