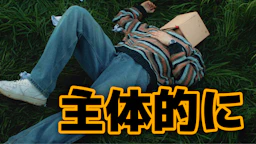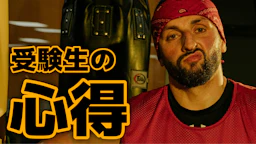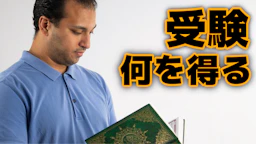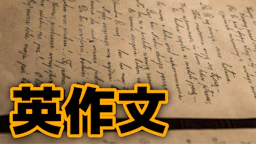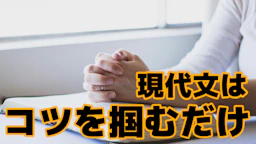自分の判断を信じ貫け
どうも、フジです。
「東大志望なのですが直前期に何をすればいいか迷ってしまっています。自分は過去問はほんの数年分だけ解いて、あとは切羽詰まっている基礎に時間を注ごうと思っていますが、とにかく過去問を解けと言う人もいて不安です。」
このようなメッセージをいただきました。
なるほど。
受験勉強に関する情報を発信している人で溢れかえっているこの世の中、ナイスな情報が得やすくなった一方で、逆に何が正解なのかがわからなくなっちゃうっていうね。難しいところです。でもね、試験本番までもう2週間をきっていますしね、ラストスパートは「自分を信じて突っ走る」のがいいんじゃないですか?
自分の判断を信じ貫け
受験勉強関連の情報を発信している身として言わせてもらうと、「こういう勉強をするべき」という内容を口にする時って、私も含め、その根拠に「自分はこのやり方で合格したから」を据えてしまいがちなんですよね(逆にそれ以外の根拠を示すことってできるのかな…?)。過去問演習をやりまくって合格した人は「過去問演習を死ぬほどやれ」と言うだろうし、過去問演習をあまりせずに合格した人は「過去問演習は不要だ」と言う、そういうもんなんですよ。
もちろん、勉強方針や勉強法について「自分より優れた人物の意見を取り入れてみる」というのは非常に大事なことです。その意見の根拠が”その人の成功体験”のみなのだとしても、やり方が上手だったから成功したんだろうなと推察できますからね。だから、東大を目指し始めて間もないなら東大合格者の意見を参考にすべき、中堅大学を目指すなら最難関大学合格者の意見を参考にすべきだと思います。数学が苦手なら数学が得意な人の勉強法を参考にすべきですし、世界史が苦手なら世界史が得意な人の勉強法を参考にすべきだと思います(参考にすべきってだけで絶対真似しろとは言っていない)。明らかに自分より優れた人物が目の前にいるのなら、一度「やり方を変えればもっとうまくいくのでは?」「自分のやり方に非があるからうまくいかないのでは?」と考えてみる、もはやそうしない理由がありません。
しかしどうでしょう。最難関大学を目指してその合否の境目でせめぎ合っている受験生、そして私。ぶっちゃけ、そこに”差”なんてほとんどないと思いませんか? 「まだ合格していないかもう合格しているか」という違いがあるくらい。偶然私の方が歳が上だったから先に合格しちゃっていて、そのせいで自分よりすごそうに見えるってだけ。差なんてないですよ。加えて、私も自分の意見の根拠は自身の成功体験のみで、高校生には知り得ない特別な科学的根拠をもって喋っているわけではないですし、私が自分の意見の根拠としている東大合格という成功体験も、もしかすると運が良かっただけなのかもしれません(こんなことはあまり言いたくありませんが…)。
だから、最難関大学を目指してここまで頑張ってきたあなたは、自分の考え・判断を信じ貫くのでいいと思うんです。「まだ合格していない」せいでその考えが正しいことの根拠を示せないというだけで、もっともな判断を下すだけの力はもう身についているはずです。とっとと合格して、自分のやり方が正解のうちのひとつであることを証明してやりましょう。どこの誰だかもわかんないようなインターネット上の人間の意見に心惑わされている場合ではありません。自分の考えを信じて、今自分が必要だと思っていることに全身全霊で取り組む、これがいいと思いますよ。
「自分は過去問はほんの数年分だけ解いて、あとは切羽詰まっている基礎に時間を注ごうと思っています」と、しっかり自分の考えがあるようなので、それならばそれを貫くべし!自分の得点を最大化するためのベストな選択がそれだと、あなた自身がそう判断したのなら、それが正解です!
演習?基礎?
前節の内容があまりに精神論すぎて、加えて演習メインと基礎メインのどちらがいいのかの判断材料すらも書いてないということで、これでおしまいにしちゃうとさすがにやや雑すぎるような気が。私の経験をもとに、どういう時にどちらが適しているのかを考えてみました。
まず、私が高校3年生の時の話。受験生の頃、この時期の勉強スタイルは「7割基礎」って感じでした。直近で「過去問演習のやりすぎはNG」「共テ後の過去問演習のやり方」というような記事をあげているので、そちらを見てもらうと詳細がわかると思います。
しかし、高校受験の時は違ったスタイルだったんですよね。中高一貫校のエスカレーター進学を蹴っての高校受験で、勉強開始が中3の11月、そこからたった3ヶ月でビックリするくらい成績を伸ばした経験がありますが、その時は「9割過去問演習」でした。毎日毎日全国高校入試問題正解の問題をアホほど解いて、間違えた問題をできるようにし、知らなかった知識をインプットするというやり方で、約2年半の間適当にしか勉強してこなかったにも関わらず、たった3ヶ月で「開成高校にギリ不合格」のレベルに到達することができたんですよね。
大学受験と高校受験を比較しながら振り返ってみると、中長期的に少しずつ演習を重ねてきている場合は「基礎メインの直前期」(基礎知識の実践的な運用方法はある程度わかっているので、基礎力を増強すればするほど得点力が増す)、相当切羽詰まっていて基礎と応用を同時並行でレベル上げする必要がある場合は「過去問演習メインの直前期」もありっちゃあり(基礎知識の運用スキルを叩き上げるために過去問演習に多くの時間を割くことが必須だが、そうすると基礎をじっくりやる時間がなくなるので、仕方なく過去問演習の中で基礎知識の粗探しをする、基礎力が乏しいからこそこのスタイルでも少しずつ基礎力が高まる)って感じなのかなと思いました。
おわりに
過去問を解いてみて、そして「この問題が解けるようになるには何が必要なのか?」を自分で考えてみて導き出した結論、これを最後まで信じ抜いて、一心不乱に頑張ること!確か最近「迷うヤツは弱い」ってガープ中将も言ってましたよ!
というわけで、お返事はここまでです!
メッセージありがとうございました!
合格できるよう祈ってます!!!!!!!!