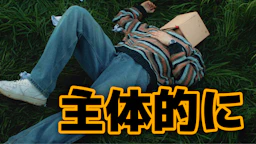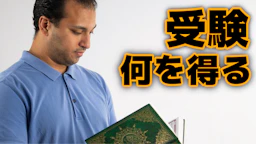受験生はこれを心に留めておけ
どうもフジです。
今回は「受験生の心得」というテーマ。
受験勉強というのは、精神面も行動面も、徹底して「合格するために必要なことをやり切る」という覚悟が問われる戦いです。ただ、勉強を続ける中で「もう十分やったんじゃないか」と思いたくなる瞬間は必ず来ますし、周囲の人との人間関係や、日常生活の誘惑に気を取られることも避けられません。だからこそ、今回紹介する私が受験生当時大切にしていた「4つの心得」、改めてそれを意識しておくことは、単なる精神論ではなく、行動の具体的な指針として大きな意味を持つと感じています。
受験に臨む皆さんの、モチベーションや行動のヒントになれば幸いです。
やるしかない
受験勉強にゴールはない
まず、受験勉強において最初に心に刻んでおいてほしいのは「やるしかない」という現実です。
受験というものには「これだけやれば確実に合格できる」という保証はどこにも存在しません。つまり受験勉強には終わりがないってこと。少し厳しい響きかもしれませんが、私はこれを高校3年生の時に痛感していました。
確かに、計画を立てて勉強すること、「今日はここまでやる」「明日はこの範囲を終える」といった目標設定を行うことは、モチベーション維持に大いに役立ちますし有意義なことであると思います。しかし、計画を終えたからといって「今日はもう勉強を切り上げていい」と言っていいほど、受験生に時間の余裕はありません。予定通りに進んだからこそ、余った時間をさらに勉強に使うという発想、これを見て見ぬフリをしてはいけないと思います。受験とは「合格するための可能性を少しでも上げる作業」であり、そのためには1分1秒を無駄にするわけにはいきません。
勉強にメリハリをつけることをヨシとする風潮もありますが、「今日はやるべきことを終えたからもう休もう」と安易に手を止めてしまうのは、受験勉強においては非常に危険です。勉強を計画的に進めることは重要であっても、それを口実に自分に甘くなってしまうと、結局「まだやれるはずだった時間」を自分で切り捨てることになりかねませんからね。
泥臭く、貪欲に、勉強できる時間はすべて勉強に注ぎ込む。その覚悟を持たずに「これくらいやれば受かるだろう」という慢心を抱いた瞬間から、受験生としての戦いは実質的に後退を始めます。「やるしかない」という気持ちを徹底することが、合格を引き寄せるための第一歩だと私は思います。
利己的たれ
この1年だけは自分を最優先する
次に大切なのは「利己的たれ」という考え方です。受験勉強において何よりも重要な「質」と「量」の両立、この2つを極限まで高めるためには、周囲の目や社会的な常識に囚われず、自分にとって最適な行動を選び取るという“利己的”な姿勢が必要不可欠です。
たとえ周りから「変わっている」と思われても、他人にちょっとばかし迷惑をかけようとも、自分の勉強効率を第一に考えるべきです。受験生の1年間だけは、自分の未来を勝ち取るために「自分が最優先」だと割り切るくらいでちょうど良いと私は考えます。
実際私は、自分が最も集中できる環境を追求した結果として、駅チカのスタバに日々入り浸っていましたよ。周囲からの視線や店側の迷惑という問題は重々承知していましたが(一応田舎の店舗だったし店員さんとも仲良かったけど…)、それでも「ここで勉強するのが一番集中できる」という一点で選択していました。勉強する場をどこにするかも、受験生にとっては立派な戦略のひとつです。
また、学校の授業に全く耳を傾けず、常に内職もしていましたけど、そうしていたのも「自分の合格のため」という信念があったからです。授業中でも自分に必要な勉強を進める方が、合格への可能性を高められると考えていました。自分も塾講師をしてるので今は痛いほどわかりますが、授業を聞かずに内職をしてる生徒なんて、先生からしたら不快そのものだったと思います。定期テストすらまともにやってこないし(笑) でも、受験生にとっての1年は、将来の人生を左右する大切な時期です。周りに遠慮して自分のペースを崩すことは、大きな損失だと断言できます。
利己的になることに対して、罪悪感を抱く必要はないと思いますよ。周りへの配慮をゼロにしろとは言いませんが、受験に勝つためには、「自分が合格するために必要かどうか」という一点で、行動を判断することが求められます。受験生の1年間だけは、他人ではなく自分のために生きること。申し訳ないなと思ったら、受験が終わった後に「おかげさまで合格できました」の手土産を持っていって「ごめんなさい」しましょう。
執着を捨てろ
勉強以外の思考を排除する
続いては「執着を捨てろ」という話です。人は無意識のうちに、さまざまなことに頭のリソースを使っています。勉強以外のことに頭のリソースを奪われることは、受験生にとって大きな損失です。
それをしている時間以外でもそのことを考えてしまう…という状態は特に問題視すべきです。例えば、ゲームが好きで仕方ない人は、勉強していても「家に帰ったらゲームで何をしよう」と考えてしまうでしょう。服や容姿に強い関心がある人は「今日の服は似合っているか」「もっと良い服が欲しい」といった思いが頭を離れません。こうした執着があると、気づかないうちに集中力が削がれ、勉強の効率が大きく低下してしまいます。
受験生の一年間は、これを断ち切る覚悟が必要です。好きなことを完全に捨てろというわけではありません。ただ、勉強以外のことが頭を占領する状況を、自分で許さないようにするべきです。勉強中は完全に勉強に意識を集中し、それ以外のことは一切考えない。どうしても勉強中にチラつくような物事があるのなら、それをいっそのこと日常生活から完全に排除するくらいの勢いが必要だと思います。
私も受験生になりたてホヤホヤの頃は、容姿へのこだわりから抜け出せずにいましたね。当初は、髪型をどうするか、どんな服が似合うかを考えている時間がそれなりにありましたが、徐々にそうした執着を振り払い、最終的には、もはや「身なりに気を遣わず勉強に一心不乱であること」にカッコよさを感じる領域にまで到達していました。そうでもしない限り、頭の片隅に常に他のことが居座り、勉強に全力を注ぎきれないと感じていましたね。
受験は頭脳労働。頭の中をすべて勉強に使える状態にするためには、執着を断つ勇気が必要です。
最後は運
運を引き寄せる努力を尽くす
そして最後に伝えたいのは「最後は運」という現実です。受験は努力がものを言う世界ですが、それでも運という要素を無視することはできません。どれだけA判定を取っていても、不合格になる人は存在します。体調不良、試験当日の精神状態、出題傾向の偶然など、どうしようもない不確定要素が受験には必ずや付き纏います。
しかしだからといって「受験なんて運ゲーだから」と開き直り、努力を怠るのは絶対に違います。大切なのは「運を味方につけられるだけの努力をしているかどうか」です。運というのは、準備を徹底した人間にしか微笑まないと私は思います(別にスピリチュアルな話ではないです…)。
私自身、東大を志望して勉強していたものの、東大模試で一度もA判定を取れたことはありませんでした。それでも「自分は不合格になるかもしれない」という不安を感じたことはありませんでした。なぜなら、可能な限りの努力をしているという自信があったからです。努力しきった人間にしか持てない「不安に飲まれない強さ」は、まさに運を呼び込む最大の武器だといまだに感じます。
「まだできることはないか」と問い続け、日々の行動を積み重ねること。問題集の精度を高める、復習漏れを潰す、睡眠や体調管理にも妥協しないなど、こうしたひとつひとつの行動が、運を味方につける下地になります。受験の本番で「自分はやれることをやり切った」と胸を張れる状態をつくることが、最終的に運を呼び込むのです。
受験には絶対はありません。しかし「絶対はない」と知りつつも、それを言い訳にせず、むしろだからこそ最後まで努力を尽くすこと。なんだか最初の節で話した内容と被り気味だなあと書きながら感じましたが、それはさておき、運を引き寄せる準備こそが受験勉強の本質だと思います。
というわけで今回は以上。
受験は決して甘いものではありませんが、今回紹介した4つの心得を意識することで、自分自身の受験勉強をより力強く進めることができるはずです。皆さんが志望校に一歩でも近づけるよう、心から願っています。