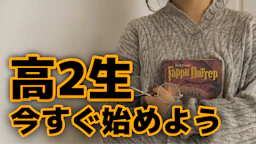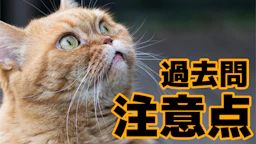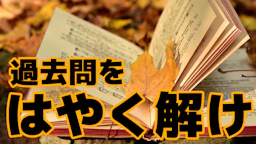ゴールを知っておけ
どうもフジです。今回は「赤本(過去問)はいつから解き始めるべきか?」という疑問にお答えしていきます。
赤本という名前を聞いたことがない高校生は、おそらくいないでしょう。志望校の過去問が何年分も掲載されていて、受験生の多くが手に取る参考書のひとつです。ですが、「いつからやるのが正解なのか」「まだ自分には早いんじゃないか」とタイミングに迷ってしまう人も少なくありません。
そこで今回、私の考えを明確に伝えたいと思います。
結論から言うと
過去問にはできるだけ早く、最低でも一度は取り組んでおくべきです。
まずは「ゴールを知る」ことから始めよう
そろそろ本格的に受験勉強を始めなければ…と考えるようになると、多くの人が「いつ赤本をやるべきなのか」と悩み始めます。志望校がぼんやりとでも見えてきた段階で、この悩みが生まれるのは自然なことです。
ただし、ここで注意してほしいのは、「志望校が定まった時点で、まずは1回過去問にチャレンジするべき」ということです。
理由は単純、到達すべきゴールが見えていないと、効率よく進んでいくことができないからです。「なにがどのレベルまで求められているのか」を知らずに進んでいってしまうと、何にどれだけ時間を割けばいいかなんてわかるはずもありません。
また、過去問を開かないまま勉強を進めていってしまうと、大学が求めている学力と自分の実力のギャップに気づくのが受験直前になってしまう危険性もあります。直前期にそれに気がついたときにもし、「もう間に合わないかも」と感じるようなズレがあったとしたら、それはあまりに苦しい状況です。だからこそ、早いうちに過去問を一度解いて、「今の自分はどの位置にいて、ゴールはどこにあるのか」を明確にすることが重要なのです。
過去問から「求められる力の正体」を見抜こう
過去問を解く意義は「点数を取ること」ではなく、「大学がどんな力を求めているかを知ること」にあります。
たとえば英語なら、その大学は文法問題をどれくらい重視しているのか、語彙の難易度はどの程度なのか、長文の分量や設問の形式はどのようなものかといった点が見えてきます。空欄補充が多いのか、語句整序が出るのか、英文の読み取りの中でも細かい推論が問われるのか、そうした出題傾向を知るだけで、普段の勉強の方向性は大きく変わってきます。
数学であれば、解法の暗記で対応できる問題が中心なのか、それとも初見の問題をじっくり考える力が問われているのかといった、勉強スタイルそのものに関わる情報を読み取ることができます。共通テストのようにテンポよく処理する計算力が求められるのか、それとも論理的に構築された記述解答が重要なのかで、準備の内容はまったく違ってきますよね。
早い段階でこうした情報を得ることができれば、自分の得意不得意を客観的に把握し、時間をかけるべきポイントを明確にできます。つまり、やみくもな努力を避けて、戦略的に準備を進められるということです。
自分の立ち位置を「模試」で確かめてみる
加えて難関大志望の方は、もし可能であれば志望校の冠模試(大手予備校が実施している難関大の大学別模試のこと)を受けてみるのも非常に有意義ですよ。
私が初めて受験した冠模試は高2の秋のものだったかな。結果はズタボロ中のズタボロ…しかしこの模試によって得られた気づきはとても大きく、「赤本を自室で時間を測って解く」という経験とはまったく異なる価値を感じましたね。試験会場の緊張感、制限時間のプレッシャー、そして周囲にいるレベルの高い受験生たちの存在。そうした要素が、「今の自分の立ち位置」をよりリアルに示してくれました。
弟にも同じように高校2年生の秋の冠模試を勧めたところ、彼も「この模試があったからこそ、やるべきことが明確になった」と話していました。学校で機会がない場合でも、自分で申し込んで受験することはできます。ぜひ前向きに検討してみてください。
ここまでお伝えしてきたように、過去問に早めに取り組むことで得られる最大のメリットは、「現状とゴールの差を知ること」にあります。
過去問は決して“最後の仕上げに取り組む教材”ではありません。むしろ、一度目の過去問は“地図を開く作業”に近いのです。山のてっぺんがどこにあるのかを知らずに登り始める登山者はいません。合格という山の頂を目指すなら、まずはその高さを正しく知ること。自分が今どこにいるのかを把握し、その上でどう進んでいくかを決める。それこそが、効率的な受験勉強の第一歩になるのです。
怖がらずに赤本を開きましょう。そして「今は全然できなくて当たり前」という気持ちで取り組んでください。そこで得たものは、今後の努力の“方向性”を決めてくれるはずです。
というわけで今回は以上。