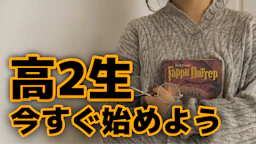受験は戦略的に
どうもフジです。
今回は「受験は戦略的に」というテーマで、すでに志望校が決まっている高校3年生に向けてお話していきます。
大学受験本番まで、残り1年を切りました。この時期、志望校に向かって全力で努力を重ねている人も多いと思います。「よし、もう志望校は決めた。あとはただひたすら勉強あるのみ!」と気合い十分な方もいるかもしれませんね。
でも、ちょっと待ってください。
受験は“気合い”だけで突破できるものではありません。むしろ、正しい戦略を持たずにがむしゃらに勉強してしまうと、思ったよりも成果が出ずに空回りしたり、最短距離で合格にたどり着けなかったり…そんな事態に陥ってしまう可能性があります。
そこで今回お伝えしたいのが、「各教科における目標点数を設定する」という受験戦略です。
志望校の過去問や配点をもとに、「この教科では〇点、この教科では△点を取ろう」とあらかじめ目標を決めることによって、日々の勉強の優先順位が明確になりますし、自分にとっての「合格までの道のり」がぐっと現実的なものになります。
では具体的に、目標点数を設定することにはどんなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
勉強の方向性がクリアになる
目標点数を設定することで、受験勉強の羅針盤が手に入ります。
何となく「全部の教科をバランスよく頑張ろう」と思っていても、配点や合格ラインを考えたときに、実は“頑張るべきポイント”には明確な差があることがほとんどです。たとえば、英語200点・数学100点の大学なら、当然英語を優先すべきですし、苦手な教科を伸ばすのが正解とは限りません。
「合格には合計で〇点必要。現状は△点だから、あと何点上げたい。そのうち×点は英語、+点は数学で狙う」
こういった考え方ができるようになると、やるべき勉強が自然と見えてきます。あれこれ手を出して中途半端になることもなく、効率的に成果が出せる状態になるのです。
現状分析と課題発見ができる
目標を持つことで、自分の今の実力をより正確に捉えることができます。
「目標点との差分」を意識する習慣がつくと、課題の発見スピードが飛躍的に上がります。「この単元は得点源にするつもりだったのに取れていない」「ここで時間を使いすぎて失点している」など、問題点がどんどん明確になってくるのです。
これによって、日々の勉強が「とりあえず参考書を進める」といった作業的なものではなく、「目標との差を埋めるためのピンポイントなアプローチ」に変わります。限られた時間の中で最大の成果を出すために、こうした“戦略的思考”は必須です。
モチベーションの源になる
目標点は、勉強を続けるうえでの「灯台」のような役割を果たします。
受験勉強は長期戦です。1日や2日では成果が見えづらく、ふとした瞬間に「自分は本当に合格できるのかな」と不安になってしまうこともありますよね。そんなとき、目標点があると、「自分は今、この位置にいて、ここまで伸ばせばいい」と冷静に状況を把握することができます。
たとえば、「合計で90点も伸ばさなきゃいけない」を「英語であと30点、数学であと30点、現代文であと30点」といったふうに、目標を細かく分解して見ることができれば、全体がぼんやりした「遠い理想」ではなく、「現実的な課題の集まり」に変わって見えるはずです。
「英語であと30点必要だ」と分かっていれば、「大問1であと5点、大問2であと5点、大問3であと10点、大問4であと10点」と細かく目標を設定できます。ここまで細分化すれば、「意外といけそうじゃん!」という実感が湧いてくる気がしませんか?
また、「目標に近づいている感覚」が得られることで、日々の勉強に手応えを感じられるようになります。「今日はこの問題集で3点ぶん強くなれたな」と思えるかどうかで、受験生活の充実度は大きく変わるのです。
というわけで今回は以上。
目標点を設定するという行為は、「今の自分の位置」「ゴールまでの距離」「そのためのルート」をはっきりさせる、いわば“受験戦略の地図”を描く作業です。気合いと根性に頼るのではなく、戦略的に合格を引き寄せていきましょう。