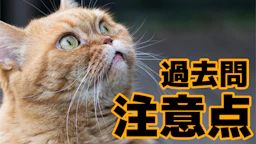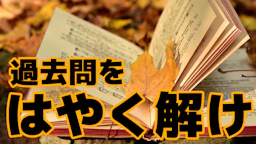過去問演習で大切なのは「解いた後」である
どうもフジです。
今回は「過去問演習」についてです。
共通テスト対策にせよ、二次試験対策にせよ、夏以降は過去問に取り組む時間が徐々に増えてきますよね。もちろん、「本番と同じ形式の問題に触れておく」という意味で、過去問をやること自体には大きな意義があります。
でも、ここでひとつ注意しておきたいのは、「ただ解いているだけ」で満足してしまっていないか…ということ。過去問をやる意味、果たして“解くこと”だけなのか。
私はそうは思いません。
むしろ本当に重要なのは、「解いた後」だと思っています。
「通しで解く」にこだわらなくていい
まず前提として、過去問を解くときの「時間の使い方」について少し触れておきます。
過去問って、1年分を通しで解こうとすると、1教科につき60〜90分ほどかかりますよね。もちろん、本番を見据えた実践練習として、時間を測って通しでやるのも大事です。でも、それを毎日毎回繰り返してしまうと、どうしても“その教科だけで1日の勉強時間の大半が終わる”みたいな事態になりがちです(後述しますが、過去問を解いた後にも時間がかかりますからね)。
だからこそ、私は「大問ごとに分けて解く」スタイルをおすすめしています。
たとえば、英語の長文問題だけを1題だけ解くとか、数学の大問3だけを集中してやる、みたいな感じですね。あらかじめ「この問題は本番では20分で解く」といった時間の目安を決めておけば、分割して演習してもなんの問題もないでしょう。
過去問演習を始めたばかりの頃は、「時間内に終わらなかったからそこで切り上げる」というやり方は避けましょうと、巷ではよく言われていると思いますが、これはその通りです。まだ実力がつききっていない段階では、制限時間内に解けないことの方が多いはず。でも、そこで中断してすぐに答えを見てしまうと、「思考を深める経験」がごっそり抜け落ちてしまうんですよね。だから初期段階では、時間をかけてでも「最後まで解き切る」ことを重視しなきゃいけないんですが、それも考慮するとやっぱり、1年分を通しで解くっていうのは、無理があるんですよね。
過去問の価値は「解いた後」にある
さて、ここからが本題です。
私はこれまでたくさんの受験生を見てきましたが、「過去問を解くこと」だけに意識が向いてしまっている人が本当に多い。解いて、丸つけして、解説を読んで「なるほど、こうやって解けばよかったのか」で終わってしまう。ここで満足してしまう。
でも、そこから先が、むしろ一番大事なんです。
過去問って、「同じ問題がそのまま出てくるわけじゃないんだから、慣れるために数をこなすのが大事なんでしょ?」という誤解をされがちなんですが、それはちょっと浅い理解です。
確かに、設問の形式や出題傾向に“慣れる”ことも重要です。でも、本当に価値があるのは、「この問題を通して何が学べたか」「自分の中にどんな新しい知識や視点が加わったか」という部分なんですよね。
たとえば、英語であれば、本文中に出てきた単語や熟語の表現。古文・漢文であれば、頻出の構文や助動詞の用法、現代語訳で見落としがちなニュアンス。世界史や地理であれば、用語だけでなく「なぜそうなったのか?」という因果関係や流れ。これらを「気づいた瞬間」で終わらせずに、手元のノートやルーズリーフに書き出す、再整理する、あるいは既存の参考書のどこに対応しているかを確認して印をつける、そういった“二次処理”が、本当の意味での実力に変わるのです。
自分の「間違い」を力に
過去問演習において、最大のチャンスは「間違えたとき」に訪れます。
自分がどこでつまずいたのかを丁寧に言語化し、それを起点に知識を補強する、これこそが、過去問をやる真の目的だと私は思っています。
たとえば、「これは知らなかったから間違えた」という単純なパターンもあれば、「知識はあったけど、設問の問い方を誤解していた」とか、「選択肢の比較が甘かった」といったパターンもありますよね。どのタイプの間違いであれ、「じゃあ、次に同じような場面に出会ったときに、どう対処すればよかったのか?」を具体的に考えることが、次の一歩につながるんです。
よく、「過去問演習は復習が9割」なんて言葉もありますが、まさにその通り。解いた時間よりも、復習にかける時間の方が長くていい。むしろ、そうあるべきです。
というわけで今回は以上。
これから過去問演習に本格的に取り組む人も多いと思いますが、ぜひ「解いたあと」にしっかり時間を割いてみてください。1問に対して10の学びを得られる人と、1問解いて満足してしまう人とでは、この先の伸びが全然違ってきますよ。