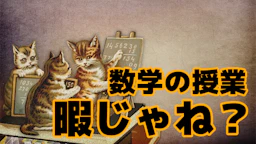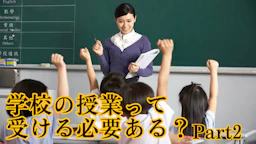こんにちは!くるみるくです。
今回は今まで前日勉強に徹していた私が1週間前から勉強を始めるようになった成果や思うこと等の体験談をご紹介したいと思います。
テスト前のスケジューリングがうまくできない!という方は参考にしてみても良いかもしれません(参考にならないかも。。。汗)
テスト勉強をいつから始めるかが問題
さて、これはいつの時代も(?)皆さんが気になる話題ですよね。
私は正直、高校1年生までは本当に前日か前々日まで勉強をほとんどしないタイプでした。
「前日にやった方が記憶が新しくて良いじゃん」と思う系ですね。
実際に前日勉強でもそれなりに点は取れるので(私の学校では基本進度ゆったりの授業でやった内容しか出ない)何も危機感を持っていませんでした。
あえていうなら大の苦手分野かつ私の学校では珍しく、授業がYouTubeの3倍速くらいのペースで進む恐ろしい歴史総合のプリントを少し前からみておいたくらいです。
危機感を覚えたのは高校2年生から。
まず数学が、復習なしでは点を取れないことに気づきました。
数学1Aまではなんとなく中学校のノリでついていけるのですが、数学2Bからは多くの公式が一瞬で目の前を駆け抜けていくので、しかもそのあとの授業でほとんど使わなかったりもするので、復習しないと簡単に忘れるんですね。
また、古文漢文も地味に復習が必要ということに気づいてしまったのです。
それまではまたまたノリでどうにかしていたのですが、文章も長く、多くなってきて、さらに助動詞や敬語など覚えなければいけない品詞が増えてくるとどうしても勉強しないとわからないままになってしまいます。
そんなこんなで、高校2年生の2学期からはようやく真面目に1週間前から勉強するようになりました。
ちなみになんで1週間前かというと、私の学校ではテストの時間割が1週間前にならないと発表されないためです。最終日の教科を1週間前から本腰入れてやるのも違うなあと思ってしまうので。
そんな私から先に結論を申し挙げますと、
教科を分けてスケジューリングをすべし!!
これ1択です。
科目の種類を分けよう
これは皆さんも無意識でやっている方が多いと思いますが、改めて論理的に考えることで今後の計画がしやすくなると思うのでご紹介します。あくまで私の例ですが。
私はテストがある科目を「長期暗記系」「短期暗記系」「理解系」「理解&演習系」の4つに分けています。
それぞれ簡単に説明すると、
【長期暗記系】
覚える量が多く、問題演習などはない。また今後の学習に繋がりやすい分野や受験で使う科目。1週間前から毎日見る。
【短期暗記系】
プリントを覚える必要はあるが量は多くない。また受験で使わない、今後の学習に繋がりにくい科目。前日勉強、または1週間前と当日だけに見る。
【理解系】
ノートや教科書に目を通し理解の過程を思い出す必要があるが覚えることはそんなにない。前日勉強。
【理解&演習系】
上に同じく理解の過程を思い出す必要がある+問題の形式を知る必要がある科目。1週間前とは言わずできるだけ早くから演習に取り組む。
こんな感じ。
そして、私にとっての科目の分類はこんな感じです↓
長期暗記系・・・公共、古典
短期暗記系・・・生物、(歴史、)家庭科、保健
理解系・・・国語、英語、(生物、)、歴史
理解&演習系・・・数学、物理
これは受験科目や得意不得意によってかなり違うと思います。例えば私は生物は絶対に受験で使わないと決めているので短期暗記系に入れていますが、受験で使う、特に大学でも使うような人は長期暗記系として捉えた方がいいかもしれません。
あくまで参考程度に。。。!
テスト1ヶ月前から勉強ってどうなの?
私がたまに目にするのは「テスト1ヶ月前から勉強しています!」という猛者。
確かに早いうちからテスト対策をするのはいいと思います。が、
私個人の意見としては、「理解&演習系以外はそんなに前からやらなくても大丈夫」です。
(もちろん本当に人によるのでこんな考えもあるのだな程度にしてください!「1週間前にやっと始めたら赤点だった泣」という声には責任持てません。汗)
1ヶ月前から始める、1週間前から始める、それぞれメリットとデメリットがあると思います。
まず、1ヶ月前から毎日復習することで記憶が定着しやすくなります。また、時間がたっぷりあるのでわからない問題にじっくり向き合うこともできるし、先生に質問する余裕も生まれます。
1ヶ月前から始めるデメリットとしては、授業が終わっていなくて範囲もわからない恐れがある、モチベーションがない、1ヶ月前に勉強しても1週間前、一日前に勉強しなければ忘れてしまう、といったところでしょうか。
逆に、1週間前から始めると、記憶が新しく、またそれなりに危機感もあったり周りも勉強し始めたりとモチベーションをテスト当日まで保ちやすいです。
デメリットとしては、時間が足りないことでしょうか。
ですが、個人的には定期テストの勉強には1週間も1ヶ月も時間的余裕にはあまり差異がないように感じられます。
だって定期テストの範囲なんて1年で学ぶ半分もない。共通テスト全体の何割の内容ですか?
正直、理解度や範囲の広さにもよりますが、定期テストくらいならどちらも集中して取り組めるなら1週間も1ヶ月もあまり大差はないと思います。
ただし、先ほども言ったように「理解&復習系」に限って言えば、それらはより多くの問題に触れ、問題の形式になれたり解法の型をある程度覚えることが大切になってきますから時間は多い方がいいでしょう。
まとめ
さて、今回は私の定期テスト前勉強スケジュールについて少しご紹介しました!
勉強で何よりも大事なのは自分自身で勉強法を見つけること。それは単に「勉強の仕方」だけではなく、時間の使い方も含まれます。ぜひ自分にあった勉強のスケジュールを見つけてみてくださいね。
それでは!