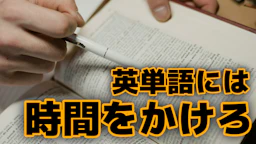おすすめ暗記法
どうも、フジです。
今回は「おすすめの暗記法」というテーマ。
この記事を読んでくださっている皆さんは、きっと勉強に対するモチベーションが高いはずです。ただ、やる気があっても、努力の方法を間違えてしまえば、時間ばかりかかって結果がついてこない…なんてことにもなりかねません。
だから私が実際に活用して効果を実感できた暗記法を3つ紹介します。これを参考にして、皆さんが自分に合うスタイルを見つける手助けになればと思います。
隙間時間活用法
まず最初に紹介するのは「隙間時間を活用する暗記法」です。
皆さんは学校生活の中で訪れるちょっとした休憩時間をどう過ごしていますか? 「10分だけだし友達と喋っている」という人や「眠いから10分仮眠をしている」という人も多いかもしれません。それはそれで良い過ごし方だなと思いますが、しかし、この10分を侮ってはいけません。
1日の中で隙間時間は何度も訪れます。学校の休み時間だけじゃなく、通学の待ち時間、帰宅して夕食までのちょっとした間…。この「何度も訪れる」というのがポイントなんですよね。
エビングハウスの忘却曲線を思い出せば、このことの重要性が理解できると思います。人間は一度覚えたことをそのまま放置すると、驚くほどの速さで忘れてしまう…というのが忘却曲線で示されていますが、だからこそ、暗記した直後の早いタイミングで復習を入れる、そしてその後短いスパンでそれを繰り返すことが大切になるわけですね。休憩時間の10分は、それを行うのにまさに最適な時間です。
前日に暗記したものでも、その日の朝に暗記したものでも良い、とにかくそれをその日の隙間時間で反復するんです。そうすれば、その内容はめちゃくちゃ頭に残ります。
私の場合は、前日暗記した英単語のうち、曖昧なものに付箋を貼っておき、休憩のたびにそれを見直すようにしていました。1日の間で何度も触れることで、夜には自然と定着している感覚がありました。暗記の勝負は「時間の長さ」だけでなく「繰り返す回数」も重要なんだと実感した瞬間でした。
音読暗記法
2つ目は「音読」を取り入れる暗記法です。
皆さんは普段、音読をしていますか? 英語のリスニングの練習のときくらいしか声を出さない、という人も多いのではないでしょうか。でも、これは非常にもったいない。実は、音読をすることで脳が刺激され、暗記効率は格段に高まるのです。
私は特に世界史の勉強で音読を多用していました。歴史の流れや出来事の関連性を覚えるには、ただ黙読するよりも声に出すほうが頭に入りやすくなります。声に出すことで「視覚」だけでなく「聴覚」も使うことになり、情報を多くの感覚からインプットできるため、記憶が強固になるんです。
さらに便利なのは、音読や暗唱は机に向かっているとき以外にもできるという点。私は自転車通学中やランニング中にも、直前に覚えた内容を声に出して暗唱していました。これだけで、移動や運動の時間をそのまま勉強に変えることができました。
もちろん、音読は世界史に限らず、英単語や古文単語の暗記にも応用できます。単語をただ眺めるのではなく、声に出しながら指でなぞったりノートに書いたりすることで、身体全体で記憶していく感覚を得られます。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、やってみると「思った以上に覚えやすい」と感じるはずですよ。
「思い出し」暗記法
3つ目は「思い出す」ことを意識する暗記法です。
多くの人は、暗記を「インプット=詰め込むこと」と捉えがちです。例えば、英単語と意味を同時に見ながらノートに書き写したり、何度も繰り返し眺めたりする方法です。しかし、実際のテストで求められるのは「知識を思い出して使うこと」です。つまり、アウトプットができて初めて“暗記が完成した”と言えるのです。
本番の試験でいきなりアウトプットを求められても、普段からその練習をしていなければできません。だからこそ、普段の勉強から意識的に「思い出す訓練」を繰り返す必要があります。
具体的には、1回目は英単語と意味を一緒に確認しても構いませんが、2回目からは必ず「英単語だけを見て意味を思い出す」という形に切り替えてみてください。これこそが最もシンプルかつ効果的な“思い出し暗記”です。
私は英単語だけでなく、古典の助動詞の活用や世界史の年号、化学の反応式などでも同じ方法を使っていました。アウトプットを重視して勉強しておくと、テスト本番でも自然と知識が引き出せるようになっていきます。
以上、今回は「おすすめの暗記法3選」として、隙間時間活用法、音読暗記法、思い出し暗記法を紹介しました。
暗記は「努力の量」だけではなく「努力の仕方」で差がつきます。勉強時間は限られていますからね。工夫で効率を最大化し、自分の力に変えていきましょう。