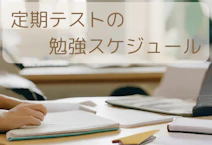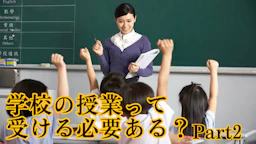暇な数学の授業の活用方法
どうも、フジです。
今回は高2高3の文系学徒へ向けた記事。
学校の数学の授業って暇ですよね。
いや、暇というよりは、真面目に聞く意味がないというか(もちろん人によりますが)。
文系数学は、どこも高2の夏頃に1A2Bの全てが終わり、演習に突入するハズなんですが、この演習がねぇ…。なかなか無駄が多いわけなんですよ…。遅かれ早かれ、多くの人が「なんかこれ、あんま聞かなくてもよくね?」っていう状態になってくるんじゃないかなと思います。
ということで今回は、数学の授業時間の活用法。
学校の数学の授業は大事?
きっと高2の夏以降の数学演習は、予習として問題を解いてきて授業前に指名された生徒が黒板に板書、授業中に先生が解説…といったスタイル。
まぁこれが、学校側にできる最大限の効率化ってとこなんでしょうね。なので学校の授業スタイルを非難する意図はないのですが、それにしても非効率が過ぎる!
使用するテキストは、「各単元から頻出の重要問題をピックアップしてきました!」みたいな薄っぺらい問題集。基本パターンをきちんと網羅しているわけでもなければ、問題のレベルも中の中くらいで、「誰が得すんねん」感満載です。
無論、最難関大受験生にとっては取り組む必要のないくらいのレベル帯であり、解く時間すら無駄(まあ、ちょいちょいできない問題はあるかもしれないので、それだけは見落とさないように…)。レベルは相応な学生に関しても、変にこんなテキストをいじり始めるくらいなら、高3冬までずっと、青チャートなど網羅性の高い参考書の完成度を高めるのだけに時間をかけた方がよっぽどマシだと思います。
んで、授業時間は50分間フルで解説ということになりますが、自力で解けちゃった問題の解説を一生懸命聞くのなんて、時間の無駄も甚だしいですからね。わからなかった問題の解説だけは聞くにしても、授業時間の半分くらいは無駄なものとなるはずです(全部の解説を聞かなきゃいけないような状態なら、やっぱり青チャートをやれ!笑)。
要は、数学の授業をフルでちゃんと聞かなきゃという層は相当限られてるでしょって話です。
さて、暇な時間、内職するしかないですよね?
どう内職する?
基本的には、青チャート等の網羅性の高い参考書を開いて、苦手をひとつひとつ潰していくのに時間を費やすのでいいと思います。これをやって時間が無駄になることは絶対にありません。最高の内職です。迷ったらコレです。
「参考書はひと通りマスターしたしなあ」という人は、自分のレベルに合った問題集を使って演習をしましょう。正直、文系の場合、限りある放課後の時間を数学の演習に割くのは若干もったいない気がしています。数学は、学校の授業時間だけで完結させるというのがベストです(文系ならそれが可能だと思います)。
ちなみに私は、高2の半ばからずっと、ひたすら赤本を解いていました。東大の問題は1問20-25分想定なので、授業1回あたり2問ですね。問題を解いて、解説を読んで…を2回繰り返すというのをずっと続けていました。東大の赤本(27年)、駿台•代ゼミ•河合の東大模試過去問10年分以上、京大の赤本(27年)、一橋の赤本(27年)…くらいはこなしましたね。