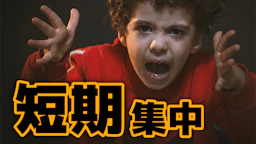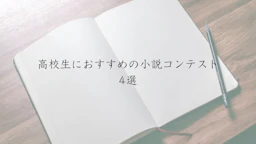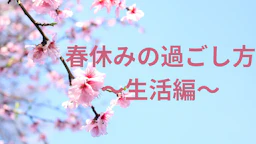春休みはバランスを崩せ part2
どうも、フジです。
今回はpart2なので、前回の続きとなっています。先にpart1をお読みいただいたほうがいいかもしれません。
単位はデカい方がいい
前回は、全体を細分化してそれぞれの完成度をあげていく…という話をしました。そこで、数学は単元に分解されると述べましたが、もう少し丁寧に分解すると「数学→数I/数A/数II/数B→各単元」となりますね。単元のうえに、4つの大きな”科目”があって、それを全て束ねるのが”数学”という教科ということです。
前回の結論は「単元ごとに丸ごと学習するべし」としましたが、実は、丸ごと学習する単位はデカければデカい方が効率がいいと私は考えています。
要は、できることなら数Iをいっぺんにマスターしちゃったほうが効率がいいよね、ということです。半年かけてチンタラ数Iを勉強して完成度を高めていくよりは、春休みなら春休み、短期集中で丸ごと数Iをマスターしてしまったほうが圧倒的に効率がいいと思うのです。この理由については、前回の全体像云々の話とは違って、どちらかというと気持ち的な側面の方が強いのかなと思います。
次の数IAの実力テストに向けて、二次関数だけマスターしたところで、その実力テストでの高得点は望めません。「まあ二次関数の問題は解けて、その分点数は上がったよね」でおしまいです。しかし、数Iを丸ごと完璧にして挑むと、きっとそれなりの点数になるでしょうし、「おお!点数めちゃくちゃあがったやん!嬉しい!次も頑張ろう!」というモチベーションアップにも繋がるのです。
「単元」という最小単位(これ以上細分化できないまとまり/これ以上細かくするとわかりづらくなっちゃう限界)をさらに分割する勉強は効率を悪くし、逆に「単元」の上のまとまりごとに勉強する場合は、メンタル面で効率が良くなるということですね。
私も長期休暇はそうしてた
数学の話ばかりしていたので、次は、私の実体験をお話しましょう。
私は高1の時、世界史が苦手でした。定期テストでは毎回60点前後(平均点以下)と、なかなか悲惨な状況だったんです。なのになぜか文系を選んじゃったので、高1の冬休みを世界史に全振りしたんですよね。
他の教科との兼ね合いを考慮して、単元ごとにひとつひとつできるようにしていく(冬休みで間に合わなかったらしょうがないよね)という選択肢も当然ありました。でも、私は高1で習った世界史全てを冬休みで完成させることを優先したんです。現状最も大きな単位がそれだったからですよね。もちろん、他教科の勉強がゼロというわけではありません。世界史以外はギリギリの最低限を攻めつつ、世界史に1日4-5時間ベットするって感じです。
結果、冬休み明けの実力テストにおける世界史の学年順位は1桁、以後高いモチベーションを維持し、高3の最後までその順位帯に留まり続けました。これは、高1の冬に丸ごと世界史を詰めたことのおかげだと思っています。
ちなみに、高1の夏休みは英単語の完成に努めました。夏休みは長すぎて、英単語に全振りする必要までは流石になかったのですが、とはいえ夏休み前に購入した鉄壁を1ヶ月で完璧にするのはなかなか大変でしたね。
英単語帳は、適度に細分化してコツコツ覚えていくのもアリだとは思いますが、私はまとめて詰め込んだ方がプラスに働くと考えていたので、夏休み明けまでにという目標を立てて取り組みました。そのおかげで、夏休み前と後で明らかに長文の読みやすさが異なり、モチベーションが高まったのを覚えています。
最後に前回同様注意点ですが、”他教科の勉強時間はゼロ”になるのはマズイです。最低限やらなきゃいけないことだけはやるというスタンスで、ギリギリの勉強時間は確保してください。
ということで、以上。
是非実践してみてください。