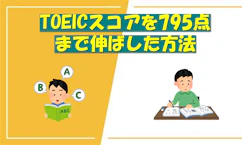リスニング力を高めよう!
どうも、フジです。
今回は「ぜひリスニングの方法についての記事を書いて頂きたいです!」というリクエストにお応えして、英語リスニングの学習に取り組む上での考え方と具体的な練習法について、これまでにも書いてきたものをうまい具合に集約して、ひとつの記事で紹介します。
「リスニングの勉強はしてるつもりなのになかなか得点に結びつかない」「何をやれば伸びるのかがよく分からない」という悩みを抱えている方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。私自身、リスニングで苦戦した経験がありますが、それでも最終的には東大の入試で戦えるレベルには到達できました。その過程で整理された視点や方法をもとに、今回は「確実に東大レベルのリスニング力が身につきます」とまでは言わずとも(涙)、「こう考えて取り組むことで前進はできるはず」という内容をまとめています。
リスニング練習の目的を見失うな
まず最初に伝えておきたいのは、リスニング練習の「目的」についてです。
多くの人は、「リスニング問題を解けるようになること」を目標に据えがちですが、これは本質的にはズレています。問題を解けるようになることは重要ですが、それは副次的な成果であって、本来目指すべきなのは「英語を聞き取れるようになること」です。
この2つは似て非なるものです。
リスニング問題を解くためだけのテクニック練習に偏ってしまうと、結局のところ「音が聞こえないけど何となく解く」という力しかつきません。一方で、英語の音がきちんと聞き取れるようになれば、試験問題であろうが実践的な英語であろうが、柔軟に対応できます。
つまり、我々がやるべきはあくまで「音声に対する解像度を高めていくこと」であって、「問題の点数を取ること」はその延長線上にあるんだという認識を忘れてはいけません。
この考え方は表面的には地味に思えるかもしれません。しかし、リスニングで得点できるようになった人の多くは、「まず聞き取れるようになった」結果として点が取れているだけであり、「問題に慣れたから得点できるようになった」という順序にはなっていないのです。そういう意味で、「聞き取れる状態になること」を最優先に据えるのが、リスニング力向上の出発点になります。
基礎なきリスニング練習は意味がない
リスニング対策に入る前に、必ずチェックしておくべきポイントがあります。
それは「英語の基礎力が足りているかどうか」です。ここを無視してリスニングに入っても、効果は限定的でしょう。
英語の基礎とは、当たり前ですが「英単語」と「英文法」ですね。単語は見た瞬間に意味が反射的に出てくるレベルまで仕上がっているか。発音や複数の意味まで正確に把握できているか。文法は、文章の構造を瞬時に読み解けるようになっているか。こういった点を改めてひとつひとつ確認してみましょう。
そもそも英文が意味として理解できないなら、音としてそれを聞き取れるはずがありませんからね。だからこそ、まずは基礎の完成度を徹底的に高めること。英語の勉強時間の大部分を単語と文法に充てる覚悟で取り組むべきフェーズがある、という認識を持ってください。
ありがちなのは、「そこそこ覚えたしまあ大丈夫だろう」という自己満足でリスニング練習に進んでしまうパターンです。「完璧だと思っていた自分の基礎力」が、実は中途半端な完成度だったというケースは本当に多いんですよね。単語の意味を一つ覚えて満足していたり、読み方を曖昧なまま放置していたり、複数の意味や使われ方に対する理解が乏しかったり。こういった小さな穴が積み重なることで、音として聞こえてきたときに意味が取れないという現象が起きます。
基礎を甘く見ないこと。
「基礎に対する過剰なくらいのこだわり」があなたの伸びを支えます。
音声理解の土台を築く「音読」
基礎がある程度固まったら、いよいよリスニング練習の第一歩として「音読」に取り組みましょう。
音読は一見すると単純な練習に思えますが、実はリスニングにおいて極めて重要な土台を築く作業です。
リスニングでは「聞こえた英語をそのまま理解する」という処理が必要になりますが、それを実現するためには「語順どおりに意味を取っていく」習慣が欠かせません。そりゃそうです。みなさんもう既にお分かりかと思いますが、日本語の語順で理解するクセが残っていると、英語の音を聞いたときに処理が追いつかなくなりますよね。ここで音読。音読をすれば、この”英語の語順で理解する型”を自分の中にしっかりと築いていくことができるわけです。
音読を行う際は、まずは一文ずつしっかり意味をとらえながら、語順通りに理解することを常に意識しながら読み上げる練習を積む、これが非常に大切です。もちろん発音やリズムももちろん意識はしますが、それに気を取られすぎて内容理解がおろそかになるのは本末転倒です。音読の目的は「内容処理と意味理解の型を身体にしみこませること」であり、聞こえた英語をそのままの流れでで処理する練習として位置づけましょう。
音読を丁寧に繰り返していくことで、「この語順ならこういう意味がくるはず」という予測や、「こういう構文ならここで切れる」という構造把握が徐々に速く、正確になっていきます。この処理のスピードと型が、音声情報に対する理解力の下地となるのです。
ちなみに使う英文としては、内容が難しすぎず、自分の理解力に見合ったものを選ぶのが理想です。学校の授業で扱った長文問題とかがちょうどいいのかなと思います。内容がわからないまま進めても効果は薄いので、意味が取れる状態を前提として、繰り返し取り組むようにしましょう。
音と意味の処理精度を高める「精聴とシャドーイング」
音読によって英語の語順処理や意味理解の型がある程度身についたら、ここからはいよいよ実際の「音」に対応する力を鍛えていく段階に進みます。この段階で軸となるのが、「精聴」と「シャドーイング」です。
まずは精聴。これは英語の音声を一語一句を正確に聞き取る訓練です。ネイティブの話す英語には、音の連結や脱落、弱音化など、教科書では扱われない音の変化が数多く含まれています。精聴では、英語の音声を何度も繰り返しじっくりと聞き込み、どうしてもわからなければスクリプトと突き合わせて確認し、「聞き取れなかった音」をひとつずつ潰していく作業に集中します。
精聴を通じて「この表現はこう聞こえるんだ」「この単語はこういうふうに消えるんだ」という気づきを積み重ねることで、実際の音への慣れが形成されます。この慣れが、「知らないうちに音が消えていた」「なんとなく流れてしまった」といったリスニングでの聞き逃しを確実に減らしていきます。
そして、精聴で音が聞こえるようになったら、次に取り組むのがシャドーイングです。これは、聞こえた音を少し遅れて発話する練習で、「音の認識」「意味処理」「発話」という3つの処理を一体化して鍛えるトレーニングです。聞きながら意味をとり、同時に発話するというのはかなり高度な作業で、集中力と瞬発力の両方が求められますが、逆に言えばこの練習によって、英語を聞きながらリアルタイムで処理する力が大きく伸びていきます。
ここでひとつ注意しておきたいのが、「シャドーイングは音読の上位互換であり、シャドーイングを始めたら音読はもうやらないでいい」というような段階的なイメージを持たないようにねってことですね。音読とシャドーイングは目的が異なるため、並行して行うべきトレーニングです。音読は「意味処理の型」を鍛える練習であり、シャドーイングは「音に反応するスピードと精度」を高める練習です。どちらも役割が異なるからこそ、両輪として継続していく必要があるなあと個人的には思います。
まず音読で語順理解の型をつくり、精聴で細かい音の認識を固め、最後にシャドーイングで処理力を統合する。この一連のサイクルを何度も回すことで、「意味の分かる音声処理力」が着実に育っていくでしょう。
というわけで今回は以上。
リスニング力の向上は、結局のところ「地道な積み重ね」でしかありません。基礎の徹底と、丁寧な音への向き合い。それを毎日継続することが、遠回りに見えて実は一番の近道だったりもします。焦らず、自分の耳と英語の音の距離を一歩ずつ縮めていってください。
質問やリクエストがある方は、アプリ okke のマイページ「コメント・要望」から、フジ宛と明記して送ってください。お待ちしております!