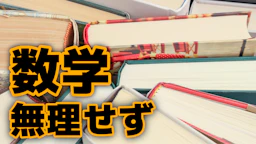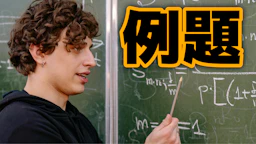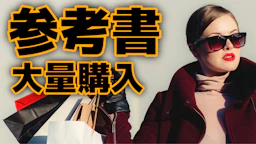“参考書ルート”で勉強した気になるな
どうも、フジです。
今回は「参考書ルート」という言葉が広まりすぎたことで、勉強の本質を見失いかけている受験生があまりにも多い、というお話。
「参考書ルート」を“こなすだけ”になっていないか
今の受験界隈では、「この順番でこの参考書をやればここまで到達できます」という“参考書ルート”なるものが、調べりゃ当たり前のように手に入ります。英語なら単語帳から文法・構文・長文へ、数学なら黄チャートから青チャートへ。まるで進化の道筋のように整然と並んでいるわけです。
見た目も美しく、進む方向が明確な分、安心感があるのもわかります。どこまでやればいいかが示されていると、努力の“終わり”が見えるからです。しかしその安心感がかえって、「あ、これをやっておけばいいんですね」「とりあえずこの順番で進めればいいんですね」と、思考を止めてしまう原因にもなる、これが問題なんですよね。
実際、今の受験生の中には“ルートを信じているだけの人”が少なくありません。まるで誰かに引かれた線路の上を走るように、進む順序を守ること自体が目的になってしまっている。けれどそれは、残念ながら勉強の本質から最も遠い姿勢に他なりません。
勉強は「何のためにそれをやるのか」から始まる
英単語帳や古文単語帳のように「覚えることが目的」と明確な教材なら、まだその目的を意識できます。しかし、英文解釈書や長文読解集、青チャートのような問題集になると、「とりあえず解けばいい」「ただ一周すればいい」と思い込んでしまう人が一気に増える。何を得るためにやっているのか、つまり取り組む目的を考えないまま取り組む勉強は、どれだけ時間をかけても“作業”でしかありません。
どんな参考書を開くにしても、最初に考えるべきは「自分は何をできるようになりたいのか」です。
これを明確にしないまま進める勉強ほど、無駄の多いものはありません。同じ教材を使っても、伸びる人と伸びない人がいますが、その差はセンスではなく、意識の深さでしょうね。「なぜこの参考書をやるのか」「どんな力を身につけるために取り組むのか」、これを自分の中で言語化できていない人は、努力量を重ねているのに前に進んでいる実感がない…という状態に陥ってしまうわけです。
「何を得たいか」を最初に決めること、これがめちゃくちゃ重要です。
「〇〇をできるようにするために〇〇をできるようにする」
目的を定めたら、あとはその目的を達成するために“できるようになるまでやり切る”ことです。勉強というのは、「これをやっておけば〇〇ができるようになる」ではなく、「〇〇をできるようにするために〇〇をできるようにする」営みなんですよね。
ただ、目的意識を持つだけではなんの意味もないってこと。
せっかく目的をハッキリさせたのなら、それを達成するために試行錯誤し、取り組み方を工夫し、そして最後までやり切らなければなりません。目的意識を持ったとしても、教材を終えることに満足していてはダメで、“終わった”ではなく“できるようになった”状態を目指すよう心掛けてください。「できるようになるまでやってないから、できるようになっていないだけ。できるようになりたいなら、できるようになるまでやれ」、シンプルですがこれが勉強の真理だと思います。この意識を持つだけで、勉強は別物になるでしょう。
勉強というのは、ページを進めることではなく、「自分が今、どんな力を身につけようとしているのか」を理解しながら取り組むことなんですよ。それを理解した上で、“参考書を終える”ことではなく、“できるようにする”こと、ここを意識できている人だけが、着実に伸びていくでしょう。
というわけで今回は以上。