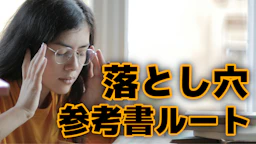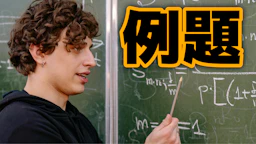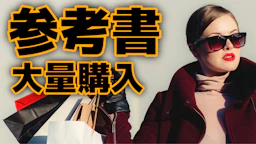“自分のレベルに合った”参考書を選べ!
どうもフジです。
今回は、数学の参考書について。
昨日の記事で、「解説を読んで理解するのだけでも例題1つに15分かかっちゃうんだって場合は、おそらく問題集のレベルが不相応なんでしょう。もうひとつ易しい、解説が丁寧な問題集に切り替えるべきです。」という話をしたので、そこの深掘りです。
「とりあえず青チャート」ではダメなのか?
進学校の高校生であれば、多くの人が「青チャート」あるいは「フォーカスゴールド」といった分厚い参考書に触れたことがあるのではないでしょうか。これらは多くの高校で“標準”の教材として配布され、定期テストも基本的にはその中から出題されることが多い印象です。
配られた教材をそのまま使う……それ自体は自然な選択です。でも「配られたからそのまま青チャートを使っているけど、実はかなり難しく感じている」という人、いませんか?
もし「なんかむずいなあ」と感じているのなら、その感覚、無視しない方がいいと思います。それは単に自分の努力不足でもセンスの問題でもなく、“その参考書が今のあなたのレベルに合っていない”という可能性が高いです。
「解説の丁寧さ」で選べ
参考書選びにおいて大切なのは「どこまで自分を導いてくれるか」、つまり「解説の丁寧さ」です。
例えばチャート式。白チャート、黄チャート、青チャート、赤チャート。いろいろ種類がありますが、これらの違いってなんだかわかりますか? 扱っている問題のレベル帯がズレているってのは、そりゃそうなんですが、それ以外にも明確な違いがあるんです。
私は高校生のとき「学校で青チャートを配布されたけど赤チャートを愛用してた人」でした。一般的に「赤チャート=超上級者向けの難問を集めた問題集」というイメージがあるかもしれませんが、実際に中身を見てみると、実は、1段階下のレベルの青チャートに載っている問題までも網羅的に掲載されている。だから私、「青チャートと赤チャートの違いってなんなんやろ…」と思って、同じ問題の解説を見比べてみたことがあるんです。そしたらまあ、違う違う。出題されている問題のレベル帯だけでなく、「どこまで丁寧に解説するか」も違う、これめちゃくちゃ重要ですね。
赤チャートは「なぜそう考えるのか?」まで踏み込んだ本質的な説明が多く、青チャートはそこまで深くは突っ込まない所謂“普通の解説”が並び、そして黄チャートは赤や青では省略されがちな”行間”にも触れている、みたいな。
だから、もしあなたが今使っている参考書で「なんかむずいなあ」と感じているのならそれは、その参考書が「今の自分のレベルに相応な解説を与えてくれていないから」なのだと私は思います。書店に足を運んで、実際に解説部分に目を通してみて、そして「この解説ならすんなり理解できそうだ」と思える参考書を購入し、使用するべきなのです。
青チャートのような総合参考書は、確かに完成度が高く、最終的には全受験生にとって価値ある一冊です。私も過去の記事で「とりあえず青チャートの例題を完璧にしろ」といった話をしたこともあります。でも、それは“いきなり最初から使え”という意味ではありません。
今の自分にとって「解説が自然に読める」「スッと理解できる」と感じるものを選んでそこからスタートする。それが、結果として一番の近道になるんです。
というわけで今回は以上。