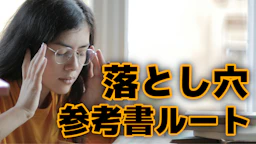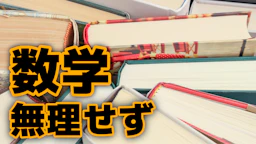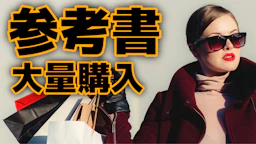「毎日例題〇問解く!」
どうも、フジです。
今日は、数学の網羅系問題集に載っている「例題」の捉え方について、少し角度を変えてお話ししてみようと思います。
数学を勉強するときに、その日の目標として「例題を〇問解く」みたいなノルマを自分に課している人って、結構多い印象があります。「数学は例題を完璧にするので十分」なんて言われてたりもしますから、悪いようには見えないかもしれません。でも私は、そういう“例題の使い方”には、ちょっとした違和感を抱いています。
例題はあくまで「例」
私はそもそも、例題を“解くもの”とはあまり捉えていません。
「例題」という言葉の通り、これはあくまで「こういう場面ではこう考えるんだよ」という“例”にすぎないんですよね。つまり、問題を通して「考え方」を提示してくれているに過ぎない。だから、例題で必要なのは“時間をかけて試行錯誤して正解すること”じゃなくて、“考え方の筋道を理解して納得すること”なんです。
一言で言えば、「読む問題」なんですよ。
納得できれば、もはや解かなくてもいい。
しばしば、「例題を1問解くのに15分や20分かかってしまい、1日で3問しか解けません」みたいな人を見かけるんですが、そういう人は、例題の捉え方がズレているような気がしますね。改めて言いますが、例題は“時間をかけて試行錯誤して正解する”みたいな使い方をするようなもんじゃありませんから。
ちなみに、解説を読んで理解するのだけでも例題1つに15分かかっちゃうんだって場合は、おそらく問題集のレベルが不相応なんでしょう。もうひとつ易しい、解説が丁寧な問題集に切り替えるべきです。
例題で示された考え方を使いこなせるか
何が数学において大事かというと、やっぱり“使いこなせるかどうか”じゃないですか。「この場面ではこう考える」と書かれた例題の内容を、ちょっと形式が変わった問題に出くわしても、しっかり引き出せて使えるか、ここで差がつくわけです。
だから、例題を読んで理解したら、次にやるべきことは明確。練習問題を解くことです。
多くの網羅系問題集には、例題のあとにセットで練習問題がついていますよね。あの練習問題こそが“主役”です。例題の考え方を使ってみて、自分の中に落とし込めているかどうかを試す場です。ここで初めて「理解」が「実力」に変わるんです。
よく「〇〇チャートの例題を完璧にするだけで点数取れるようになる!」みたいなことが言われていますが、この「例題を完璧にする」っていうのは、例題を解いているだけじゃ達成できないモンなんですよ。これを言っている人の中に、「僕は例題しか解いたことないです!」なんて人は絶対にいません。必ず練習問題を解いて、知識を使いこなすための練習をしています。
「毎日例題〇問」はズレてる
ここまで読んでもらえればもう察していると思いますが、「今日は例題を5問解く!」みたいな目標設定、実は本質からズレているんです。
その日の進捗を「”例題”を何問“解いたか”」で測ろうとすると、どうしても「読んで理解する→使いこなせるかどうか試してみる」という本来の流れではなく「時間をかけて試行錯誤して例題を正解する」というだけになってしまいがちです。しかも、例題を解くのに時間をかければかけるほど、「頑張った感」も得られるから、自己満足の罠にもハマりやすい。
実際に点数が取れるようになるのは、例題の内容を使う「練習問題」をこなした先にしかないからです。
だから、目標を立てるなら「例題を〇問解く」ではなく、せめて「例題〇個分進める」くらいにした方がいい。そのうえで、「例題で得た考え方を練習問題で試す」ところまでを、1セットとしてやっていくべきです。最終的に問われるのは、“例題を何問こなしたか”ではなく、“その考え方を使えるようになったか”です。
というわけで今回は以上。