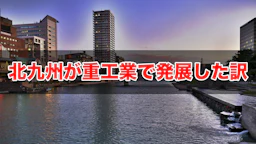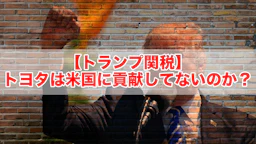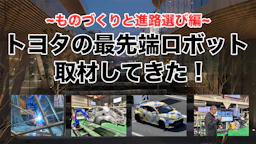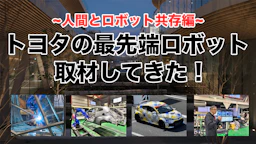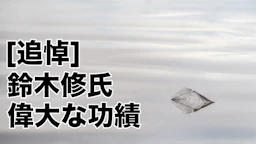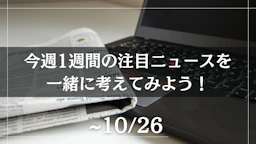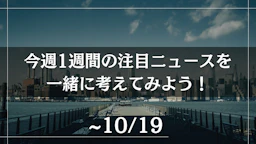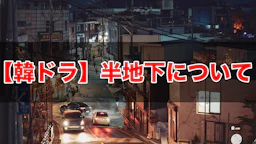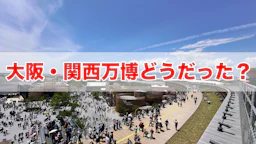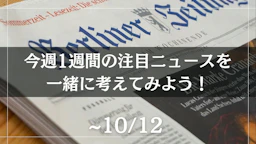皆さん、こんにちは。
突然ですが、東京スカイツリーを見たことがありますか?
首都圏に住んでいる方なら一度は見たことがあるでしょうし、そうでは無い方でもテレビやドラマなどで見たことがあるのでは無いでしょうか?
ご存知の通り東京スカイツリーは高さ634メートルを誇る日本一の建造物であり、世界でも2番目に高い建造物です。
そんな東京スカイツリーには最先端の技術が詰め込まれていると思われがちですが、実は奈良時代の技術を応用している事をご存知でしょうか?
今回は、東京スカイツリーに奈良時代の技術がどのように活かされているのかについて話していきます。
東京スカイツリーとは?
まず東京スカイツリーについて簡単に説明します。
東京スカイツリーは、2012年に開業した東京都墨田区に位置する高さ634mの電波塔です。
東京タワーがテレビ電波等の送信機能を担っていましたが、高層ビル等が周囲に乱立するようになり、その役目を果たすのが難しくなっていました。
そこで東京タワーの機能引き継ぐために計画されたのが高さ600m超の東京スカイツリーでした。
当時、高さ600m級の建造物を建てるという計画のもと、中国の上海が対抗し高さ600m建造物を建設しましたが、東京スカイツリーはそれを上回る634メートルの高さで世界一の電波塔となりました。
しかし、地震大国日本でこのような超高層建築物を建てるためには、強靭な耐震技術が不可欠でした。
そこで採用されたのが、奈良時代から続く伝統的な建築技術「心柱制振構造」でした。
奈良時代の技術「心柱制振構造」とは?
この心柱制振構造は、奈良県にある法隆寺の五重塔に採用されているものです。
法隆寺はご存知の通り世界最古の木造建築であり約1300年以上の間、地震や台風にも耐えてきました。
その秘密が「心柱」と呼ばれる中央に配置された柱にあります。
心柱は、建物のメイン構造とは独立しており、地震等で揺れが発生した際に建物の揺れとずれて動くことで、揺れのエネルギーを分散する役割を果たします。
この仕組みにより、法隆寺の五重塔は長年の自然災害を乗り越えてきたのです!
そして東京スカイツリーもこの技術を応用し、塔の中央に高さ約375メートルの心柱を設置しました。
この心柱はメイン構造とは独立しており、地震発生時に本体の揺れよりも少し遅れて動くことで、揺れを最大50%軽減することができます。
これにより、東京スカイツリーは超高層建築物でありながら、地震に非常に強い建物となっています。
ちなみにこの心柱は地面と直接は繋がっておらず地面から浮いている状態となっています。
東京スカイツリーに採用されたその他の先端技術
東京スカイツリーには、奈良時代の技術を応用した物だけではなく、現代の最先端技術もふんだんに使われています。
超高強度コンクリート
長さ375mにもなる心柱には非常に高強度なコンクリートなどが必要でした。
そこで使われたのが、通常のコンクリートの約1.5倍の強度を持つ「超高強度コンクリート」です。
これにより、巨大な心柱を造ることが出来き、東京スカイツリーの高い安全性を実現しました。
脅威の3本構造
東京スカイツリーの周辺には水路や線路があり、限られたスペースでスカイツリーを作る必要がありました。
通常、高層建築では4本や5本の柱を用いて安定性を確保しますが、スカイツリーではスペースの関係上、主要な基礎柱は3本のみで構成されています。(参考までに東京タワーは4本の柱で支えている)
そして3本の柱を三角形状に設置することにより、3本の柱へ均等に力を分散させています。
また上に上がるにつれて三角形状から円形へと形を変化させており、風の抵抗も最小限に抑えられています。
 (東京スカイツリーと東京タワー)
(東京スカイツリーと東京タワー)
(東京都内にて著者が撮影)
まとめ
このように東京スカイツリーは、最先端技術は勿論のこと、奈良時代の伝統的な技術「心柱制振構造」を取り入れることで、高い耐震性を誇る建造物となりました。
また、超高強度コンクリートや限られたスペースでの基礎設計など、さまざまな工夫が施されています。
私自身も東京スカイツリーに訪れたことがありますが、東京都内を一望出来るのは勿論のこと、天気が良ければ富士山や筑波山も見ることが出来ます。
皆さんが東京スカイツリーに訪れた際には、ぜひ東京スカイツリーを支える技術にも注目してみてはいかがでしょうか?
最後までありがとうございました。