とうとう先日、2025大阪・関西万博が閉幕しました。
この大阪・関西万博、入場者数は公式発表によると2800万人以上、黒字額も280億円に上り、大きなトラブルもなく、多くの方々に夢と希望を与え、盛大に成功のうちに閉幕を迎えました。
そこで今回は、「大阪・関西万博、どうだったのか」、私自身の体験も交えてお話ししていきます。
若い世代にとっての万博体験
私は、以前の記事を見ていただいたらわかると思いますが、取材で1回、さらにプライベートで1回の計2回大阪・関西万博に行っています。
会場では、大屋根リングをはじめ、世界中の展示物や最先端の技術を実際に体験することができました。
その中で私が感じたのは、「この若い時期、つまり10代のうちに世界一の博覧会を体験できたことこそが、何よりの財産である」ということです。
もちろん黒字額などの数字も大切ですが、それ以上に、日本の若い世代が最先端技術に触れるチャンスを得られたということが大きなものだと私は感じます。
この体験を通じて、多くの若者が未来への希望を感じ、そこから新しい技術や文化が生まれていく。
それこそが今回の万博のレガシー(遺産)であり、象徴的な成果だと私は思います。
(数々の最新技術に触れることができた大阪・関西万博)
(大阪・関西万博にて筆者が撮影)
万博に関する3つの誤解
ここで、よくある3つの誤解について訂正したいと思います。
①入場者数
公式発表では総入場者数は約2800万人以上とされていますが、一部の報道では「2500万人」とも言われています。
もちろん、一般の入場者数で言えば約2500万人前後でありますが、関係者を含めると総入場者数は約2800万人以上となります。
そして万博の通例では関係者パスで入場した人も含めるのが一般的であり、今回の万博だけ「別の計測方法」にするのはアンフェアです。
当然、公式発表も通例通りの計測方法に基づいており、「総来場者数約2800万人」が正しい数字となります。
ちなみにこの2800万人という数字は、歴代万博の中でもトップ10前後に入る大盛況でした!
②黒字額の扱いについて
今回の大阪・関西万博の黒字額は約280億円となり、愛知万博などを大きく上回る額なのですが、一部「建設費を含めれば赤字ではないか」との批判も見かけます。
まずそもそも万博では「建設費」を損益に含めないのが通例となっており、今回の万博だけの話ではありません。
また大阪・関西万博の経済効果は数兆円とも試算されています。
したがって、この黒字額280億円超という数字は正しいものであり、むしろ経済効果を含めれば“とんでもない成功”であったといえます!
(万博を牽引してくれたミャクミャクさん)
(大阪・関西万博にて筆者が撮影)
③BEVバスは本当に中国製?
次の誤解がシャトルバスです。先日とある大手メディアの記事で「BEVバスは全て中国製だった」と報じられているのを目にしました。
また他のメディアさんも「万博のBEVバスの殆どは中国製」などとの報道されている影響で「なぜ日本開催なのに中国製なの?」そう思われているかもしません。
ただこの報道、誤解を招く誤った報道だと自信を持って断言させてもらいます。
私は実際に桜島駅(万博会場最寄りのJR線の駅)から万博会場へのBEVシャトルバスを利用しましたが、大半は日本のいすゞさんのBEVバスでした。
もちろん私は全ての車両を確認したわけではありませんが、少なからず「全て(殆ど)のBEVシャトルバスが中国製」というのは完全な誤りです。
むしろ、日本のものづくりの力をふんだんに活かした万博だったと言えるでしょう!

(日本のいすゞ製のBEVシャトルバス。しっかりといすゞのロゴが確認できる)
(シャトルバス乗り場にて筆者が撮影)
※BEVとは電気自動車です。
批判を乗り越えた7年の道のり
この大阪・関西万博の誘致が決定したのは2018年。
そこから開催まで約7年という長い年月を経て実現しました。
開催に際し多額の費用がかかることから、問わず賛否両論を呼びました。
しかし、最終的には約2800万人の来場者が訪れ、終盤には連日20万人以上の入場制限がかかるほどの大盛況となりました。
改めて、開催に尽力されたすべての方々に感謝を申し上げます。
万博が残した未来へのレガシー
2025大阪・関西万博は閉幕しましたが、私たち若者にとっては一生の糧として心に残り続ける出来事です。
この経験をきっかけに、きっと未来の日本から新しいイノベーションや文化が生まれていきます。
次回のフルスペックの万博は2030年のリヤド万博(サウジアラビア)、こちらも大規模な開催になる予定です。
また、2027年には規模は少し小さくなりますが、「横浜花博」が開催予定です。
改めて関係者の皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんが残してくれたレガシーは、確かに私たち若者の心の中に生き続けています。


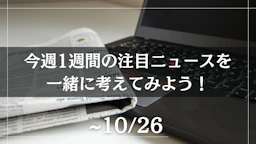

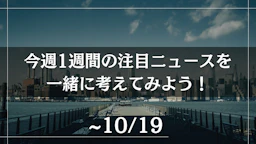

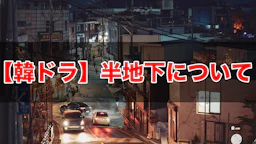
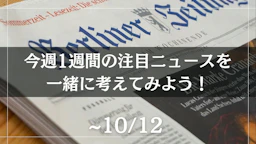
.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)