こんにちは北の大学生です!
今回は高校数学で学んだ内容は、将来どんなことに活きるのかについて書いていきたいと思います。自分が工学部の大学生であることもあり、大学に入ってどのようなことに使ったか、という体験談として書いていきます。
数学で養われる論理力などはめちゃくちゃ幅広く役に立っていきますが、数学で学ぶ「内容」自体は何か役に立つのでしょうか?
勉強のモチベーションがない人も、ぜひこの記事を読んでやる気を出してもらえればなと思います。
物理編も書いているので、ぜひそちらも読んでみてください。
そもそも大学の勉強についていくのに必要
文系の場合は分かりませんが、理系の場合は数学が出来ないと勉強についていくのが厳しいと思います。私が通っている工学部の機械工学科では、そもそも数学が出来ないと、物理など他の科目の内容も理解できないので、間違いなく留年します。
例えば材料力学だと、微分や積分を用いて材料のたわみ(変位)を求めたりします。また、制御工学だとラプラス変換という数学の考え方を用いて機械の制御を行ったりします。
このように勉強内容は難しいですが、その分将来に活きる勉強内容ばかりなので、数学的なところさえ乗り越えられれば勉強していて楽しいですし誇りを持てると思います。
具体的にどんな分野が活きる?
微分・積分
高校で学んだ微分・積分は大学の4力(熱力学、流体力学、材料力学、機械力学)や電子回路など、本当にたくさんの科目で必要になってきます。
特に大学では微小変化(Δx,Δtなど)での議論がとても多くなってくるので、微分や積分の概念の理解は必須です。
上で出てきたラプラス変換では積分の知識が必要ですし、回路に流れる電流や電圧を求めるためには微分方程式や積分方程式を解くことが必要になります。
例えば電磁気の回路の問題だと、下のようにキルヒホッフの法則から微分や積分が含まれる方程式を立て、これをゴリゴリ解くことによって回路に流れる電流や電圧が求められるのです。.jpeg?w=499&h=166)
「微積物理」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、大学物理では微積分が密接に関わってくるのです。
電磁気の他にも、例えば飛行機にかかる揚力を求める際にも微積分の知識が大事になってきます。流体力学では飛行機の周りの空気を流体とみなすのですが、流体は微小体積や微小区間で考えることが多いので、数学が得意でないと、飛行機が飛ぶ仕組みを詳しく理解できません。
飛行機が飛ぶ仕組みを詳しく説明出来たらかっこいいのに、数学が苦手なせいで説明できないなんてもったいないです。
ただ逆にそれが理解できていれば、飛行機が空を飛ぶ仕組みについても理解できるので、どうやったらうまく飛ぶか等についても議論できるようになります。鳥人間コンテストにも参加できるかもしれませんね。
今回はここまでです!
それでは読んで頂きありがとうございました🙏
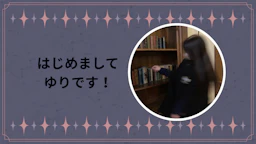

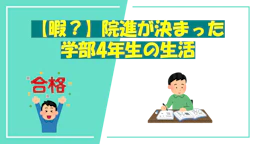
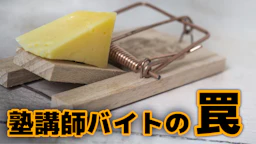

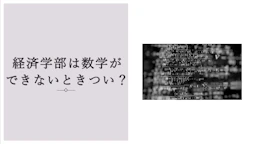
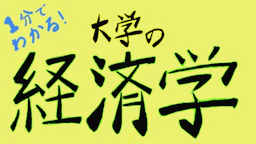
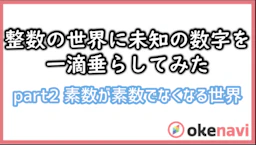
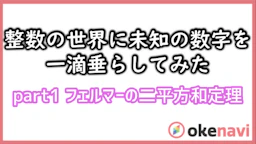
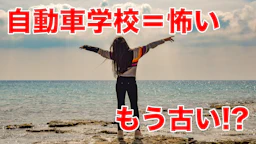
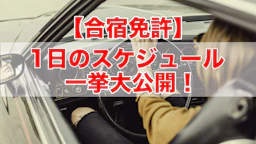


.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)