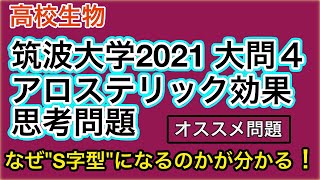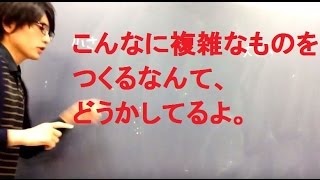シャペロン 高校生物
概要
動画投稿日|2021年3月15日
動画の長さ|0:56
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
*基本的に下記の★の内容以外は発展。しかし、タンパク質の『フォールディング(折畳み)』の概念については、たまに難関大で問われる。
●シャペロン(分子シャペロンともいう)は、タンパク質の正しい立体構造形成(フォールディング)を助けるが、最終的な構造体には組み込まれないタンパク質の総称である。
●すべてのタンパク質が正常な立体構造の形成にシャペロンの助けを必要とするわけではない。自然に正しい立体構造に折りたたまれるタンパク質も多い(たとえば、疎水性のアミノ酸は、水を避け、ポリペプチドの内側に自然に配置される)。
●シャペロンの中には、熱変性によって異常に折れ曲がってしまったポリペプチドを元に戻す働きを持つものもある。そのようなシャペロンは高温で合成が促進される(ピンチになった時やってくるヒーローのようである。なお、高温で合成が誘導されるタンパク質はヒートショックタンパク質と呼ばれる)。
★タンパク質の構造について
①タンパク質の一次構造:アミノ酸の配列。
②タンパク質の二次構造:ポリペプチド鎖(アミノ酸の鎖)の『部分的』な立体構造。二次構造の例として、α-ヘリックスとβ-シートが非常によく問われる。
③タンパク質の三次構造:1本のポリペプチド鎖『全体』の立体構造。
④タンパク質の四次構造:何本かのポリペプチド鎖が集まってとる構造。その時、四次構造をつくるポリペプチド鎖1つ1つをサブユニットという。サブユニットは部品のようなイメージ。すべてのタンパク質が四次構造をとっているわけではない。三次構造までしかとらないタンパク質もある(たとえばヘモグロビンは4つのサブユニットが集まって四次構造をとっている。対して、筋肉に酸素をためておく役割をもつミオグロビンは1本のポリペプチド鎖であり、四次構造をもたない)。
●「シャペロン」とは元来、社交界で介添人を務める婦人のこと。
●シャペロンは原核生物、真核生物の両方に広く存在する。特に発現量の多いHSP60( GroEL )ファミリーに属するシャペロンをシャペロニン( chaperonine )と呼ぶ。
「タンパク質の触媒的、制御的あるいは後生的な機能を分析すれば、これらの機能はすべて、なによりもまず、タンパク分子の立体構造的な結合能力にもとづいていることを認めないわけにはいかなくなる。」モノー(オペロン説の提唱者)
#タンパク質
#高校生物
#シャペロン
関連動画
関連用語