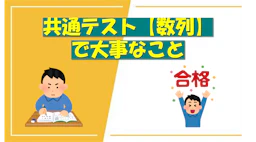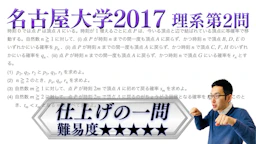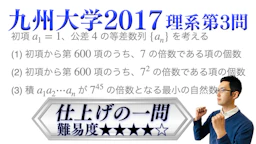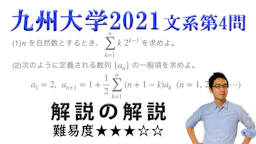こんにちは北の大学生です!
今回は数列について、減点されないための記述の仕方について書いていこうと思います。2次試験で記述式の数学がある方は、ぜひ1つの参考にしてください。計算ミスに気づく方法も最後に紹介します。
試験のときだけしっかり答案を書こうとしても、時間もかかって失敗すると思うので、普段の演習から意識して、ノートに丁寧な答案を書くようにしましょう。自分で読み返してみるのも効果的です。
減点されないための記述
数学的帰納法という証明方法を明記する
「全てのnで〜が成り立つことを示せ」系の証明問題などで、数学的帰納法を用いることがありますよね。
このとき、「数学的帰納法により証明する / 証明された」と書かないで証明してしまうと、採点者にとって「どうやって証明されたのか」がパッと見てわかりません。
減点はないかもしれませんが、どのような証明方法なのかを一文書くだけで、採点者にとって「あ、帰納法の答案なのね」と内容がとてもわかりやすくなるので、書かない理由は無いです。
もちろん、証明の論理が合っていることは大前提(例えば、n=1のときに成り立つことを示し、n=kで成り立つと仮定したときn=k+1でも成り立つことをきちんと証明する)ですが、採点者に自分の論理をしっかり伝えるためにも、答案の見た目にも気を配りましょう。
成り立っている事実と、自分で置いた仮定や予想を区別する
上の数学的帰納法とも関連しますが、「成り立っている事実と、自分で置いた仮定や予想を区別する」ことはとてもとても重要です。
どういうことかというと、例えば数学的帰納法で「n=kで成り立つと仮定したとき、n=k+1でも成り立つことを示す」ということをやりたいとします。
このとき、「n=kで〜〜が成り立つ。n=k+1のとき〜」と書くと論理的に間違いなので、大きく減点をくらうでしょう。理由はわかりますか?
「n=kで成り立つ」ことは、すでに示されている事実や与えられている事実ではなく、あくまでも自分で成り立つことを仮定するものなので、「成り立つ」と言い切るのは間違いで、「n=kで〜〜が成り立つと仮定する。このもとで、n=k+1のとき〜」と書かなければなりません。
※ これと「n=1のときに実際に成り立つことを示す」ことを組み合わせることによって、パタパタとドミノが倒れていくようにして、全てのnについて示したことになる、というのが数学的帰納法の証明のポイントでしたね!とても大事なので、理解できていない方はわかりやすい動画などで納得しておきましょう。
日本語を省略して「n=kのとき〜〜(数式)」とだけ書く人も多いと思いますが、式だけ書いてしまうと、事実なのか仮定なのかが採点者に全く伝わらないので、減点される可能性が大きいでしょう。
同じように、「漸化式の一般項を推測して、それを示す」という問題もよく出てきますが、「おそらくこういう一般項になるな」というのが見えた時点で「an=〜〜である。」と書くと論理的に間違いです。
これも、まだこの時点では、「an=〜〜」というのは成り立つことが示されている事実ではなく、あくまでも推測でしかないので、「an=〜〜であると推測される。」と書いて、その後でそれを実際に示していかないといけません。
自分の論理をしっかりと言葉にして、採点者に過不足なく伝えられるようになりましょう。
式が成り立つnの範囲に注意する
これは、Snから一般項を求める場合や、階差数列の一般項を求める場合によく出てくる話ですが、「その式ってn≧2でしか成り立たないよね」という場面があります。(階差数列について、詳しくはこのokke用語の解説を見てみてください)
このときは、しっかりと式の後ろに(n≧2)などと書いて、nの範囲を明記しておきましょう。自分の頭の整理にもなります。
そして、もし一般項を求める必要があれば、a1については別途計算して、もしまとめられそうであればまとめる、という作業が必要です。
この確認をおろそかにすると、一般項を正しく求めていないことになるので減点をくらうでしょう。注意しましょう!
計算ミスに気づく方法
一般項に小さいnを代入して、答えが合っているか確認する
こちらは記述ミスというより、自分の解答が合っているか確認するための作業です。
せっかく難しい漸化式を解いたのに最後の一般項の答えが間違っていたら元も子もありません。
自分が求めた一般項にn=1,2,3あたりを代入して計算してみましょう。そして、元の漸化式にもn=1,2,3あたりを代入して、実際の項の値を求めて、一般項に代入した値と全て合っていれば、求めた一般項はおそらく合っているだろうということが分かります。
もし一致しなかった場合は求めた一般項の式が違うということなので、見直しをしてみましょう。
もちろん試験本番では時間との兼ね合いもあると思いますが、普段の演習から意識して確認するようにすることをおすすめします。
いかがでしたか?
自分が理解出来れば良いという考えは捨てましょう。採点してくれる人が読みやすく理解しやすい答案でないと、良い答案とは言えないです。
日本語や図が少なく数式や計算しか書かれていない場合、どのような思考で解答に至ったのか、採点者は判断できません。採点者がいる以上、もし最後の答えが合っていたとしても、記述があまりにも雑すぎて、内容を理解してもらえず減点されてしまっても全く文句は言えません。
こちらの記事にも答案の作り方について少し書いてあるので、ぜひ読んでみてください。
答案の書き方については、普段の演習から意識してみてください!
今回はここまでです!
それでは読んで頂きありがとうございました🙏