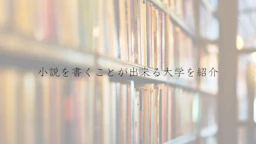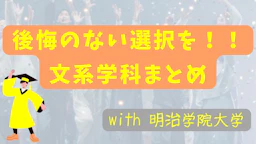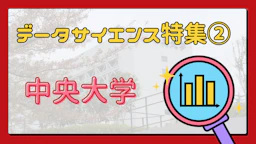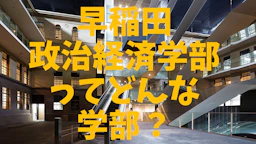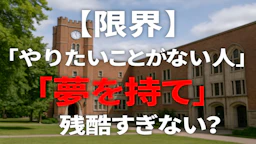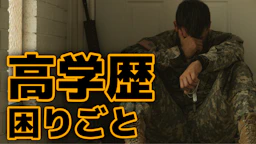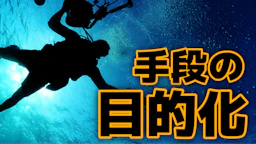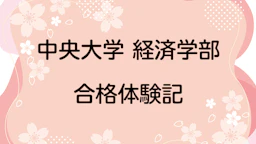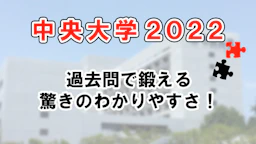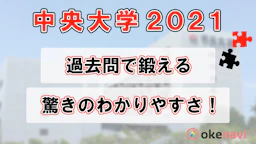受験生の方は、気温が下がるにつれて少しずつ気持ちが引き締まってくる時期だと思いますが、息切れはしてませんか?
モチベーションが上がらないなあというときには、個人的には大学に入った後のことをぼんやり考えてみるのがとてもおすすめです。
そこで、この記事では、大学や学部によらず挑戦できて、そのまま仕事につながる難関資格試験を3つ紹介します!大学生活のイメージを膨らませてモチベを上げたい人や、志望校を下げざるを得なくなって、大学で頑張って巻き返したいと思っている人にとてもおすすめです。
また、資格試験の合格実績があり、サポートがとても充実している大学の一つに中央大学さんがあるのですが、今回許可を頂きましたので、大学から得られる資格試験のサポートの例も紹介します!
大学で挑戦できる難関試験3選
これから紹介する国家試験は、どれも合格率は低く大変ではあるのですが、大学や学部によらず挑戦できますし、時間をかけてコツコツ取り組めば突破できないものはありません。また何といっても、その先ずっと続けることのできる、やりがいのある仕事が待っています。
間違いなく、時間と体力があるのは大学生の特権です!受験勉強が好きではなかった方も、大学に入ったら難関資格試験に挑戦して、将来の可能性をぐっと広げてみませんか?
① 国家総合職・一般職試験
これはいわゆる、〇〇省といった中央省庁で、国家公務員として働くための試験です。
試験に受かった後、自分が志望する省庁に何度も面接に行く必要があり(官庁訪問と呼ばれます)、試験に受かったからといって内定がもらえるわけではありません。いわゆる「キャリア官僚」と呼ばれる人たちは、この国家総合職に受かり、省庁で働く人たちのことを指します。
特に総合職試験については、法律、経済といった文系区分のみならず、工学などの理系区分や、専攻知識が問われない教養区分などがあり、自分が得意な専門分野で受験できるのが大きな特徴です。ただ、基本的に文系区分の場合は「事務官」、理系区分の場合は「技官・技術職」として働くことになり、その後のキャリアパスが変わってきます。
どちらの試験も、1つ1つの問題の難易度はそこまで高くないのですが、範囲がとても広いのが特徴で、数的処理と呼ばれる中学受験の算数のような問題や、推理クイズみたいな地頭系の問題も出てきます。総合職試験では、政策論文を書く試験もあります。
※ちなみに、県庁などの地方公務員として働きたい場合は、各自治体の地方公務員試験を受験することになります
② 公認会計士試験
これはいわゆる公認会計士になるために必要な試験です。
公認会計士試験に受かって、3年間の実務経験を積めば、公認会計士として働くことができます。また現在の制度上、公認会計士試験を突破し、一定の研修を修了すれば、税理士として働くこともできます。
高校生にとっては「会計」というもの自体のイメージが全然わかないと思うのですが、めちゃくちゃ簡単に言うと、会社の取引や財務状態を正しく記録するためのルール、という感じで、会計士は、会計情報のスペシャリストとして、会社に対してチェックやアドバイスなどを行います。
試験内容としては、法律や会計ルールが幅広く問われ、マークシート式の試験も論述試験もあります。(ちなみに、下の司法試験もそうなのですが、論述試験ではなんとボールペンしか使えません... !初めのうちはかなり緊張します)
簿記を知っている方は、簿記1級よりもさらに深い知識に、法律系の知識も問われる試験、というイメージです。
ちなみに、勉強に専念できる大学生でも、最終合格するまでに基本は2年くらいかかります。河野玄斗さんが約9か月で公認会計士に合格して話題になっていましたが、化け物です。
③ 司法試験
これはいわゆる弁護士・検察官・裁判官になるために必要な試験です。いろんな法律を幅広く勉強する必要があり、マークシート式の試験も論述試験もあります。
司法試験を受けるには、2つのルートがあり、1つは大学の学部卒業後にロースクール(法科大学院)に通って受験資格を得るパターン、もう1つは予備試験という試験に受かるパターンです。知らない人も多いのですが、実は司法試験は法学部じゃなくても挑戦できます。
1つ目のロースクールについては、法学部出身の学生用の2年間の既修者コースの他に、基本的に、法学部以外の学生用の3年間の未修者コースも設置されているので、法学部以外の人でも入学できます。
2つ目の予備試験については、学部関係なく、大学の学部在学中でも受けられる試験で、とにかく受かりさえすれば司法試験が受験できるので、めちゃくちゃ優秀な学生は、大学学部中に予備試験 → 司法試験まで突破して、ロースクールに進むことなく一足先に社会に出ることができます。ちなみに、年齢制限が無いので高校生でも受験できます!実際に高校生で受かった子もいて、以前話題になっていました。
司法試験に受かると、司法修習という1年間の研修(全国各地で行われます)があり、最後の修習生考試という試験に合格すると、めでたく判事補、検事、または弁護士となる資格を取得することになります。

大学からの資格試験のサポートを紹介!
ここまで、仕事に直結する難関試験として、目指す大学生も多いものを紹介しましたが、大学によっては、これらの資格試験へのサポートがとても充実しているので、志望校を決めるときの1つの軸として調べてみるのもおすすめです。
今回、資格試験に強い中央大学さんにお話をお伺いできましたので、ここでは中央大学での資格試験のサポートの例を紹介します。自分でもびっくりするくらい充実していました!
① 難関資格に特化したプログラムがある
難関国家試験に受かるためには、基本的に大学とは別に予備校に通うことになるのですが、中央大学の場合は、司法試験予備試験やロースクール進学のサポートを行う「法職講座」や、公認会計士などの取得のサポートを行う「公認会計士講座・簿記会計講座」が学内で開講されています。
大学の中で完結できるので、授業が終わってそのまますぐに資格試験の勉強ができる点も魅力的ですし、なんと費用は予備校の10分の1〜半分で、安く受講できます。バイトの時間も勉強に回したい学生にとっては、本当にありがたいプログラムですね。
また、OBやOGの実務経験者の方々が講師を務められているとのことで、実際の仕事内容なども聞けて、モチベーションも爆上がりしそうです。
実際、中央大学の司法試験や公認会計士試験の合格者数はどちらも全国6位で、結果にも出ています。また、私立大学の中で、国家一般職試験の合格者数は全国1位、国家総合職試験は全国3位とのことです。資格試験にめちゃくちゃ強いですね。(全て2023年度)
👉 プログラムの詳細はこちらの公式ページから!
② 資格試験の勉強に集中できる環境がある
大学受験でも同じですが、勉強に集中できる環境があることはとても大事ですよね。中央大学では、資格の勉強を頑張る学生に対して、なんと1人に1つ勉強机とロッカーを貸し出しているそうです!社会人の自分からするとうらやましすぎます。
多摩キャンパスには、通称「炎の塔」と呼ばれる、炎のように燃える情熱を持って頑張る学生のための施設があり、それぞれの資格試験のための研究所や研究室が入っています。茗荷谷キャンパスにも「学生研究フロア」と呼ばれる施設が設置されています。
自分だけの集中できる環境がありつつ、頑張っている他の人が視界に入ることで、モチベーションがとても上がりそうですね。

(炎の塔の外観)
(集中できる勉強環境が手に入る!)
(入るだけでテンション上がりそうですね)
本編はここまでです!いかがでしたか?
冒頭にも書いた通り、大学に入って、時間を活かして資格試験に挑戦している自分を想像してみると、受験を頑張るモチベーションも湧いてくるはずです。
中央大学は法学部が強いこともあり、難関資格試験に挑戦する学生が多く、それに合わせて大学からのサポートもかなり充実しているのだなと感じました。
どの試験も合格率は低いですが、コツコツ努力を継続することが最大の鍵なので、勉強のための環境はとても大事です(受験勉強で痛感している人も多いと思いますが...)。大学に入ってから難関資格試験に挑戦したい方にとって、同じように頑張っている学生と一緒に切磋琢磨し、充実したサポートを受けながら勉強を頑張れる点は、とても魅力的ですね!
共通テスト併用方式もあり、国立大学との併願もかなり多いようなので、受験校の1つとして検討してみてはいかがでしょうか?
中央大学の受験生向けのページもあるので、興味のある人はこちらから詳しく見てみてください!
読んでいただき、ありがとうございました。




.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)