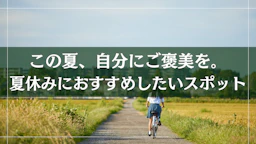こんにちは、Harunaです!
今回は「お盆は“ただの休み”じゃない!由来や歴史を詳しく解説」というタイトルでお届けします。
夏休みにも入り、そろそろやってくるのが“お盆”。
夏になると「お盆休み」や「帰省ラッシュ」といった言葉をよく耳にすると思いますが、「お盆ってなんのための行事?」「なんでみんな実家に帰ったり、お墓参りしたりするのか」この疑問に対して答えられる方はいますか?
私自身も、ちゃんと答えられないままこの歳まで過ごしてきました…。笑
そこで今回は、日本の伝統行事「お盆」について、その由来や歴史、現代の過ごし方までを詳しく解説していきます!
それでは早速、見ていきましょう。
あなたは知ってる?〜お盆の由来と歴史〜
お盆って、そもそもなに?
お盆とは、亡くなった先祖の霊が一時的にこの世に戻ってくると考えられている期間のことです。
毎年8月13日から16日ごろに行われるのが一般的で、この時期になると多くの人が実家に帰ったり、お墓参りをしたりします。
この行事の目的は、「先祖の霊を迎えて感謝の気持ちを伝えること」です。
家族や親せきが集まり、亡くなった人を偲ぶことで、命のつながりや家族の大切さを感じる機会にもなっています。
お盆の由来とは?
お盆の正式な名前は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。
これは、古代インドの仏教に由来する行事です。
昔、お釈迦さまの弟子である「目連(もくれん)」という人が自分の母親が亡くなった後、地獄で苦しんでいる姿を見てショックを受けました。
目連はお釈迦さまに相談し、「たくさんの人に施し(食べ物や衣服を分け与えること)をすることで母を救える」と教えられます。
その教え通りに目連が多くの人に施しをしたところ、母親は無事に成仏(じょうぶつ)できた、というお話が元になっています。
この物語から、「お盆には亡くなった人への感謝と供養が大切」とされるようになったのです。
日本に伝わったのはいつ?
お盆の風習が日本に伝わったのは、6世紀ごろ(飛鳥時代)といわれています。
最初は、仏教行事としてお寺で行われるものでした。
やがて、貴族や武士の間にも広まり、時代が下るにつれて庶民の家庭でも行われるようになりました。
江戸時代には、お墓参りや迎え火・送り火などの風習が一般的になり、現代につながっています。
現代のお盆ってどんな感じ?
今の日本でも、多くの地域でお盆の行事が続いています。
地域ごとに多少違いはありますが、代表的な過ごし方をいくつか紹介します。
◎お墓参り
先祖の霊を迎えるために、お墓を掃除してお花や線香を供えるのが定番です。
手を合わせて「ありがとう」と心の中で伝えることで、先祖とのつながりを感じられます。
◎迎え火・送り火
13日の夕方には「迎え火(むかえび)」、16日には「送り火(おくりび)」を焚く風習もあります。
これは、霊が迷わずに家に帰ってこれるように、そしてまた無事にあの世へ帰れるようにという願いを込めたものです。
◎精霊馬(しょうりょううま)
お盆の時期にスーパーなどで見かける、キュウリとナスに割りばしをさした飾り物。
これが「精霊馬」です。
・キュウリの馬:早く家に帰ってきてほしいという意味
・ナスの牛:ゆっくり帰ってもらいたいという意味
このように、早く来て、ゆっくり帰ってもらいたいという気持ちが込められています。
すごく独特なんですが、日本らしい優しさが感じられるものです。
◎盆踊り
地域によっては、「盆踊り」というお祭りが開催されるところもあります。
これは、先祖の霊を供養しながら、地域の人たちが一緒に踊って楽しむという伝統行事です。
浴衣を着て参加する人も多く、夏の思い出の1つになります。
最後に・まとめ
今回は「お盆は“ただの休み”じゃない!由来や歴史を詳しく解説」というタイトルでお届けしました。
この記事を通して、“お盆”について改めて知れましたか?
お盆は、「亡くなった人を思い出し、感謝の気持ちを伝える」大切な行事です。
夏休みの時期でもあるので、家族や親戚と一緒に過ごすいい機会でもあります。
昔から受け継がれてきたお盆の意味を知ることで、「ただの休み」ではなく、「心を込めて先祖と向き合う時間」になるかもしれません!
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
また次回の記事でお会いしましょう!
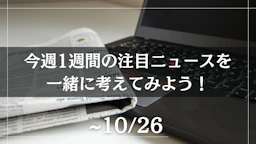

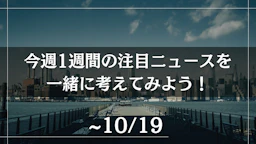

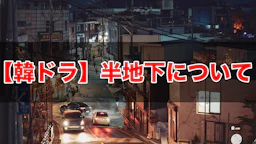


.png?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)