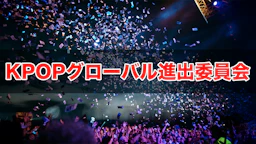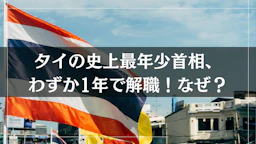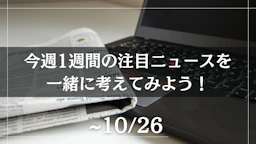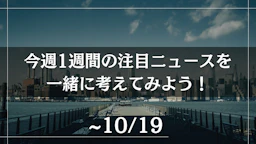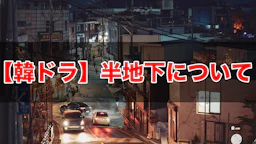皆さん、歴史の授業で習った「国際連盟」そして「国際連合」。
国際連盟は約100年前の1920年に発足し、国際連合は1945年に設立された国際組織ですが、名前が非常に似ているため、テストなどで「あれ?どっちがどっちだっけ?」と迷ったことがある方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、国際連合と国際連盟の違いについて解説していきます。
国際連盟の誕生と理想
まず、国際連盟について説明します。
そもそもこの2つの組織はいずれも、戦争の反省から生まれたものです。
第一次世界大戦では、世界中で約1,000万人もの人々が犠牲になったといわれています。
その悲惨な出来事を二度と繰り返さないようにと考えられたのが、国際連盟でした。
1919年のヴェルサイユ条約に基づいて1920年に発足し、初代事務局はスイスのジュネーブに置かれました。
この構想を主導したのはアメリカのウッドロウ・ウィルソン大統領で、彼が提唱した「十四か条の平和原則」が基礎となっています。
しかし、肝心のアメリカは議会の反対によって加盟できず、提唱国でありながら不参加という矛盾を抱えたままのスタートでした。
理想的な国際協調の第一歩ではありましたが、その段階からすでにほころびが見え始めていたのです。
国際連合の誕生と戦勝国の思惑
続いて、国際連合について見ていきましょう。
こちらは第二次世界大戦の反省をもとに設立された組織です。
第二次世界大戦中、ナチス・ドイツや日本、イタリアといった枢軸国に対抗する形で、アメリカやイギリス、フランス、ソ連(現在のロシア)、中華民国(現在の台湾)などが手を組み「連合国」という軍事同盟を結成しました。
この連合国こそが、のちの国際連合の原型となった存在です。
実は「United Nations(国際連合)」という言葉自体も、1942年にアメリカのルーズベルト大統領が提案したもので、本来は「戦勝国連合」という意味を持っていました。
つまり、国際連合は“第二次世界大戦の勝者たちによる秩序の維持”という性格を最初から備えていたわけです。
そして1945年10月24日、サンフランシスコ会議で国際連合憲章が採択され、アメリカ・イギリス・フランス・中華民国(現在の台湾)※・ソ連(現在のロシア)を中心とする51か国でのスタートとなりました。
この5か国は現在でも安全保障理事会の常任理事国として強大な権限を持っています。
※なお、創設当初の「中国代表」は中華民国(現在の台湾政府)でしたが、1971年の国連総会決議により「中国の代表権」は中華人民共和国に移されました。これにより中華民国(台湾)は国連から排除され、現在は中華人民共和国が常任理事国の地位を有しています。
国際連盟の理想と挫折
国際連盟は「戦争を防ぎ、平和を維持し、国際協調を促す」という崇高な理想を掲げていました。
しかし現実には、多くの問題を抱えていたのです。
まず全会一致制が採用されていたため、どんなに正しい決議でも、たった一国の反対で成立しないという欠点がありました。
さらに軍事的な裏付けがなく、各国への“勧告”しかできなかったため、実行力がほとんどなかったのです。
しかも提唱国アメリカの不参加に加えて、日本・ドイツ・イタリアといった大国が次々と脱退。主要国が抜け落ちたことで、組織の求心力は一気に低下しました。
その結果、満州事変やイタリアのエチオピア侵攻、ナチス・ドイツの侵略を止めることができず、ついに第二次世界大戦を防ぐことはできませんでした。
理念は立派でも、力が伴わなかった。
これが国際連盟の最大の弱点であり、1946年、国際連盟は正式に解散することになります。
国際連合の改良と現在の課題
第二次世界大戦後に発足した国際連合は、国際連盟の失敗を反省しながら、より現実的な仕組みを整えて設立されました。
例えば全会一致制を廃止して多数決制を導入し、さらに軍事的裏付けとして国連軍やPKO(平和維持活動)が行えるようになりました。
また、アメリカ・イギリス・フランス・中華民国(現在の台湾)※・ソ連(現在のロシア)という当時の大国が最初から参加することで、前回のような“主要国不在”を防ごうとしました。
しかし、現在の国際連合も決して完璧ではありません。
むしろ、かつての国際連盟と似たような問題を抱えていると指摘されることもあります。
最も深刻なのは、常任理事国による「拒否権」の存在です。
例えば、シリア内戦やロシアによるウクライナ侵攻などで国連が行動を起こそうとしても、ロシアや中国が拒否権を行使すれば、たとえ世界の大多数が賛成しても決議は成立しません。
こうして安保理が機能不全に陥っているのが現実です。
また、国連は第二次世界大戦の戦勝国によって作られた組織であるため、その構造は今も「勝者中心」です。
ドイツ、日本、イタリアといった敗戦国は常任理事国になれず、インドやブラジルなど新興国も同様に除外されたまま。
本当の意味での「世界の代表」とは言えない体制が続いています。
さらに、国際情勢が変化する中で、紛争の形も多様化しました。
国家同士の戦争だけでなく、内戦、テロ、民族対立、難民問題といった複雑な課題が増え、国連の仕組みが時代に追いつけていないのです。
財政面での問題も深刻です。
アメリカの分担金削減や加盟国の負担未納が相次ぎ、国連は慢性的な財政難に陥っています。
さらに、常任理事国の中に戦争当事国が存在することから、「国連は本当に平和を守るための組織なのか?」という根本的な疑問まで投げかけられるようになっています。
※なお、創設当初の「中国代表」は中華民国(現在の台湾政府)でしたが、1971年の国連総会決議により「中国の代表権」は中華人民共和国に移されました。これにより中華民国(台湾)は国連から排除され、現在は中華人民共和国が常任理事国の地位を有しています。
国際連盟と国際連合の共通点と違い
国際連盟と国際連合はいずれも、戦争の反省から生まれたという共通点を持っています。
ただし、その性格は大きく異なります。
国際連盟は「理想主義」の象徴であり、人類が初めて平和を制度として築こうとした試みでした。
一方の国際連合は「現実主義」に立ち、軍事力や政治力を背景に秩序を維持しようとする仕組みです。
しかし今、国際連合はかつての国際連盟と同じように、機能不全の危機に直面しています。
拒否権の濫用、大国偏重の構造、そして国際社会の分断。
100年前と同じ問題が、形を変えて再び現れているのです。
まとめ:本当に反省は生かされているのか
国際連合と国際連盟、この2つの覚え方としては、国際連盟は「第一次世界大戦の反省」、国際連合は「第二次世界大戦の反省」。
これだけでも十分に整理できます。
しかし、本当にその“反省”は生かされているのでしょうか。
国際連盟は理想に溺れて崩壊し、国際連合は現実に縛られて動けなくなっている。
そう考えると、両者は対照的でありながらも、どこか似た運命をたどっているようにも感じられます。
戦争から80年が過ぎた今、平和のための新しい国際協力のあり方が問われています。
100年前に掲げられた「世界平和」という理想を、私たちはもう一度見つめ直す必要があるのかもしれません。
最後までありがとうございました。