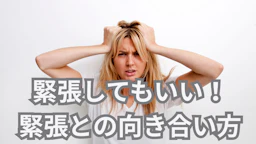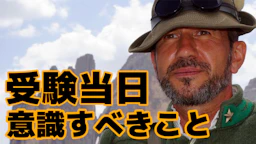「していい言い訳」と「してはいけない言い訳」
どうもフジです。
今回は「言い訳」について掘り下げていきます。
言い訳という言葉には、どうしても悪い印象がつきまといますよね。「逃げているだけ」「甘え」「言い訳するな」と言われてきた人も多いはずです。でも本当に、すべての言い訳が悪なのでしょうか?
私はそうは思いません。
むしろ、正しい場面で正しい言い訳を口にすることができる人こそ、長期的に自分を保ちながら、継続して努力できる人だと思っています。では、「どんな言い訳ならしてもいいのか?」「どんな言い訳はやめるべきなのか?」を整理していきましょう。
思考停止型の言い訳はNG!
言い訳の中には明確に「してはいけないもの」があります。ズバリ「自分の失敗を何となく納得して流してしまうタイプの言い訳」です。
たとえば「今日もあんまり勉強できなかったなぁ。学校から帰ってきてから結構ダラダラ過ごしちゃったし。まぁでも、ちょっと体調悪くて疲れてたからしょうがないか!」というような言葉。思考が止まっちゃってるのがわかりますかね。なぜダラダラしてしまったのか?どうすれば切り替えられたのか?今後どう改善していくか?そういった問いがまったく出てこないまま、「しょうがないよね」で終わってしまう。この瞬間、自分を守るために「考えること」をやめてしまっているわけです。
こうした言い訳を繰り返していると、自分にとって都合のいい“言い訳テンプレート”ができあがります。そして似たような失敗が起きるたびに、それを自動的に再生してしまう。これでは、成長が止まってしまうのも当然です。
だから私は、「反省も分析もなく、ただの安心感だけを得るための言い訳」は、明確に「してはいけない言い訳」だと考えています。
「なぜ失敗したのか」を言語化し、次の行動に活かせる言い訳はOK!
一方で「してもいい言い訳」も存在すると思っています。
その1つ目が「失敗の原因を具体的に言語化し、次に繋げるための言い訳」です。
たとえば、「今回の模試の数学、点数が思ったより取れなかったな。整数と場合の数、それから確率あたりは完全にノーマークだったからまあしょうがないか。とりあえずこの辺りの単元を重点的に見直してこうかな!」というような言葉です。
この言い訳がOKな理由は明確です。
失敗をあいまいにせず、「何が問題だったのか」「なぜそうなったのか」「次はどうすべきか」を具体的に考えているからです。ただ悔やむだけの言い訳ではなく、冷静な分析を含んだ言い訳。しかもその分析の先には、自分で次の打ち手まで見えている。これがまさに“してもいい言い訳”の典型です。
「やば、点数悪かった。まあ集中できなかったし、しゃーないな!」などのように、理由も改善案もなくその場をやり過ごすだけの言い訳はNG。こういう思考停止な言い訳で留めるのではなく、なぜ集中できなかったのか、何をどうすれば違う結果になったのか、そういった“考える習慣”をセットにしてあげると、言い訳は自分の成長に資する行為になるんです。
言い訳をすること自体が悪いのではなく、「思考を止めずに前に進めているか」が重要ってことですね。
全力を尽くしたのなら自分を守るための言い訳もOK
もう一つ、してもいい言い訳があります。
それが「限界まで努力したのにうまくいかなかったときに、自分のメンタルを守るために口にする言い訳」です。
これは、目に見える結果が伴わなかったときに、自分の中の“折れない芯”を保つための言葉。実際、私もこういう言い訳は数えきれないほどしてきました。
たとえば、高3のときの東大模試。死に物狂いで勉強して臨んだにもかかわらず、思うように点が取れなかったんですよね。そのとき私は「これはあくまで模試だからな、問題の質も悪けりゃ採点の質も悪いから、俺の実力が正当に評価されてないねん。点数は取れてないけど、俺は着実に前に進んでるぜ?」と、友人には言って回ってました。
これって、表面的には“めちゃくちゃな言い訳”に聞こえるかもしれません。でも私は、この言い訳を堂々と口にしてよかった、むしろそれは必要だったと思っています。模試後には原因分析も復習も徹底的にやっていたし、同じ問題が出たら二度と間違えないぞという気持ちで向き合っていた。裏ではすでに反省と改善が完了していた。そのうえで、自分のメンタルに傷をつけすぎないために、あえて“都合のいい解釈”を口にする必要があったんです。
こうした言い訳は、努力した人間にだけ許される“心の安全装置”です。人は常に現実と真正面からぶつかってばかりでは持ちません。ときには「まぁ今回は仕方なかったよな」と言い聞かせることが、次の努力へとつながるのです。だから私は「全力を尽くした人が、自分を守るために言い訳を口にすること」は肯定したいなあと思います。そういう言葉を口に出すことが次の一歩につながるなら、それは戦略的な回復手段だと思いませんか?
あ、大事なことなので念を押すように言っておきますが、このタイプの言い訳が許されるのはあくまでも、「本気でやることをやったうえで」「冷静な振り返りが済んでいる」ことが大前提ですよ。それがないまま、都合のいいことだけを口にしても、それはただの逃避になってしまいます。
言い訳を使いこなせ
ここまでの話を整理すると、してもいい言い訳には2パターンあります。1つは、失敗の原因を具体的に振り返り、改善策まで言語化できている「分析型の言い訳」。もう1つは、本気で努力し、反省も終えたうえで、心の安定を保つために自分を守る目的で口にする「メンタル防御型の言い訳」。どちらも、その背景に“本気の姿勢”と“次につなげる意思”があるという点で共通しています。
逆に、してはいけない言い訳は、「自分を安心させるだけで、なにも考えなくなる言い訳」です。「しょうがない」で終わってしまい、同じミスを繰り返すような言い訳は、今すぐやめた方がいいですね。
ちゃんと整理できましたか?
いやあほんと、私は、頑張っている人に「言い訳するな」なんて言うべきじゃないとしみじみ思いますね。むしろ、頑張っているからこそ、「してもいい言い訳」をきちんと選び、口に出してほしいです。正しく使えば、言い訳は“自分を甘やかす敵”ではなく、“自分を守る味方”になります。必要なのは、言い訳を恐れず、言い訳を使いこなすこと。それが、長く努力を続けるための大事な技術だと私は信じています。
というわけで今回は以上。