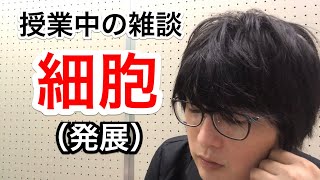炭素循環・温室効果・真核生物8系統群 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2021年7月26日
動画の長さ|10:09
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
炭素循環・温室効果・真核生物8系統群について解説します。
語呂「温かいお風呂に参加(温室効果ガス、オゾン、フロン、二酸化炭素)」
●関連するニュース
プレスリリース「植物プランクトンDicrateria rotundaが石油と同等の炭化水素を合成する能力をもつことを発見(2021.7.19 国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立大学法人豊橋技術科学大学、大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所)」
NHKなどが、ガソリンと同じ成分をつくる植物プランクトン発見と報じました。
(上記ニュースと高校で学ぶ生物とのつながりを中心に炭素循環・温室効果・真核生物ドメインについて解説しました。)
●オリーブ油、コーン油といった植物油は、非常に高い割合で『不飽和』脂肪酸を持っていて、一般に酸化されて劣化しやすく、長時間の保存には不向きであると考えられている。
JAMSTECのプレスリリースによれば、今回発見されたDicrateria rotunda (D. rotunda)北極海株ARC1は、炭素数10から38までの『飽和』炭化水素を合成するとされる。
合成される炭化水素の組成は、ガソリン(炭素数10から15)、ディーゼル油(炭素数16から20)、燃料油(炭素数21以上)と同等であるという。
●当たり前ですが、石油の上に直接工場を立てているわけではありません。ガソリン一つ取ってみても、市場に出るまで、原油の分留、加工などの作業があります。念のため。
●地球温暖化の原因については結論が出ていません。
●バイオ燃料は実用化されています。
●トウモロコシなどを燃料として使うことは、食料問題とも関係します。
●ホイタッカーはホイッタカーともいいます(資料集はホイッタカーが多いのですが、2021法政大入試、、2008静岡大入試、2020熊本大、動物の系統分類と進化[裳華房]にホイタッカーと記されていたのでこの動画ではホイタッカーとしました。)
●植物の成長に膨大な時間がかかることを考えれば、植物を燃やすことに何の問題もないわけではありません。当然ですが、念のため。
●現状では微量の石油しか得ることができません。今後生産効率を大きくする研究が進んでいくものと思います。
●脂肪酸は、β酸化により呼吸基質に使われる(β位の炭素を酸化し、まるで長い炭素鎖を短く切っていくようにして、アセチルCoAを次々に作り出し、呼吸に使う。発展生物ではβ酸化という語は問われる)。
●植物・菌・動物・原生生物という真核生物の分類は見直されつつある。真核生物は、現代では、塩基配列から、以下のような8グループに分類される。覚えなくてよい。( )の中は語源。
①アメーボゾア(アメーバ動物)
②エクスカバータ(細胞側面が凹んでいる excavated)
③アーケプラスチダ(古い色素体)・・・陸上植物はここに分類される。
④ハクロビア(ハプト藻とクリプト藻、ビアが生物を表す)
⑤アルベオラータ(細胞膜直下に機能不明の袋=アルべオールを持つ)
⑥ストラメノパイル(麦藁の毛=べん毛に生えている小毛)
⑦リザリア( rhizo=根)
⑧オピストコンタ(うしろのべん毛)・・・ヒトや菌類はここに分類される。
※ストラメノパイル、アルベオラータ、リザリアを、SAR(三つのグループの頭文字をとっている)としてまとめるという考え方もある。
0:00 生物学に関するニュース
0:17 炭素循環
5:19 温室効果
7:44 真核生物ドメインの8大グループ
#生物基礎
#温室効果
#炭素循環
#SDGs
関連動画
関連用語