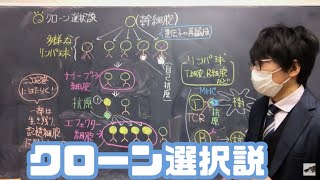島の生物地理学理論 高校生物基礎発展
概要
動画投稿日|2021年8月7日
動画の長さ|6:01
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
マッカーサーとウィルソンの島の生物地理学理論(島の平衡モデル)について説明します。
ポイントは以下の通りです。
1 島に存在する種の数は、大陸からの新たな種の移入・定着と、島にいる種のランダムな絶滅の平衡関係で決まる。島にすでに生物種がいるほど移入速度は小さくなり、絶滅速度は大きくなる。
2 島が小さいほど種の絶滅速度は大きい。
(動画ではその原因を個体群の減少と説明しているが、もちろん、環境の多様性の低下、競争的排除の増加、遺伝的多様性の低下、近交弱勢なども原因になり得る)
島が大きければ、個体群も大きくなるし、様々な環境が島内にあるので、絶滅を避けることができる。
3 大陸から遠い島ほど種の移入・定着速度は小さい。逆に近い島ほど大きい。
●黒板には書いていないが、一般に、
小さい島では移入速度が低くなること(たとえば、とても小さい島に植物の種が運ばれてきて、偶然その小さい島に落ちるのは稀である)、
近い島では消失速度が小さくなること(島で消失した種が陸から再侵入することがあるので)
も知られている。
●もちろん、このモデルでは、撹乱、進化的適応などの他の要因を無視している。
しかし、このモデルは、島でなくとも、島のように孤立した生息地に当てはまる。たとえば、我々人の影響で分断化された森林や公園などの環境が、どのくらい多くの種を保存できるかという、重要な予測を可能にする。
#高校生物
#島の平衡モデル
#生態系
関連動画
関連用語