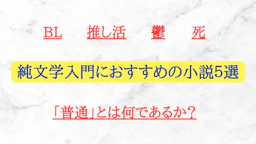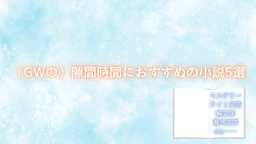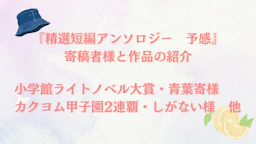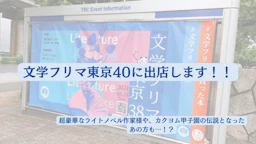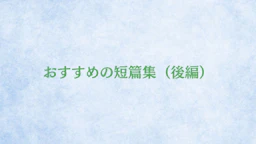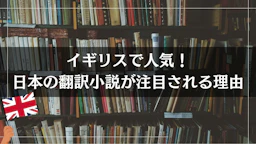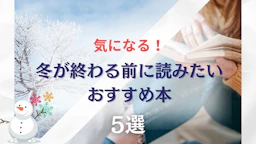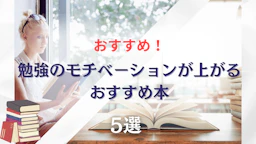こんにちは、Harunaです!
今回は「納得する!なぜ日本では”読書の秋”と言われるのか?」というタイトルでお届けします。
いつの間にか今年も残り4ヶ月となり、秋が到来しますね!
秋になると、「読書の秋」という言葉がよく聞かれますが、なぜこの季節が読書にふさわしいとされているのでしょうか?
今回の記事では、読書の秋の由来や日本における文化的背景について紹介するとともに、Harunaの秋におすすめしたい本をいくつかご紹介していきます!
それでは早速、見ていきましょう。
なるほど!“読書の秋”と言われる理由

読書の秋の由来
「読書の秋」という言葉は、日本の文化や習慣と深い関わりがあります。
その起源は平安時代までさかのぼり、平安時代の貴族たちは秋の夜長に物語を読み聞かせることを楽しんでいました。
この風習が、後に「秋は読書に適している。」という考え方につながったとされています。
また、読書の秋の背景には中国の古典「晋書」に記された一節が関係しています。
この一節には、「人が学問に励むのは秋が最も良い」という趣旨の内容が含まれていて、これが日本に伝わって秋に読書をすることが推奨されるようになったとも言われています。
秋と読書の文化的背景
日本では、四季折々の風情を楽しむ文化が根付いていて、秋は夏の暑さが和らいで涼しい風が心地よい季節です。
また、日が短くなることで自然と家の中で過ごす時間が増えて、読書に適した環境が整います。
このような季節の変化により、“秋は読書を楽しむのに最適な時期”として多くの人々に親しまれてきました。
さらに、秋は農作物の収穫期でもあり、心に余裕が生まれる季節でこの余裕が、知識を深めたり、教養を高めたりする時間を持つことに向かわせます。
そのため、古くから秋は学びの季節とも考えられてきました。
秋におすすめの本リスト
ここからは、Harunaが秋に読みたいおすすめ本をご紹介していきます!
1.『ノルウェイの森』村上春樹
・概要: 1960年代の日本を舞台に、青春と喪失をテーマにした物語です。
大学生の主人公が友人の死や複雑な人間関係に悩みながら、自分の生き方を模索していく姿が描かれています!
・おすすめポイント: 秋の夜に読むと主人公の孤独感や人生の選択について考えさせられる作品です。
村上春樹特有の感覚的な描写や繊細な心理描写が心に響いてきます!
2.『流れる星は生きている』林芙美子
・概要: 著者自身の経験をもとに、戦後の激動の時代を生き抜いた女性の姿を描いた自伝的な作品です。
戦争による混乱や貧困の中で生きる強さと、希望を持ち続けることの大切さが伝わってきます。
・おすすめポイント: 秋は、物思いにふける季節でもあります。
この作品を通して過去の歴史や人々の生き方を考えることで、自分の生活に新しい視点を持つことができます!
3.『銀河鉄道の夜』宮沢賢治
・概要: 不思議な列車に乗って、銀河を旅する少年の冒険を描いたファンタジー作品です。
夢と現実が交錯する世界観の中で、生と死、友情と孤独といったテーマが繊細に描かれています。
・おすすめポイント: 秋の澄んだ夜空を眺めながら読むとこの作品の幻想的な世界観が一層引き立ちます。
物語の中に込められたメッセージを自分なりに解釈しながら楽しむのも魅力です!
4.『告白』湊かなえ
・概要: 中学校で起きた事件を巡る教師と生徒たちの視点から描かれるサスペンス小説です。
次々と明かされる真実と、複雑に絡み合う人間関係がスリリングに展開されます。
・おすすめポイント: 肌寒い秋の夜、背筋がぞくっとするような緊張感を味わいたい方におすすめです。
物語の進行と共に心理的な緊迫感が高まって、最後まで目が離せない内容です!
最後に・まとめ
今回は「納得する!なぜ日本では”読書の秋”と言われるのか?」というタイトルでお届けしました。
季節の中で1番秋は、「〇〇の秋」と呼ばれることが多い季節ですが、それほど楽しみが詰まった季節であり、夏の暑さがなくなるため何事にも積極的に動きやすくなる季節でもあります!
是非、今年の秋はいつもと違うことに取り組んだり、新しいことにチャレンジしてみませんか??
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
また次回の記事でお会いしましょう!