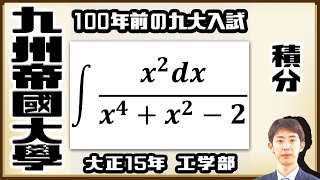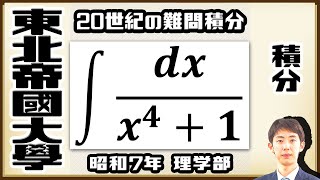【東北帝國大學】難問!有理関数の積分【戦前入試問題】
概要
動画投稿日|2021年5月14日
動画の長さ|24:06
【Amazon・書店等で好評発売中!】東京帝國大學入試問題が書籍になりました!
"100年前の東大入試数学 ディープすぎる難問・奇問100"
https://amzn.to/3d39zgN
東大入試のみですが,面白い問題を揃え,丁寧に解説しました。
ぜひご覧ください!
✅ 東大に合格したい受験生のための個別指導 (人数限定)
https://hayashishunsuke.com/lp/lecture-ut/
✅ 難関大受験生のための公式LINE:https://lin.ee/lI7n1SJ
登録者特典&受験生向けライブあり
🌟 出版社の方へ
https://hayashishunsuke.com/lp/for-publishers/
数学の書籍を執筆することに強い関心があります。
私に企画のご案内をしてくださる方は,上記ページをご覧ください。
※これまでの著作:”100年前の東大入試数学” (KADOKAWA)
ℹ️ 林俊介のプロフィール
https://hayashishunsuke.com/profile/
・栄東中→筑駒高→東大理一→東大物理学科卒
・東大二次の数学で 9 割獲得し現役合格
・2014年 日本物理オリンピック金賞
・2014年 東大実戦模試物理1位
ℹ️ ご注意いただきたいこと
・解説は林俊介独自のもので,大学公式のものではありません。
・書籍等の紹介には Amazon アソシエイトリンクを用います。
今回も,前々回・前回に引き続き東北帝國大學の入試問題です。
(a) (b) とは異なり三角関数は登場せず,普通の有理関数の積分になっています。
分母が因数分解された形になっているので,部分分数分解をするという発想に自然と至ると思うのですが,因数分解のパーツを揃えるのにまず一苦労です。
分母が 4 次式だったものをいくつかの分数にバラすので,分子は一般的に 3 次式になります。
その係数を揃えて 1 にするので,部分分数分解の際の条件式は
▶︎ 3 次の係数が 0
▶︎ 2 次の係数が 0
▶︎ 1 次の係数が 0
▶︎ 0 次の係数が 1
の 4 つとなり,ゆえに部分分数分解するパーツは 4 つ用意したいところです。
そして,もちろん各パーツは(手計算で)積分可能である必要があります。
こうした条件を踏まえると,分母の因数 2 つそれぞれについて
▶︎ log の微分
▶︎ arctan の微分
を考えれば,4 種類用意できるので,今回はこれらを利用しました。
用意した 4 つのパーツが独立であるかどうかの判定は簡単ではなく,今回は「なんとなく独立に見える」ものを揃えたというのが正直なところです。
部分分数分解ができ積分を実行できればよいので,パーツの用意自体を厳密にやる必要はない,というのが僕の考えです。
有理関数の部分分数分解,特に「どういう分数に分解すればよいか」いんついて,ご存知の方がいらしたらぜひコメントでお教えください!
----------
<目次>
00:00 昭和8年 (1933年) の東北帝國大入試
00:21 積分の方針:部分分数分解
01:34 分数は 4 つ用意する
07:14 分解後の係数を求める
09:24 各分数の積分
11:15 答えと解法のまとめ
15:22 類題:分数の調達
17:22 類題:係数の調整
18:37 類題:各分数の積分
20:13 類題:答えと解法のまとめ
21:30 複雑な有理関数の積分
23:37 おわりに
関連動画