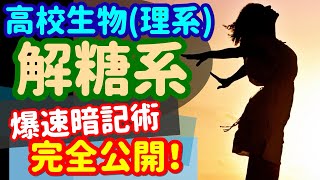解糖系【呼吸①】 高校生物
概要
動画投稿日|2015年7月3日
動画の長さ|4:30
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
解糖系について講義します。
語呂「瓶に書いとけ(ピル "ビン" 酸になるまでの過程が "解糖系" )」
クエン酸回路【呼吸②】の動画はこちら。 https://youtu.be/m3q8ONetpnA
脱水素酵素とNAD+についての動画はこちら。 https://youtu.be/mNWWHEt-QGw
●NADHは高エネルギー電子運搬体。生物はNADHやATPをエネルギーの運搬体として用いている。
●NAD+は脱水素酵素の補酵素。NAD+は、脱水素酵素から外れて、高エネルギーの電子を抱えたまま遠くへ移動することができる(呼吸では、運搬した高エネルギー電子のエネルギーは電子伝達系で使われる)。
●解糖系は細胞質基質で行われる。
問題:解糖系は( ? )で行われる。空欄を埋めよ。
答え:細胞質基質
●解糖系は、地球上のほぼ全ての生物に普遍的に存在し、エネルギーの産生を担う最も古典的かつ重要な代謝経路である。解糖系では、1分子のグルコースが2分子のピルビン酸に変換される。その過程で生じるエネルギーは2分子ずつのATPとNADHに蓄えられる。
●発酵を学ぶときは、「ATPの獲得」と「(反応を継続するための)NAD+の再生」という現象に注目することがポイント。
●解糖系の調節には、ATPとAMPが関わることが知られている。ATPは負のアロステリックエフェクターとして働く(ATPは、ホスホフルクトキナーゼ[解糖系の中で使われている酵素]の働きを抑制する。そうすることでATPの作りすぎ[基質の無駄遣い]を防ぐ)。また、逆に、AMPは正のエフェクターとして作用することが知られている。
●解糖系の反応を詳しく見ると、まず2ATPが消費され、その後、4ATPができる(差し引き2ATPが生成する)。はじめの2ATPを使う作業は、紙にマッチで火をつける作業に似ている。紙はそのままでは自然に燃え出すことはない。紙が二酸化炭素と水に変化するためには、「マッチの火[熱]というエネルギーの投入」が必要。解糖系の反応も同様で、グルコースをピルビン酸にまで分解し、4ATP分のエネルギーを取り出すために(活性化させ、反応を進ませるために)、まずは2ATPの投資(先行投資。後で4ATPのリターンがあるので、2ATP分の利益がある。有益な投資である)が必要。
●乳酸発酵と同様の反応は人の筋肉でも起こる(特に酸素の供給が間に合わないような状況でよく起こる)。その場合は、乳酸発酵とは言わず、『解糖(解糖系ではない!)』と言う(高校生物では、この、動物組織で起こる乳酸発酵と同様の反応[グルコース→乳酸]を解糖と呼び、今回の動画で説明した代謝経路[グルコース→ピルビン酸]を解糖系と呼ぶ。ただし、大学では、解糖glycolysisという用語は、解糖系glycolytic pathwayによるグルコースの分解を広く指して使うことが多い。そのうち高校の教科書が修正されるかもしれない)。
●乳酸発酵は以下の反応式で表される。
C6H12O6 → 2C3H6O3(乳酸) + エネルギー(2ATP)
(グルコースを真っ二つに割っているかような反応である)
●アルコール発酵は以下の反応式で表される。
C6H12O6 → 2C2H5OH(エタノール) + 2CO2 + エネルギー(2ATP)
●酵母菌は真核生物でありミトコンドリアをもつ。酵母菌細胞内では、酸素存在下でアルコール発酵が抑制される。この現象をパスツール効果という(グルコース1分子から得られるATPは、アルコール発酵では2分子である。呼吸では最大38分子である。呼吸を優先するのは当然である)。
●パスツールがパスツール効果を報告してから、呼吸の酸化的リン酸化の仕組みが解明されるまで、100年を要した。
●古代エジプトの『死者の書』(死者を来世に復活させるために遺体とともに埋葬委した呪文)に、すでにビールの作り方の記述がある。
●解糖系の詳細
*基本的に高校生は解糖系の詳細など暗記しなくてよい(過去に知識問題として解糖系の細かい反応が出題されている場合のみ注意すればよい)。
①まず、ATPが使われ、グルコースはグルコース6-リン酸になる(ここでのATPの投入は、後で見返りのある投資である)。
*リン酸基がくっついたグルコースは細胞膜を通れなくなるので、この反応によってグルコースを細胞内に閉じ込めることができる。
②グルコース6-リン酸はフルクトース6-リン酸に変換される。
③ATPが使われ、フルクトース6-リン酸はフルクトース1,6-ビスリン酸になる(ATPの投入は、後で見返りのある投資である。また、この反応を触媒する酵素ホスホフルクトキナーゼは、ATPやADPなどの分子によって、アロステリック的に活性が調節されている[ATPによって働きが阻害され、ADPによって活性化される。つまり、丁度うまい具合に、ATPが足りずADPが多いなら解糖系を推し進める方向に、ATPが過剰なら解糖系を止める方向に調節されている]。この反応③は、代謝的に不可逆であり、解糖の重要な調節点となっている)。
④フルクトース1,6-ビスリン酸は分解され、2個のグリセルアルデヒド3-リン酸が生じる(実際は、フルクトース1,6-ビスリン酸はジヒドロキシアセトンリン酸とグリセルアルデヒド3-リン酸になるが、ジヒドロキシアセトンリン酸は異性化してグリセルアルデヒド3-リン酸になる)。
*これ以降、1分子のグリセルアルデヒド3-リン酸の運命を見ていくが、実際は⓸でグリセルアルデヒド3-リン酸は2分子生じていることに注意(グルコース1分子あたりを考える場合は、これ以降、分子数を2倍にして考えなければならない)。
*これ以降、エネルギーの生成過程に入る(投資した2ATP以上のリターンを得ていく)。
⑤グリセルアルデヒド3-リン酸は脱水素される。また、リン酸化される。結果、1,3-ビスホスホグリセリン酸が生じる。
(グルコース1分子あたりで考えれば2NADH生成)
⑥1,3-ビスホスホグリセリン酸が3-ホスホグリセリン酸となる。この時ATPが生成する。
(グルコース1分子あたりで考えれば2ATPが生成される)
⑤3-ホスホグリセリン酸はピルビン酸になっていく。その間にATPが生成される(3-ホスホグリセリン酸は2-ホスホグリセリン酸になり、2-ホスホグリセリン酸はホスホエノールピルビン酸になる。そしてホスホエノールピルビン酸がピルビン酸になる時、ATPが生成される)。
(グルコース1分子あたりで考えれば2ATPが生成される)
*解糖系のATP生成のように、ATP合成酵素を用いずに(つまり酸化的リン酸化や光リン酸化とは異なる仕組みによって)ATPを生成することを「基質レベルのリン酸化」という。
#解糖系
#呼吸
#高校生物
関連動画