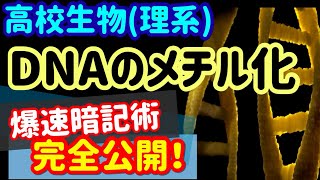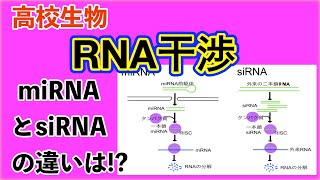RNA干渉(RNAi)・CRISPR系 高校生物発展
概要
動画投稿日|2022年1月7日
動画の長さ|7:31
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
RNA干渉とCRISPRについて解説します。
問題:以下の文章の空欄を、この動画中に使われていた用語を使って埋めよ。ただし、①は「ダ」から、②は「ア」からはじまる用語である。
「真核生物において、RNA干渉は、ウイルスなどのつくる2本鎖RNAの撃退にも使われている。細胞内にウイルス由来の2本鎖RNAが存在すると、(①)が引き寄せられ、2本鎖RNAを切断する。そうしてできた短いRNA断片をsiRNAという。その後、siRNAが(②)などのタンパク質と結合し、RISCが形成される。RISCは、siRNAのガイドによって、ウイルス由来の2本鎖RNAに導かれ、(②)がこれを切断・破壊する。このように、細胞はウイルス由来の2本鎖RNAをRNA干渉のしくみを使って破壊している。」
答え:①ダイサー ②アルゴノート
*ウイルスの生活環の中で、一時的に2本鎖RNAが生じることが多い。
*RNA干渉は、もともと、実験的に二本鎖RNAを導入し、相補的mRNAの配列特異的な分解を引き起こす機構を指す語であった。しかし、近年では、RNA干渉の語は、細胞自身のゲノムにコードされているmiRNA(マイクロRNA[microRNA])による遺伝子発現阻害を含めた意味でよく使われている。むしろ、二本鎖RNAの導入が、miRNAによる遺伝子発現調節(RNA干渉)を惹起したと捉えるのが普通である。
*アルゴノートとは、もともとは、ギリシャ神話において黄金の羊毛を探しに出航したアルゴ船の船員のこと。
●RNA干渉(RNAiと略記):二本鎖RNAによって配列特異的にmRNAが分解される、あるいは翻訳が抑制される結果、遺伝子発現が抑制される現象。真核生物に広く見られる。
●CRISPR(くりすぱー)系:細菌が短い非翻訳RNA分子を用いて行う防御機構。外来ウイルスゲノムを探し、破壊する(ウイルスが細菌に感染すると、細菌は、ウイルスDNA断片を自身のゲノムに組み込む。組み込まれたDNAを鋳型として作られたRNAが、再度侵入してきたウイルスの破壊に働く)。細菌のCRISPR系を用いた免疫についてはまだわかっていないことが多いが、この現象を利用して、DNA上の好きな配列を切断する技術が発明された(ゲノム編集)。
●ヒトでは、タンパク質をコードする遺伝子の50%近くが、RNAによる発現調節を受けているとも言われている。
●動画のようなRNA干渉で用いられる短いRNA鎖をmiRNA(マイクロRNA[microRNA])という。このほかにも、siRNA(低分子干渉RNA)というRNAがガイド役として使われることもある。
●siRNAはmRNAの選択的分解の誘導により翻訳を阻害したり、クロマチン構造の凝集によって転写を抑制したりする。
●miRNAとsiRNAは、その前駆体により区別される。miRNAが前駆体RNAのヘアピン構造の1つから生成されるのに対して、siRNAはもっと長い二本鎖RNAから多数生じることがわかっている(たまに、miRNAとsiRNAの違いを「自然に細胞で生じるのがmiRNAで、ウイルスに由来する外来二本鎖RNAから生じるのがsiRNA」とする説明があるが、正確ではなく、siRNAには内在性のものもある。siRNAの作られ方は、主に次の3種類がある。いずれも二本鎖RNAができてから、それらがダイサーにより切断されることでsiRNAが生じる。1つ目は、DNAのある領域で逆方向にRNAが転写されるもので、生じたRNAが結合して2本鎖になる。2つ目は、それぞれの鎖に重複した配列があり、それを逆向きに転写するもので、やはり転写産物が結合して2本鎖になる。また、回文配列から転写産物が生じると、1本のRNA内で塩基対形成が成され、部分的に二本鎖のRNAができる。3つ目は、ウイルスや転移因子によって細胞内に二本鎖RNAが生じる場合である。いずれにしろ、高校生はまったく覚える必要はない)。このように、siRNAはクロマチンの再編にも関わっていると考えられている。
●ある種の酵母では、酵母自身が生産するsiRNAが、動原体のヘテロクロマチン(高度に凝縮されている)の形成に必要であることが分かっている。
●さらに、生殖系列の細胞で特異的に作られるpiRNAもある(トランスポゾン遺伝子を転写レベルで抑制することで、生殖系列の細胞を守っていると考えられている)。
●多くの植物では、miRNAと標的mRNAは広域で結合し、アルゴノートがmRNAを切断することで急速なmRNA分解を促している。
●多くの哺乳類では、miRNAは標的mRNAと狭い領域のみで結合し、急速に翻訳を抑制させている。この場合も、mRNAはやがて分解される(mRNAは不安定になり、P―体[P-body。細胞質にある粒子様の構造で、RNA代謝の場となっている]に移行して、やがて分解される)。
●ゼブラフィッシュでは、母性mRNAの排除にmiRNAが関わっていることがわかっている(母性因子の一斉処分)。
●RNA干渉は、ウイルスなどの外来DNAや、トランスポゾン(移動する遺伝子)に対する防御機構だったようである。今では、正常な発生を含め、様々な生命現象に関わっている。
●動画中の図では省略しているが、細菌のDNAは環状である。念のため。
●miRNAやsiRNAなど、タンパク質をコードしていないRNAをncRNA(ノンコーディングRNA)という。
●RISCは、RNA-induced silencing complex(RNA誘導サイレンシング複合体)の略。RISCを形成したmiRNAは、標的mRNAの非翻訳領域に結合し、mRNAのポリAテールの分解と、それによるmRNAの分解を促進したり、mRNAのキャップ構造と相互作用して翻訳開始を阻害したりすると考えられている。
●miRNAなどによるRNA干渉とCRISPR系は似ているが、決定的に異なる点が2つある。
①RNA干渉では主に1本鎖RNAが標的だが、CRISPR系は2本鎖DNAが標的である。
②RNA干渉とは異なり、CRISPR系では、遺伝情報のCRISPR座位への取り込みが起こる。
●ゲノム編集には、よくCRISPR/Cas9系(クリスパーキャスナインけい)が使われる。動画で見たように、この系を用いて決まった位置でDNAの2本鎖を切断させる。それで遺伝子を壊すこともできるし、少し難しいが、遺伝子をノックインすることもできる。DNAを切断された細胞は、その修復に、われわれが導入した遺伝子断片を使うことが多い。細胞は、壊れた(切られた)領域の修復に、我々が注入したDNA断片を参照するのである。結果、狙った位置に、我々が導入した遺伝子が組み込まれることになる。この組み込みの仕組みを、相同組換えという。
●RNA干渉とCRISPR系は似ている所があるが、進化的なつながりは完全には明らかになっていない。真核生物のRNA干渉の起源は、CRISPR系に似た免疫システム(核酸を用いた、細胞を守る免疫システム)である可能性がある。
●RNA干渉を発見したアンドリュー・ファイアーとクレイグ・メローは2006年に、miRNAを発見したビクター・アンブロスとゲイリー・ラブカンは2024年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞している。
0:00 RNA干渉
0:17 遺伝子発現の調節
1:05 RNA干渉(登場する物質の紹介)
1:50 RNA干渉(詳細)
3:07 CRISPR系
6:18 CRISPR系の利用
#RNAi
#RNA干渉
#CRISPR
#高校生物
#生物学
関連動画