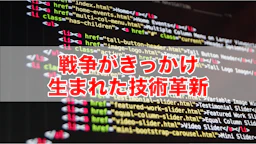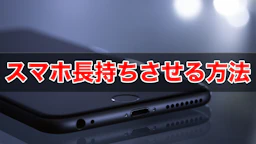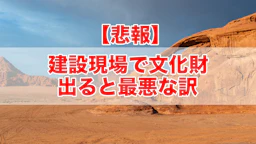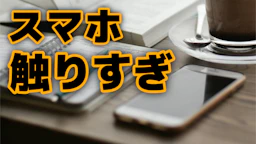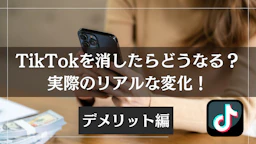今や皆さんの生活に欠かせない存在になったスマートフォン。
そんなスマートフォン、実はどのような由来があって、どのような歴史があったのか、皆さんはご存知でしょうか?
今回はスマートフォンの由来と歴史についてご紹介していきます。
名前の由来
そもそも「スマートフォン」という名前の由来は、英語の「Smart(賢い、多機能、洗練された)」+「Phone(電話)」。
つまり「賢い携帯電話」という意味になります。ただし“賢い”というだけではなく、“多機能で便利な小型コンピューター”という意味合いも込められています。
では「スマホ」という言葉はどこから来たのでしょうか?
実はスマホという言葉は日本のマスメディアや広告によって作られた略語なのです。
マスメディアや広告が積極的に「スマートフォンをスマホ」と略した結果、日本ではスマホとして一気に定着しました。実際、海外では「スマホ」という略称は使われず、“Smartphone”が一般的です。
iPhone以前のスマートフォン
世界初のスマートフォンといえば「iPhone」というイメージを持つ人が多いですが、実はiPhone以前にもスマートフォンの原型は存在していました。
- IBM Simon(1994年)
世界初のスマートフォンと呼ばれる端末。タッチパネルを搭載し、電話やアドレス帳、スケジュール帳、電卓などを備えていました。ただし見た目は分厚く、現代のスマホとは大きく異なります。
- Nokia Communicator(1996年)
横に開くとキーボードが出てくる折りたたみ型のスマートフォン。ビジネスマン向けで「携帯できるパソコン」として人気を博しました。
その後もBlackBerryやPalmなど、いくつかの機種が登場しましたが、基本的には仕事やビジネス向けで一般の人が使うものではありませんでした。
そして私たちが知っているような「全面タッチパネルで直感的に操作できるスマホ」は、まだ存在していなかったのです。
iPhoneと名前の意味
そして2007年、初代iPhoneが登場します。これが今のスマホの見た目を決定づけました。
またネーミングの効果も非常に大きかったといわれています。
実はiPhoneは、当時のパソコンに近い機能を持ちながらも、「Phone(電話)」という分かりやすい言葉を名前に入れました。
もし「iComputer」や「iPC」という名前だったら、一般の人には馴染みにくかったでしょう。ですがあえて「iPhone」とすることで「自分にも使えるものだ」と思わせ、広がりやすくしたのです。ネーミングの効果も非常に大きかったといわれています。
iPhone 3Gが広げた世界
2008年に登場した「iPhone 3G」は、日本でのスマホ普及を一気に進めました。
- 当時最速だった3G通信に対応
- ソフトバンクが独占販売し、テレビCMで大々的に宣伝
- App Storeが始まり「アプリを入れて機能を増やす」という革命
- 直感的なタッチ操作で、説明書がなくても誰でも使えた点
これらの要素によって、この「iPhone 3G」こそ、日本においてスマートフォンが“生活必需品”として一気に広まるきっかけとなったのです。

(私たちの生活に欠かせない存在となったスマートフォン)
現在のスマートフォン
現在のスマホは、もはや「電話」ではありません。
SNSや動画、音楽、ゲーム、キャッシュレス決済、健康管理、学習まで、生活のほぼすべてを担っています。
特にカメラ機能の進化は驚異的です。
iPhone 13シリーズ以降に搭載された「シネマティックモード」は映画撮影にも使われています。
また今年世界的な大ヒットを記録したApple Original Filmsが製作に参画した映画「F1/エフワン」では、実際にiPhoneのカメラの一部がF1風マシンの車載カメラとして利用されました。
私自身も記事を書くために写真をよく撮りますが、長距離撮影以外では高額なカメラと変わらないクオリティで、しかも簡単に使える点で重宝しています。
今やスマホは“電話ができるカメラ付きPC”であり、日常のすべてを支える存在となっているのです。

(iPhoneで撮影した画像を参考までに。被写体との距離によっては高額カメラと大差がないことがわかると思う)
最後に
スマートフォンというものは、iPhoneの登場によって一気に普及しましたが、実はiPhone以前にも「スマートフォン」という名前の製品は存在していました。そして現在では、スマートフォンは生活に欠かせないツールとなっています。
皆さんも日々スマートフォンを使っていると思いますが、ぜひお持ちのスマートフォンに搭載されている最新機能に触れてテクノロジーの進化を体験してみてください。
最後までありがとうございました。