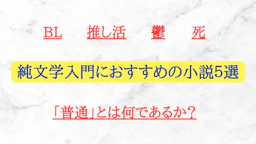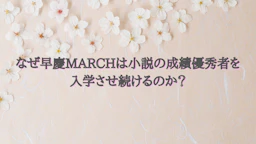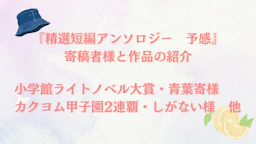春の予感は誤魔化せない
履きなれていない黒のローファーがぎごちない。数日前に採寸をしたときはちょうどよかったのに、足の指の先を曲げながら前へ進めてみると、踵に少しの隙間が覗いた。それに、歩く度に足の裏に地面が吸い付いてくるような質感がある。硬さが和らぐといいなと思って、昨日家の近くの河川敷を散歩してみたのだけれど、効果はなかったみたいだ。
それでも私はこの歩きにくいローファーの感触を気に入った。中学校まではスニーカーで登校していたから、暗い色彩の靴下と、黒の革靴が織りなす階調に、密かに憧れていたのだ。スポーツブランドのロゴが入ったスニーカーではどうしてもカジュアルになってしまう。勿論それはそれで可愛い。でも、ブレザーを羽織ってローファーを合わせるこの制服こそ、私が求めていたものなのだと、今朝、姿見を前にして確信した。
道路沿いには桜が咲いている。淡い桃色の花びらを目一杯につけた桜並木が、新入生の入学を盛大に祝福していた。家を出る前、唇に仄かに薄紅色を滑らせたのを思い出す。
「ねえ、ここいいんじゃない? 桜が道のほうに出ていて、とっても映えそうよ。一枚撮っておかない?」
お母さんが携帯を片手に、桜を見上げて立ち止まった。
たしかにその桜は他のものより背が低くて、身長の低い私を撮るなら相性が良さそうだった。引いて撮影すれば桜の背丈など関係ないのだが、そうすると後ろを通り過ぎていく他の新入生が映りこむ可能性があったのだ。
私は目立つことを危惧してあまり乗り気でなかったのだけれど、そんな私など一切考慮せずにお母さんが上機嫌にカメラを構えるので、仕方なくシャッターを切られる他なかった。
我ながらよく笑えていたと思う。新たな芽吹きを秘める高校一年生らしい、希望に満ちた微笑みを意識した。
それからしばらく歩くと正門に辿り着いた。高校の名称の後に入学式と記された立て看板があった。柔らかく開花した、その合間を縫って差す朝の光が、華やかな花を隅に飾った看板を晴れ晴れしく照らし出していた。
一生に一度の入学式。親子によって、撮影のための列ができている。友だちと並んで撮っている生徒も見受けられて、知り合いのいない私はきゅっと心が細まった。
実はこの高校は、第一志望で受験した高校ではなく、滑り止めの私立高校だった。地元にある公立高校を目指していた私は、あっけなく試験に落ちた。当日は急な腹痛に襲われたのだが、それを今になって言い訳にしても仕方がない。結果として、住んでいる県の隣県に立つ私立高校にはるばる入学することになったのである。
首元の青いリボンが慣れない。綺麗につけてきたはずなのに、変な方向にねじ曲がっている気がする。感覚で真っ直ぐを向くように整えながら門の先を進んでいくと、ちょうど、生徒用玄関の前にも同じ看板が立てられていた。そこは正門に比べて人が少なく、順番を待っていればすぐに撮影ができそうだった。私たちは前の一組の親子の後ろに並ぶことにした。
私の視線は、校内の廊下に敷かれた臙脂色の絨毯に釘付けになる。折れることも歪むこともなく、永遠と続く慶賀の色。私は、恐らく体育館へと導いてくれるだろうあの道を、後に歩むことになる。所々に跡がついて、部分的に異なった色を滲ませているのが綺麗だ。
順番が、私たちの前の組に巡ってきた。紺に染まったネクタイを締め、長く伸びたスラックスに脚を包んだ男の子と、そのお母さんらしき女性の二人だった。
写真を撮り終えた親子が完全に看板を離れたのを確認してから、彼は右足を前へ踏み出した。
そのときだった。
彼が歩き始めた拍子に、スラックスのポケットから薄水色のハンカチがひらりと宙を彷徨って舞い落ちた。幸い、コンクリートは特に汚れてはいなかった。濡れたり変色したりすることはない。
しかし、彼は気づかずに看板へ向かってしまう。
私は屈んで、ハンカチを拾うと同時に声を上げた。
「あのっ──」
彼は三段ある小さな階段の一段目に置いていた足を下ろして、私を振り返った。
僅かに見開いた彼の目が私を捉えて、そのまま私たちは見つめ合った。
捕まった。透明な光を透かした彼の瞳は、私を見つめて離さなかった。その煌めいた瞳をこちらへ向けたまま、彼は言葉を発さず、どうしたの、と目で疑問を投げかけてくる。頭一つ分下の私を見下ろしながら。
口が塞がったまま、掛けるべき声が出てこない。拾ったハンカチを返すだけ。焦る必要なんて微塵もない、簡単な行為であるはずなのに。
「あら、おともだち? 待ち合わせてたならお母さんに言いなさいよ、もう。ほら、二人で撮ってあげるわ。ならんでならんで」
逡巡していた私を勘違いしたのか、お母さんは私の背中を軽く押し、看板のほうへと向かわせた。
想定外の事態だ。
否定しようと試みたけれど、思うように口が動かない。
彼は彼の母親のほうにちらりと視線を流し、微笑ましそうに見ているその姿に何も言えなくなったのか、戸惑いながらも私の隣に立ってくれた。
もう後には引き返せない。私は彼のハンカチを一旦しまった。
ぎこちないわねぇ、とお母さんは私の作り笑顔に納得のいかない様子を示す。道の脇で撮った写真との落差が原因かもしれない。
私の時間はまだ、彼に捕まったまま止まっていた。
純真で、湖に映し出された陽光のように澄んだ、清らかな彼の瞳。
繊細な睫毛が揺れ、無垢な疑問を宿しながら瞼が開閉したとき、私は感じたのだ。
私の知らない内側が、たしかに春色で満たされていくのを。
ああ、シャッターが切られてしまう。横は見れない。彼の表情はわからない。
撮らないでと願う。誤魔化しのきかない温かさが胸の中からじんわりと拡がっていく。頬が僅かに染まっているのを自覚する。
十分にも一時間にも思えたその瞬間が過ぎ去り、強ばっていた身体から力が抜けた。
うんうんいい感じよ、とお母さんは満足そうに携帯に夢中だ。彼の母親にも見せに行き、二人で写真について何かを話している。よく撮れていますね。いえいえ、ありがとうございます。そんなところだろうか。
彼も息を吐いて、親でも私でもない門のほうを見つめる。
「ごめん、巻き込んじゃって」
謝るべきだと思った。いきなり、知らない家庭の記念撮影に巻き込んだことを。
ああ、と彼は呟いて、私のほうへ顔を向けた。
「大丈夫。ありがとう」
彼は口角を上げて微笑んだ。その柔和な目が優しく細まり、私は身体の底から何かが焦がれるのを悟った。
まだ彼に伝えなければいけないことがある。私はポケットの中に手を忍ばせて、雲一つない空を切り取ったような一寸の澱みもないハンカチを取り出した。
「これ、さっき落としてた」
私が差し出すと、彼は驚いたように目を瞬いて、スラックスのポケットに手を突っ込んだ。当然、宙を掴んだその手は元通りに帰ってくる。
「気づかなかったよ。ありがとう」
そう言って、彼の骨張った指が私のほうへと伸びてくる。
ハンカチを受け取るために近づいた彼の人差し指の、その先端が、私の人差し指に触れた。彼は一切動揺せずに、ハンカチを掴み、平然と指を戻した。
その瞬間の、二人の手の上に作られた春の陽射しの模様。移ろった肌の温もり。溢れる鼓動の音。
私は忘れないだろう。
.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)