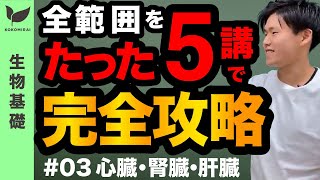血液凝固反応とその阻止 高校生物基礎
概要
動画投稿日|2021年9月30日
動画の長さ|9:53
*豚の血液を使った実験はこちら(血液が苦手な人は見ないでください。おすすめに出ないように限定公開にしてあります)。
①静脈血と動脈血の観察
https://youtu.be/4kjIK1fOojs
②血球と血しょうの分離・血液凝固反応の阻止
https://youtu.be/6mm_J0VtLsU
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
*高校では、血小板に由来する因子を「血液凝固因子(凝固因子)」と呼ぶことも多い(板書では血小板因子としている)。テストでは学校の教材の解釈に合わせること(ただ、生理学では、ふつう凝固因子と言ったら、第Ⅰ因子~第XⅢ因子などの因子を指す。血小板固有の因子[血小板膜リン脂質と血小板中のα顆粒に含まれる特有のタンパク質]は、ふつう、血小板因子と呼ばれる)。
問題:血ぺいは( ① )が( ② )という繊維状のタンパク質にからめとられたものである。空欄を埋めよ。
答え:①血球 ②フィブリン
●血液は酸素(ヘモグロビンに結合)や栄養分(血しょうに含まれる)を運ぶので、血液の流出は命にかかわる。
●血管が傷つくと傷口に血小板が集まって傷口をふさぐとともに、血小板から血液凝固に関わる因子(血小板因子。凝固因子と呼ばれることも多い)が血しょう中に放出される。すると、それらの因子などの働きによって、フィブリノーゲンから繊維状のフィブリンが形成される。
●フィブリンが血球を絡め取り、血ぺいが形成される。血ぺいによって傷口がふさがれるので出血が止まる
●血液凝固を防ぐには、①棒でフィブリンを絡め取る、②ヘパリンやヒルジンによるトロンビンの機能の阻害、③クエン酸ナトリウムによるCa2+の除去などの方法がある。
*ヘパリンは、血管内での血栓形成の阻止に使われている。ヘパリンは肝臓にもともと存在する血液凝固阻止物質として得られるが、医薬品として工業生産されている。ヒルジンは、医用ヒルの唾液腺中に含まれているポリペプチド。ヒルは、吸血と同時に、抗凝血作用を持つヒルジンを分泌する。ヒルジンの作用により、吸血後十数時間ゆっくりと出血が持続する。
●血液凝固反応とは逆に、固まった血液が溶ける反応を線溶(せんよう)という。
●血ぺいは血液を静かに放置することでも観察することが出来る。血液を放置すると、血ぺいと、液体成分の血清(=うす黄色。血清の中には抗体が含まれることから、血清療法に使われる)とに分離する。
*フィブリン(血球をからめとって血ぺいを生じさせるタンパク質)はフィブリノーゲンという物質からつくられる。つまり、血清は、血しょうからフィブリノーゲンを除いた物にほぼ等しい。
*血液凝固反応の詳細
①損傷した組織から放出されるトロンボプラスチン(反応開始の引き金である)という血液凝固因子と、血小板から放出される血小板因子が、複雑な反応を経て、プロトロンビンをトロンビン(酵素の一種)にする。
②トロンビンはフィブリノーゲンをフィブリンに変える(ここまでの反応にはCa2+が必要である)。
③フィブリンは血球をからめとり、血ぺいにする。
*なお、実際は、血液凝固反応はもっと複雑な反応であり、他にも多数の凝固因子が関わる。多くのステップで、Ca2+が必要になる。
*以下に血液凝固因子を記すが、高校生は覚えなくてよい(発見順にローマ数字が振られている)。
第Ⅰ因子:フィブリノーゲン
第Ⅱ因子:プロトロンビン
第Ⅲ因子:組織トロンボプラスチン
第Ⅳ因子:Ca2+
第Ⅴ因子:不安定因子
第Ⅵ因子は欠番。現在用いられていない。
第Ⅶ因子:安定因子
第Ⅷ因子:抗血友病因子
第Ⅸ因子:クリスマス因子
第Ⅹ因子:Stuart因子
第Ⅺ因子:血しょうトロンボプラスチン前駆物質
第Ⅻ因子:ハーゲマン因子
第XⅢ因子:フィブリン安定化因子
●フィブリノーゲンの語尾「-gen」は、「源」という意味。つまりフィブリノーゲンはフィブリンの源という意味。
グリコーゲンがグルコースの源であるのとネーミング規則は同じ。
●タンパク質の語尾はinになっていることが多い。繊維状のタンパク質であるフィブリンもその例。
その他、インスリンやケラチンやクリスタリンやアクチンやミオシンやキネシンなど。みんな語尾がinになっている。
●血餅はゼリーみたいに見える。血清は、その生物が作った抗体を含んでいるので、ウサギなどの血清が血清療法に使われたりする。
●損傷した組織から放出されるトロンボプラスチンは、分子量約45000の糖タンパク質である。
●血栓はthrombusと言う。トロンビン等の語源である。
●血小板因子には、血小板膜リン脂質のほか、血小板に特有に存在するタンパク質がある。
*血小板因子は、当初、第1因子~第9因子まで提唱されたが、その後、多くのものが整理され、第3因子(血小板膜リン脂質)と第4因子(血小板特有のタンパク質)だけがその名を残している。
●プラスミンという糖蛋白が、フィブリンを溶かし、血栓を溶解する現象を線溶(せんよう)という。この線溶の勢いと、血液凝固を進めようとする勢いが、常に働きあっている。優勢な方に現象が進む。
●どうして血液凝固因子が放出された後、関係ない様々な場所で血液凝固が起こらないのだろうか。いくつか理由はあるが、最もシンプルな理由は、血液に流れて因子が薄まるからである。
●実際は、血液凝固反応のルートには、損傷した組織からトロンボプラスチンが放出して始まる反応ルートと、破れた血管のコラーゲン等がきっかけになって始まる反応ルートがある。大学ではこの二つのルートをそれぞれ学ぶ。
0:00 血液凝固反応
5:07 血液凝固反応の阻止
#恒常性
#生物基礎
#血液凝固
関連動画
関連用語