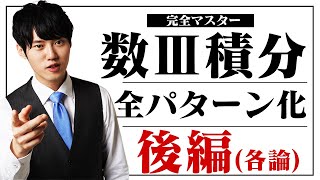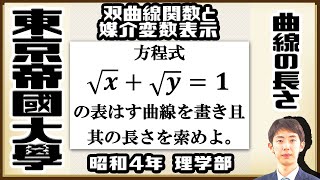【京都帝國大學】放物線の長さは?【戦前入試問題】
概要
動画投稿日|2021年5月2日
動画の長さ|25:46
【Amazon・書店等で好評発売中!】東京帝國大學入試問題が書籍になりました!
"100年前の東大入試数学 ディープすぎる難問・奇問100"
https://amzn.to/3d39zgN
東大入試のみですが,面白い問題を揃え,丁寧に解説しました。
ぜひご覧ください!
✅ 東大に合格したい受験生のための個別指導 (人数限定)
https://hayashishunsuke.com/lp/lecture-ut/
✅ 難関大受験生のための公式LINE:https://lin.ee/lI7n1SJ
登録者特典&受験生向けライブあり
🌟 出版社の方へ
https://hayashishunsuke.com/lp/for-publishers/
数学の書籍を執筆することに強い関心があります。
私に企画のご案内をしてくださる方は,上記ページをご覧ください。
※これまでの著作:”100年前の東大入試数学” (KADOKAWA)
ℹ️ 林俊介のプロフィール
https://hayashishunsuke.com/profile/
・栄東中→筑駒高→東大理一→東大物理学科卒
・東大二次の数学で 9 割獲得し現役合格
・2014年 日本物理オリンピック金賞
・2014年 東大実戦模試物理1位
ℹ️ ご注意いただきたいこと
・解説は林俊介独自のもので,大学公式のものではありません。
・書籍等の紹介には Amazon アソシエイトリンクを用います。
今回も前回に引き続き,大正14年の京都帝國大學工学部の入試問題。
放物線 y^2 = 4ax の頂点から点 (a, 2a) までの長さを計算していきます。
latus-rectum というのは,今回の場合点 (a, 2a), (a, -2a) を結ぶ線分のことをいいます。
動画内では日本語訳がよくわからないとお伝えしましたが,「通径」(つうけい)と呼ばれるようです。
普段あまり使わない言葉ですね。
曲線の長さの公式を用いて計算するのですが,見た目以上に面倒な積分になります。
難しめの積分の定番問題ですね。
今回は,代表的な計算方法を 2 つご紹介します。
どちらも使えるようにしておくことをおすすめします!
----------
<目次>
00:00 大正14年 (1925年) の京大入試
00:23 単語の意味&問われている長さ
04:18 曲線の長さの計算公式
05:28 公式を今回の曲線に適用
06:28 変数変換して見た目を簡単にする
09:04 積分方法 ① tanθ を利用
17:21 積分方法 ② sinh(t) を利用
24:16 解法のまとめ&アドバイス
25:16 おわりに
関連動画