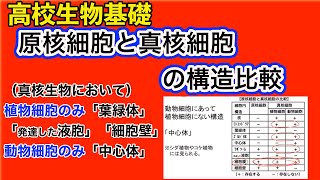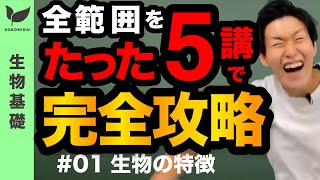植物細胞【細胞②】 高校生物
概要
動画投稿日|2015年9月6日
動画の長さ|3:31
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】
植物細胞についてわかりやすく講義します。
語呂「駅の方は案外シーンとしてるでちょ?(液胞、アントシアン、浸透圧調節、貯蔵)」
語呂「セールで買うから平気!(セルロースが主成分の細胞壁)」
●葉緑体
構造:2 枚の膜で包まれている(二重膜構造)。光合成色素(クロロフィルなど)が存在する。DNA (環状)を含む。
はたらき:光合成によって有機物を合成。
●植物細胞には、葉緑体以外の色素体(プラスチド)が見られる場合がある。色素体は、植物細胞に含まれる葉緑体、アミロプラスト、有色体、白色体などの細胞小器官の総称である。色素体は、葉緑体およびその変形と見なされている。
*アミロプラスト:貯蔵組織に存在し、大量のデンプンを蓄積する。
*有色体:大量のカロテノイドを蓄積する。トウガラシや、トマトの果皮、ニンジンの根などに見られる。
*白色体:色素を含まない。茎や胚乳、白い花弁や根などに存在する。ほとんど無色で顕著な特徴もない。
●液胞
構造:液胞膜が細胞液を包んでいる。細胞液には有機物、無機塩類、色素(アントシアン)などが溶けている。動物細胞にも存在するが、成長した植物細胞でよく発達している(大きくなっている)。
はたらき:老廃物の貯蔵、浸透圧調節。
語呂「駅の方は案外し~んとしてるでちょ?(液胞、アントシアン、浸透圧調節、貯蔵)」
*成長した植物細胞では液胞は非常に大きく発達し、核などは隅っこに追いやられてしまう。
*アントシアンはほとんどすべての植物の赤色・紫色を発色している色素であり、これは、動物を引き寄せたりするのに使われると考えられている。日本の紅葉現象の美しさは世界的に有名であるが、紅葉にはアントシアンが含まれている(紅葉には、最も単純なアントシアンの一つであるクリサンテミンが含まれている。クリサンテミンは水溶性で、葉肉細胞の液胞中に溶けている)。
●原形質連絡(
植物細胞は、隣の細胞と原形質連絡(植物の細胞間を連絡している細い細胞質の糸)でつながっている(原形質連絡は植物体の全細胞を連絡している)。原形質連絡は細胞壁を貫通しており、小分子やイオンが原形質連絡を通過できる。
●1655年、フック(ニュートンのライバルで、弾性についての法則を発見した物理学者。関係ないが、フックとニュートンと犬猿の仲で、ニュートンはフックの肖像画を火で燃やしたといわれる)が原始的な顕微鏡を用いてコルク切片に小さな孔を見つけ、『細胞(cell小部屋の意)』と呼んだ。実際に彼が見たのは死んだ細胞の細胞壁だったが、細胞という名は残った。
●1674年、レーウェンフックが原生生物の発見を報告した。フックがレーウェンフックを訪ね、レーウェンフックが「とても小さな動物たち」と呼ぶ微生物の世界を目の当たりにした時の彼の畏敬の念は想像に難くない。
●1833年、ブラウン(ブラウン運動の発見者でもある)はランを観察して『核』について記載した。
●1838年、シュライデンとシュワンが植物も動物も細胞で構築されているとする『細胞説』を提唱した(シュワンにシュライデンが「植物体が核を持つ細胞からなる」ことを話したとき、シュワンはその話が、自分が動物で見てきたのと非常に似ていたのでとても驚いたという。二人は急いでシュワンの実験室に向かった)。
●1855年、フィルヒョーは「細胞があるところ、必ず、その前に生存していた細胞がなければならない」とし、この概念を「細胞は細胞から生じる」という格言にまとめた。
●動画の中で、「(光合成で)できた炭水化物は、ミトコンドリアに運ばれて、そこで分解され」と言っているが、当然、炭水化物がそのままの形で丸ごと輸送されるわけではない。細胞質基質で解糖系によりピルビン酸になった後、ミトコンドリアへ輸送されていく。念のため。
●植物細胞同士は原形質連絡でつながっているので、巨大な多核体とみなすこともできる。
●原形質という用語は主に核と細胞質を指して用いられてきたが、現代では意味は薄れた(原形質に対して、細胞壁や細胞液、澱粉粒、色素などを、原形質の物質代謝の結果生じたものとして、後形質と呼んだ。が、この分け方は適切でなく、現代生物学においてもはや意味を持たない)。が、原形質連絡や原形質流動、原形質分離などの用語に名残を留めている。
問題:動物細胞と植物細胞のちがいを答えよ。
答え:植物細胞には発達した液胞、細胞壁、葉緑体がるが、動物細胞にはない。(小さな液胞は動物細胞にも確認されている)
問題:全生物がもつ物質をすべて選べ。
①水 ②DNA ③細胞膜 ④細胞壁 ⑤葉緑体 ⑥リボソーム
⑦DNA合成酵素 ⑧ゴルジ体
答え:①②③⑥⑦(動物細胞に細胞壁や葉緑体はない。菌類の細胞に葉緑体はない。原核細胞に核膜・小胞体・ゴルジ体・ミトコンドリア・葉緑体などの膜構造はない)
●さらにパワーアップしたい人は、菌類や原核生物(細菌・古細菌)のもつ構造を調べてみましょう。
*植物も菌類も原核生物も細胞壁をもつが、それぞれ主成分は異なる。
*基本的に菌類は葉緑体は持たない。菌類は従属栄養生物である。
*菌類の細胞と動物細胞は細胞壁の有無で見分ける(動物細胞に細胞壁はない)。
*植物の細胞と菌類の細胞は葉緑体の有無で見分ける(菌類の細胞に葉緑体はない)。
*菌類の細胞と原核細胞は核の有無で見分ける(原核細胞に核はない)。
#生物基礎
#高校生物
#細胞
関連動画