酵素
酵素とは
生体内の化学反応を触媒するタンパク質のこと。
(触媒とは、自身は変化せず、化学反応を促進する物質のこと)
簡単に言えば、酵素は体に必要なものを作るときの道具のようなものである。
はたらき
①複合体をつくる
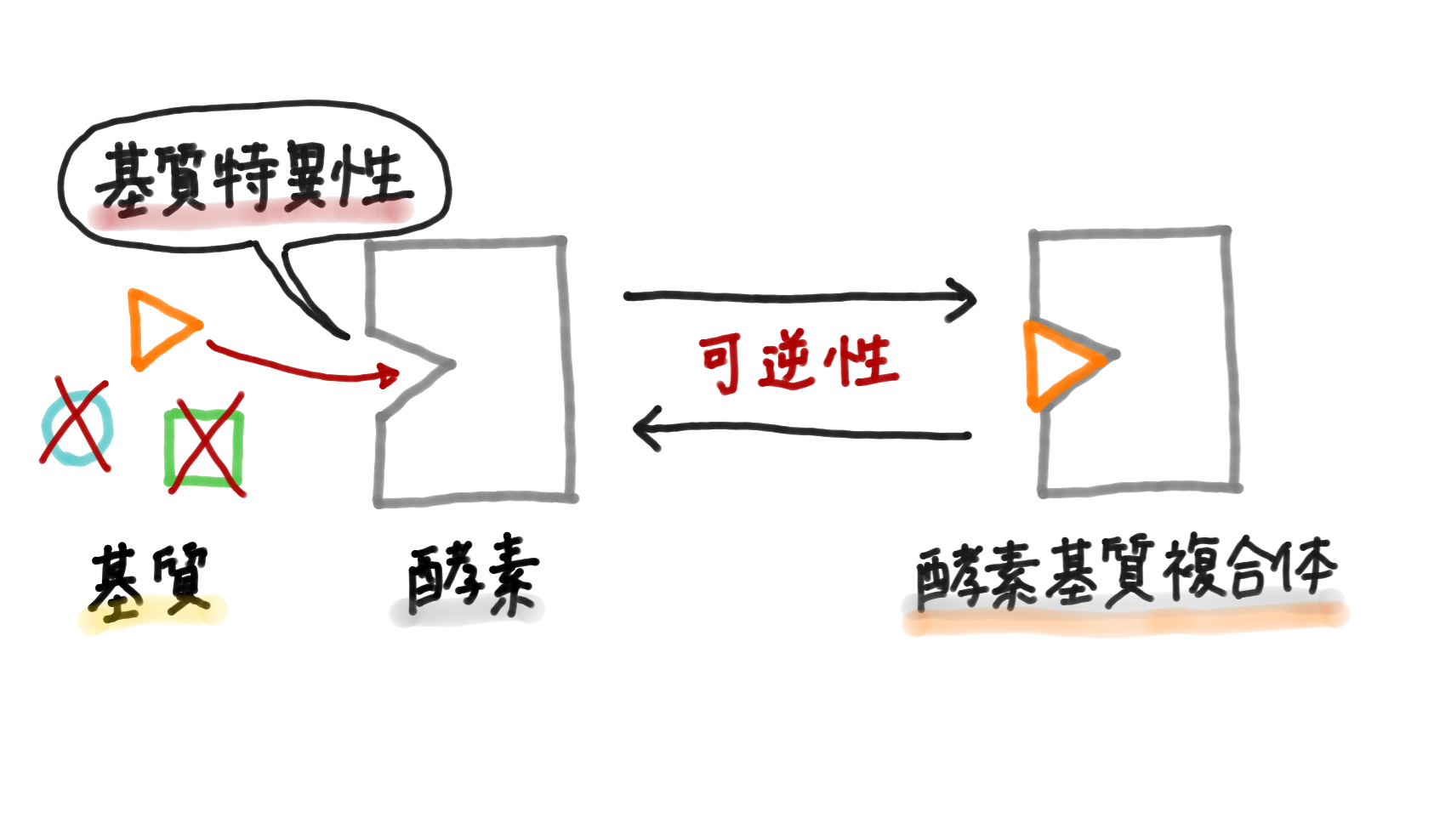
酵素には、これから化学反応する物質(=基質)がくっつく「活性部位」があり、ここの形にあった基質だけがくっついて複合体(=酵素基質複合体)を形成する。
形にあった基質しかくっつくことができない性質のことを、「基質特異性」という。
複合体を形成したら二度と離れることができなくなるのではなく、この時点では、一度くっついても離れることができる。
つまり、複合体をつくるはたらきは「可逆性」(=反応をもとに戻せる)ということができる。
②触媒作用
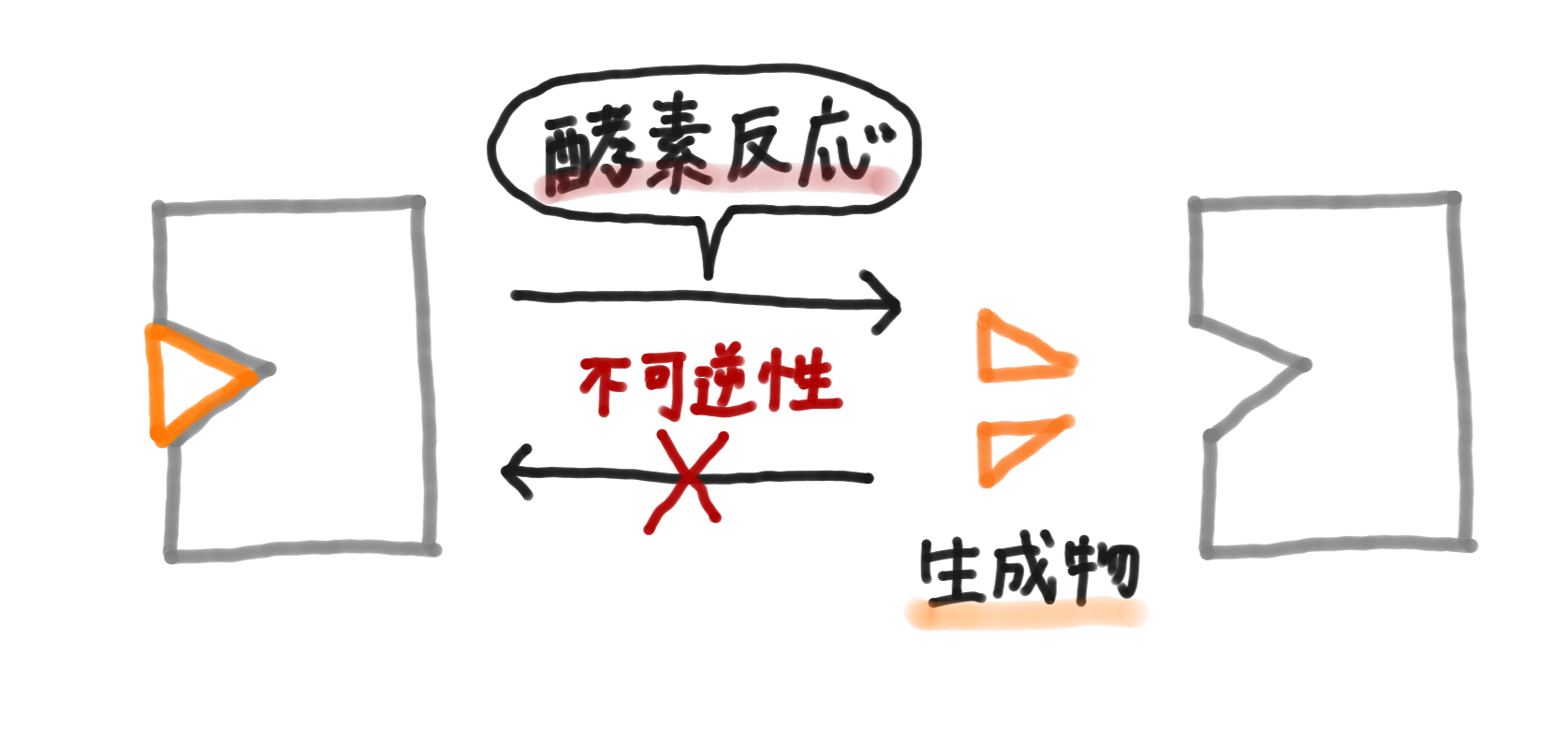 酵素基質複合体ができたら、酵素は化学反応により物質を生成する(=触媒作用)。
酵素基質複合体ができたら、酵素は化学反応により物質を生成する(=触媒作用)。
反応によってできた物質を、生成物という。
生成物をつくると、酵素はそれを元に戻すことはできない。
つまり、触媒作用は不可逆性(=元に戻せない)ということができる。
酵素の性質
酵素には、一番はたらきが活発になる温度やpHが存在する。
最適温度
酵素の温度と反応速度の関係は、以下のグラフのようになる。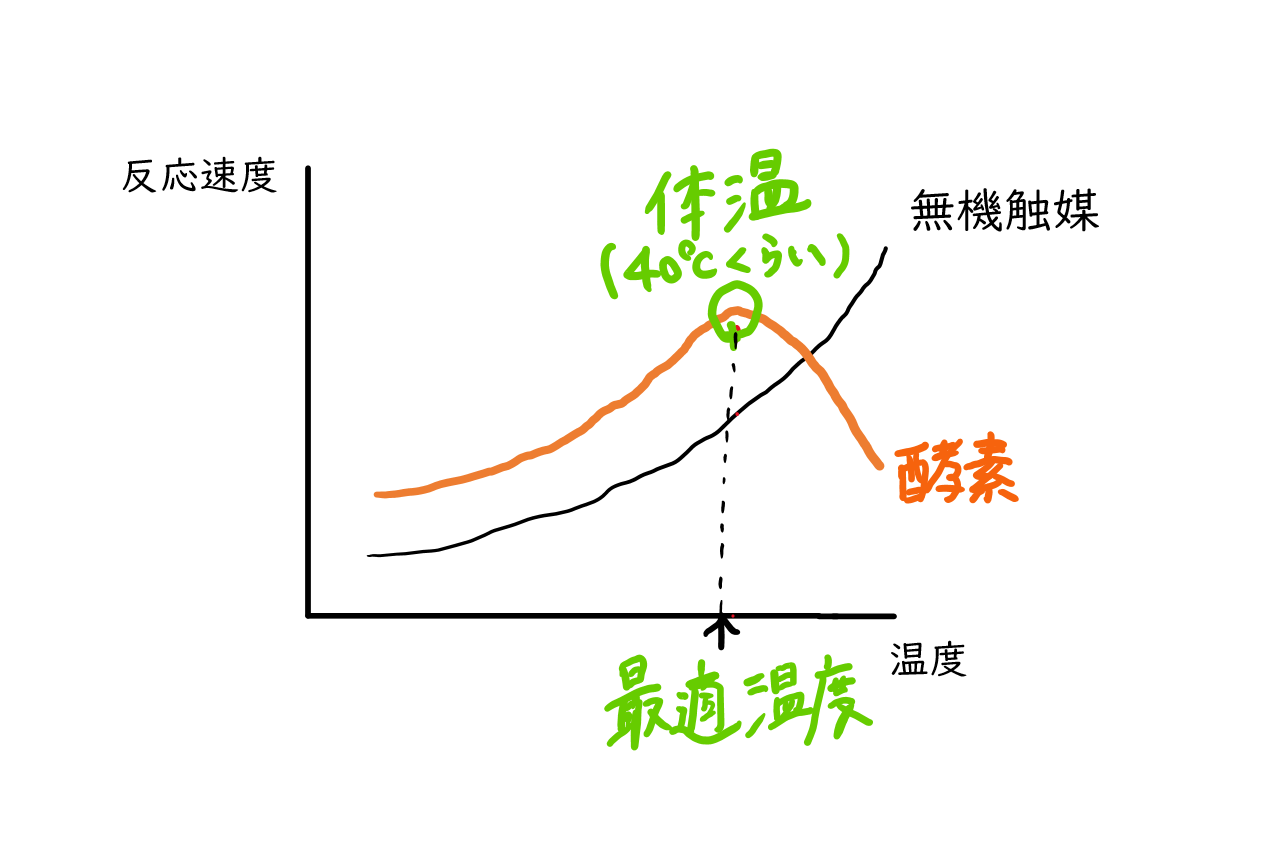
一般的に体内の酵素は、体温付近で最も反応速度が大きくなる。
それよりも高い温度になると、酵素は熱により変性し、失活してしまうので、反応速度が下がる。
(これはタンパク質の性質である)
最適pH
最適pHは、酵素の種類により異なる。
例えば、ペプシン、アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンの反応速度は以下のようになる。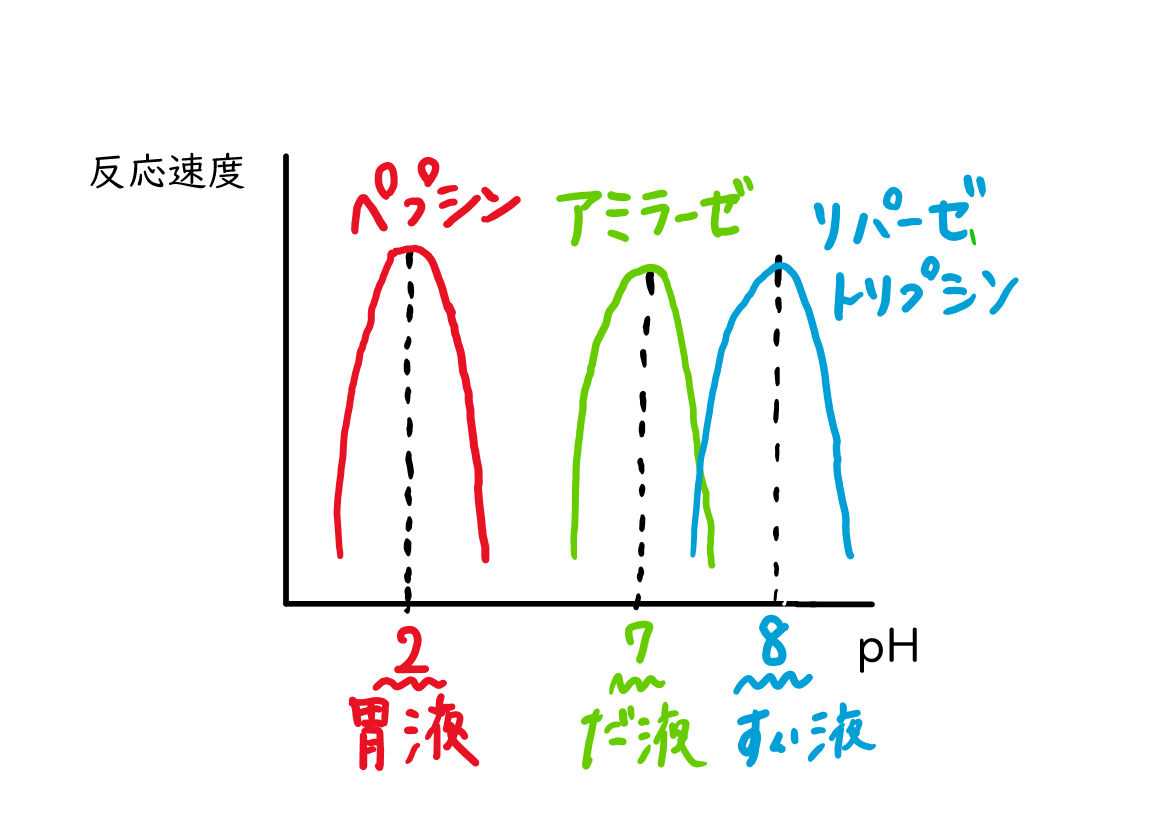
胃ではたらくペプシンは、胃液のpHで反応速度が大きく、
唾液に含まれるアミラーゼは唾液のpHで反応速度が大きく、
すい液に含まれるリパーゼとトリプシンは、すい液のpHで反応速度が大きい。
つまり、酵素は種類によりはたらく場所が異なり、その場に適したpHが最適となるということである。
酵素についてのわかりやすい解説動画はこちら!
関連動画
関連用語





