公害
だいたいのイメージ
「工場のせいで、周辺の住民が困る」というイメージを持とう。
たとえば、水俣病は、チッソという会社の工場の排水が原因で、水俣周辺で起こった環境問題なので、公害といわれる。
一方、地球温暖化は、あらゆる社会活動に原因があり、全世界で起こっている環境問題なので、公害とは言わない。
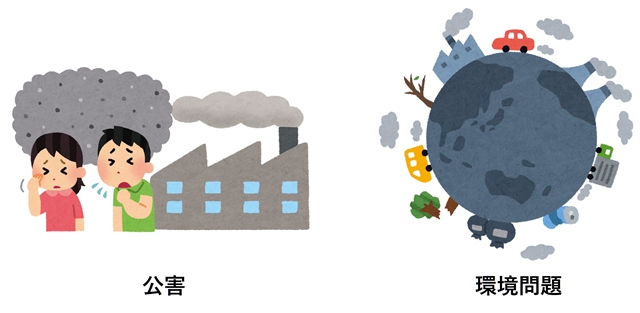
実際の定義
公害の定義は環境基本法に明記されており、
- 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
- 相当範囲にわたる
- 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
ということになっている。
日本では四大公害病が有名。
日本の公害対策
日本では、高度経済成長期まで、有効な公害対策は行われなかった。
最初の本格的な公害は足尾銅山鉱毒事件で、足尾銅山からの有毒な廃水や大気汚染によって周辺の環境に甚大な被害をもたらし、「公害の原点」といわれた。
高度経済成長期以降、全国各地で公害が発生するようになり、四大公害病は大きな社会問題となった。
これを受けて公害対策の機運が高まり、1967年に公害対策基本法が成立。1971年には環境庁を設置、1993年には環境基本法が成立し、環境問題への対応を進めてきた。
公害の類型
上記のように、公害の類型には法的な定義がある。
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
がある。
大気汚染は、四日市ぜんそくが有名。工場や自動車の排気ガスが原因になることが多い。
水質汚濁は、水俣病が有名で、工場や農地からの排水が原因になることが多い。
土壌汚染は、工場の排水や煤煙が原因となることが多い。栃木県の足尾銅山周辺では、銅の精錬工場の煙が周辺に強烈な酸性雨を降らせ、植物を全部枯らしてしまった。現在でも植物は十分に回復していない。
騒音や振動は、工場や工事現場周辺、鉄道や道路の沿線で特に多い。
地盤沈下は、主に地下水の過剰な汲み上げによって起こる。東京都や大阪府で多く、建物が傾いたり、洪水被害が拡大しやすくなるという害がある。
悪臭は、肥料工場や牧場の周辺でよくみられる。畜産業が関係するため、郊外や農村でもみられる公害といえる。
関連動画






