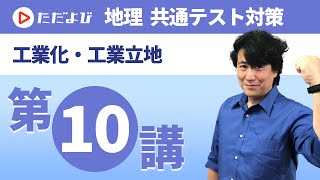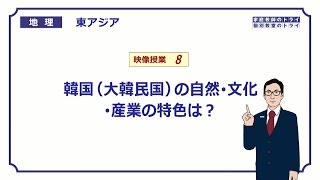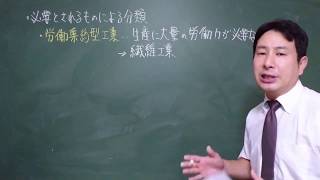輸入代替型工業化
簡単なまとめ
輸入に頼っていた工業製品を、国内生産で代替することで工業化を目指す形態。
戦後、多くの途上国でこの政策がとられたが次第に行き詰まり、1970~80年代以降は輸出指向型工業化を推進する国が増加した。
かつて、インド、メキシコ、ブラジル、アジアNIEs(1960年代)などで行われた。
経緯
国内で作れる工業製品は国内で作って、外国からの輸入を減らして、外国への富の流出を防ぎ、なおかつ工業化をして経済を成長させよう! というのが、輸入代替型工業化です。
工業化が始まる前の段階、農業や鉱業くらいしか産業がない国では、工業製品はほとんど輸入に頼っています。
工業製品は値段が高く、農産物などは値段が安いので、じゃあ経済を成長させるには工業化が必要ですねということになるのですが、もともと農業しかやってなかった国ですからお金も技術もないわけで、そんなに質の良い物を作ることはできません。ですから、いきなりバンバン輸出して世界でも戦える製品というのは作れないわけです。
しかし、国内で使うだけならそんなに質の良いものはいらないので、国内生産で十分。じゃあまずは、国内で使うものくらいは作れるようになろうぜということで進められたのです。
政策の具体的な内容
基本的に、国内産業の保護、外国製品・資本の排除が志向されます。
以下のような政策が一般的です。
- 外国製品に対する輸入関税の引き上げ、輸入規制など
- 国内資本を優遇し、外資の参入を規制
- 重要産業(鉄鋼など)の国有化、補助金など
- 為替レートを割高に設定
外国製品の流入を阻害することで国内製の製品の流通を促したり、国内資本の育成を優先したり、為替レートを操作することで原料の輸入にかかるコストを下げたりといったことをしているわけです。
問題点
輸入代替型工業化には、経済成長に限界があるという問題点があります。理由を説明しましょう。
国際競争力がつかない
一つ目には、経営が非効率になり、国際競争力がつきにくいという点です。
輸入代替型工業化では、政府が国内資本を手厚く優遇します。補助金も出ますし、輸入規制で外国製品との競争があまり起きません。さらに国営企業なら絶対潰れませんから危機感がない。要は甘やかされているわけです。
ですから、黙っていても製品が国内では売れ、ある程度までは成長できてしまうんですね。しかし、競争が弱いので製品の質はなかなか上がりません。
こんな甘えた経営では厳しい世界市場で通用するはずもなく、国内ではそこそこ売れても世界では全く必要とされないという状態になります。
市場が小さい
輸入代替型の工業化を進める国はもともと貧しい国ですから、国民もみんな貧乏なわけです。
収入が少なければ買い物もあまりできません。つまり商品が売れない。製品を作って売る側からしたら、物が売れなくて困る。
じゃあ外国に売ったらどうだと思うかもしれませんが、さっき説明したように国際競争力が低く、外国にも売れない。
国内ではみんな貧乏だから物が売れない。国際競争力がないから外国にも売れない。成長が頭打ちになってしまうのです。
貿易収支の悪化
輸入代替型工業化を推進する際、原材料の輸入コストを下げるために為替レートを意図的に自国通貨高に調整します。
しかしこれは裏を返せば、輸出するときに割高になるということを意味しており、国際競争力の低下を招きます。もともと強みを持っていた農産物などの輸出にも悪影響を与えます。
また、工業化が進めばその原材料の輸入量も増えますから、輸入も増加します。
この結果、輸出への悪影響と輸入の増加というダブルパンチで貿易収支は悪化しがちになり、経済へ悪影響を与えます。
技術力が成長しない
外国資本の投資を規制すると、外国に搾取されないという利点はもちろんあるのですが欠点も存在します。
もともと工業化が遅れている国ですので、技術力もない。ですから簡単な製品は作れても、高度な技術が必要な製品、例えば自動車なんかはまともに作れないのです。
外資が参入してくるというのは、生産技術も国内に持ってきてくれるということでもあります。国内の技術力アップのチャンスでもあるわけです。
このあたりの話は多国籍企業の項で説明しているので、そちらをご覧ください。
この用語を含むファイル
関連動画
関連用語