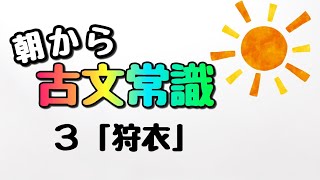古典時代の生活(誕生〜死)
古典時代の人の生涯
現在は平均寿命も上がり80歳くらいまでは生きているのが普通にも思えるが、古典時代はそこまで一生が長くはなかったようである。
そんな古典時代の人々の一生についてここでは時系列順に触れてみよう。
妊娠=出産(誕生)
-
命の誕生は今も昔も変わらずお母さんから生まれてくるため、子供を身籠る=妊娠するということが前提となっている。
-
妊娠すると、吉日にお寺にお祈りに行く。今も安産祈願と似たような感覚であろうか。
-
赤ちゃんが産まれると、生まれた日・3日目・5日目・7日目・9日目のいずれも夜に誕生祝いを行う。
-
このことを産養(うぶやしない)といい、50日目と100日目にも祝い事がある。
袴着の式
- 袴着の式とは3〜5歳の男女が初めて袴をつける儀式で、父親が紐を結ぶことが多いが親類の中でいちばんくらいの高い人が結ぶこともあったらしい。
 袴着(1)〈小笠原諸礼大全〉
袴着(1)〈小笠原諸礼大全〉
成人式
-
成人するために成人式を行うが、男性の場合は初冠(ういこうぶり)と言い冠を初めて被り、女性は初めて裳をつけるので裳着(もぎ)と言われた。
-
髪の毛もおかっぱ頭から元結で結ぶ髪上を行う。
-
成人年齢は今よりも低く、女性で12〜14歳ごろ、男性はそれより少し上の年齢であったらしいが、はっきりと決まっていたわけではないらしい。
結婚
-
成人後は、結婚をすることになる。
-
一夫一妻制の現代とは違い、一夫多妻制であったと考えられている古典社会では、夫が妻の元へかよう妻問いという風習があった。(ただし、一夫多妻制については現在も議論がなされており、もしかしたらこの先変わっていくかもしれない、最新の研究に注目!)
-
妻のもとに通うという点からすると、別居しているように思えるかもしれないが、同居していた例も見られる。
-
13世紀ごろから、嫁入りという現代の感覚に近いものになってきたとされている。
求婚
-
結婚を申し込む、つまり求婚するには、男性から女性への手紙が欠かせないものだった。
-
手紙には和歌が添えられ、その和歌の上手さと字の綺麗さ(良さ)が男性の品格を表し、良い結婚相手を得るために男性は熱心になった。
-
結婚が成立すると、まず男性が女性の元に3日連続で通い、泊まる。
-
3日目あるいは4日目に披露宴があり、その後吉日を選んで男性は女性の家から出勤する習慣もあったらしい。
-
ある期間を経てから妻は夫の家に迎えられる。
年齢ごとの祝賀
-
現在の還暦や米寿などの年齢における祝い事も存在し、40の賀以降10年ごとに祝い事があり、祝いの品の贈呈や祝宴を催した。
-
祝宴の際に立てる屏風は一流歌人に依頼して祝いの歌を貼り付けることが一般であったらしく、「賀の歌」 と言われる。
死=葬式
-
一生の終わりとして、亡くなった後には葬式が行われる。
-
入棺し、殯(もがり)という葬儀の準備が整うまで膳を備え経を読むことが行われる。
-
陰陽師に適当な日を占ってもらい、火葬場や埋葬場まで付き従って送る野辺送りをする。
-
火葬か土葬だったらしい。
-
死後49日の期間を「中有」(ちゅうう)もしくは「中陰」(ちゅういん)と呼ぶ。
-
死者の魂があの世にいかず、この世とあの世を彷徨っている=魂が落ち着いていない、とされていて、7日ごとに法事をした。人が死ぬと喪に服し、その期間は関係性などにより様々であった。
-
衣服の色も関係性などによって変わったらしい。
-
この期間は、酒や生くさいものを口にせず、音楽をやめ、魂の平安を祈った。
関連動画